|
「ちわ〜! 郵便部でーす」 昼下がりのラストガーディアン。穏やかな午後は、艦全体がのんびりした雰囲気に包まれていた。 「マッコイ姉さん宛の荷物なんだけど……」 小さな子供くらいなら1人2人軽く入りそうな段ボールを床に下ろし、郵便部の赤沢卯月は、首に引っ掛けていたタオルで汗を拭う。 「ご苦労様です。でも、マッコイ姉さんは……」 店番をしていた、アークセイバーチームの佐々山準が、レジカウンターから外に出て来て言う。 「あ、うん。知ってる。仕入れ出張中なんだってね。でも、中身が生ものっぽくってさあ。だったら、こっちに持って着て、冷蔵庫に入れといたほうがいいかなって」 「そうなんですか。ちょっと待ってくださいね」 小学生には、ちょっとばかり判断がつきかねる事項である。準は急いで倉庫にいる、ブレイブナイツの龍門水衣を呼びにいった。 「マッコイ姉さん宛の荷物って?」 特にそういった引継ぎは受けていないのだけどと、つぶやきながら、水衣が卯月の前にやってくる。 「これなんだけどさ」 ハチマキを締めなおした卯月は、足元に置いた段ボールを示す。中には液体が入っているらしく、揺らすとちゃぽちゃぽと音がする。梱包にも『生もの注意』と書かれてあった。 「……なるほどね。分かったわ」 水衣はうなずくと、配送伝票に受け取りのサインを記す。サインをしてもらった配送伝票を胸ポケットに突っ込んだ卯月は、 「重いから、あたしが運ぶよ」 と言って段ボールを持ち上げた。 リベンジ・ザ・モスキート! 夏の宵。勇者忍軍所属(?)の釧は、艦内の植物園にて、うとうとと舟をこいでいた。夢の世界とこちらの世界を行ったり来たり。とろとろまどろんでいると、ぷぅ〜んという虫の羽音が聞こえてきた。 隠し持っていたクナイを一閃させたのは、無意識の行動である。ふと浮上した意識のもと、薄目を開けて、今しがた己が切り捨てたものを見下ろす。 「──ッ!」 それを目にしたとたん、眠気は完全にぶっ飛んでいた。 釧が切り捨てたのは、巨大な蚊であったからである。 真っ二つに切り捨てたソレを鋼糸で縛り上げると──絶命しているとはいえ、それを直に触るのは御免だった──釧は、格納庫に向かった。 いつだったか、モスキートの呼称で呼んだ敵が、ラストガーディアンに現れたことがある。モスキートの呼び名の通り、それは30センチはあろうかという巨大な蚊の姿をしていた。 これの恐ろしいところは、血を吸った者の能力を完全にコピーし、なおかつ性格を反転させるというところにある。 結果、強気の者は弱気になり、勝気な者は常に泣きべそをかいているというような、そんな恐ろしい状況が作り出されてしまったのだ。 今、またあの悪夢が繰り返されようとしているに違いない。釧は、頭痛をこらえつつも、目的地へ急いだ。 大部分の照明はすでに落とされていたが、その一角。ウィルダネスよりの来訪者たちが生活している辺りは、煌々と明かりがともっている。 釧が姿を見せると、 「来たか」 酒場の店主は、やはりなという顔で、ぶら下げて来た獲物に視線を向けた。 「ここにも現れたのか」 「来たわよ〜。瞬殺してやったけど」 カウンターの止まり木に座っているトーコが、ざまあみろと言わんばかりに、ふんと鼻を鳴らす。 「天災は忘れた頃にやってくると言いますが……まさか、本当に来るとはね……」 釧が放り投げた巨大蚊の死骸に呆れたような視線を向け、イサムは肩をすくめた。放物線を描いて落下するそれをジャンクは、異能力で跡形もなく消してしまう。 「とりあえず、一晩起きてるか」 「そうねえ。前が前だから、今回もそんなにヤバいことにはならないでしょ」 この広いラストガーディアンをこれだけの人数でカバーするのはちょっと難しい。ジャンクなら、艦内の出来事は、たいてい把握できているので、モスキートの捜索も可能では? と思われたのだが── 「それがなあ。所詮、虫けらは虫けらってことなのか、変身する前は意識が希薄でうまく位置を捕らえられなくてな……」 「つまり、変身後を捕獲するか、足で探すしかないってことですか」 「なら、明日だな」 話をしながらジャンクが用意した酒に口をつけ、釧が言った。もちろん、異存の声があがるはずもなく、夜は静かに更けていく……。 朝である。まだ早朝と言っていい時間帯ではあるが、セイヴァリオンチームの古葉真人はコーヒーのいい匂いで目が覚めた。 「何だ……?」 ベッドの中で軽く身じろぎをしてから身を起こすと、 「おはよう! 真人お兄ちゃん!」 同室である倉星勇矢の元気な声がした。 「おはよう。勇矢君」 少年の背後に尻尾が見え隠れしているような錯覚を覚えつつ、真人は勇矢ににっこりと笑いかけた。 「真人お兄ちゃん、もうすぐコーヒーができるよ」 「勇矢君がコーヒーを?」 大きく瞬きをして問いかけると、少年は得意げに「うん」と首を縦に降る。 枕元の時計を確認すると、朝食にはまだ早い時間帯だ。食堂もまだ営業前である。しかし、せっかく勇矢が早起きをしてコーヒーを淹れてくれたのだ。起きないわけにはいかないだろう。 真人はベッドから降りると、簡単に身支度を整えた。 「はいっ。真人お兄ちゃん」 「ありがとう」 差し出されたコーヒーカップを受け取り、真人はそれに口をつけた。 「うん。美味しいよ」 にこり笑って見せると、勇矢は破顔一笑する。 「あのね、真人お兄ちゃんっ。外はとっても良い天気なんだよ!」 きらきらと両目を輝かせ、勇矢は言う。 ここは、雲の上なのだから、良い天気なのは当たり前なのだが……真人はそれらの言葉を飲み込み、 「だったら、今日も暑くなりそうだな」 無難な返事をした。暑くなるも何も、艦内は常に快適な温度に保たれている。空調が壊れでもしない限り、暑くなることはあり得なかった。 「うん。でね、こういう日は運動したくなるよね!」 「は?」 何を言い出すんだろうと、真人は目を点にした。勇矢は彼の反応など構わずに、真人の手を取ると、 「ジョギングに行こうよ! 真人お兄ちゃん!!」 強引に彼を外へ連れ出したのだった。 「お、おい?! 勇矢君!?」 前につんのめりそうになりながら、真人は部屋を出た。 真人が勇矢に連れ出され、ジョギングを終えた頃。勇者忍軍の頭、風雅陽平が目を覚ましていた。身支度を整え、姫を朝食へ誘いに行くことにする。 自室を出ると、左側からシャーッという音が聞こえてきた。何の音か理解できず、陽平は顔をそちらに向ける。 インラインローラースケートを履いた少女が、通路を疾走していた。髪はポニーテールで、耳からはイヤホンのチューブが伸びていた。裾の短いTシャツにミニスカートといういでたちの少女は、陽平に気づくと、 「グッモーニン♪」 小学生という年齢に似合わぬ熱烈な投げキッスを放ち、陽平の前を通り過ぎていく。  「おはよ……っつか、今のあれ──沙耶香だよな?」 フェリスヴァインチームに所属する、将来有望な大和撫子の姿を思い浮かべ、陽平は額に汗を浮かべる。 「……一体何があったんだ?」 変な物でも食ったんだろうか? と、いささか失礼なことを思いつつ、陽平は翡翠の部屋へ向かった。 少年の主君は、同じ勇者忍軍に所属している桔梗光海と同じ部屋で寝起きしている。 呼び鈴を押し「朝飯に行こうぜー」 まだ眠気覚めやらぬ声で呼びかける。と、部屋のドアが完全に開ききる前に、 「ヨーへー!」 少年の幼馴染でもある光海が青ざめた顔で、陽平を部屋の中へ招きいれた。 「どうしたんだよ?」 朝っぱらから何があったんだと、少年は幼馴染にたずねる。光海はかなり混乱しているらしく、ただ「あれあれ」と部屋の一点を指差すばかり。 訳が分からぬまま、陽平が視線を動かすと、 「ようへい、大儀である」 ベッドの上に腰掛けた主君と、その足元にぺたっと座り込んでいるもう1人の主君がいた。 「翡翠が分裂した?!」 驚く臣下に、2人の姫は揃って首をかしげる。 「何で2人もいるんだよ!?」 少年の問いかけに、姫はお互いに顔を見合わせ、 「知らない」 ステレオ放送で答えた。 「そんなことより、ようへい。わらわを迎えに来たのであろ?」  ベッドに腰掛けた翡翠は目を細めてにっと笑い、右手を胸の高さにまですっと上げる。 「どうなってんだよっ?!」 少年は主に背を向け、背後に立つ光海に悲鳴にも似た声音でぼそぼそと問いかけた。 「それを聞きたいのは、こっちの方よっ。朝、目が覚めたら翡翠ちゃんが2人に増えてたんだから! おまけに片方はあんな調子だし──!」 「2人とも、何をこそこそしておる。朝食に行くのであろ?」 ベッドに座る翡翠は、上げていた手を下ろし、不満そうに唇をへの字に曲げる。 「朝ごはん、行く」 床に直接座っていたほうの翡翠が立ち上がり、陽平の手を取った。もう1人の方は「うむ」と頷き、 「何をしておる。早ぅ手を取らぬか」 もう一度胸の高さにまで手をあげたのだった。 何がなにやらさっぱり分からぬまま、陽平は主君の意向を汲み取り、あいているほうの手で少女の手を取る。 「誰に聞けばいいんだろな?」 食堂に向かって通路を歩く陽平からは、一切の色が抜け落ちて見えた。さあ? と首をかしげる光海は、そんな幼馴染の姿に、こっそり涙したという。 「……何の用があるっていうのかしら?」 前の雇用主であるジャンクからの呼び出しに、天井裏の腹ペコ忍者(最近、待遇は改善傾向にあり)ココロは首をかしげていた。 普通に生活していれば、接点のない者同士である。呼び出すことも呼び出されることもないはずだ。 もしかしたら、またイベントがあって、トーコが何か企んでいるのかもしれない。胸のうちに抱える複雑な思いを知られてからというもの、彼女のペースに巻き込まれることが多い。 そして、それを戸惑いつつも受け入れている自分がいるのだ。ココロ自身気づかなかった、もう1人のココロ。それを彼女たちは簡単に暴き立ててしまう。 何故かチクリと痛む胸に手を当て、ココロは嘆息した。格納庫の酒場はもう目の前である。 「おはようございます」 酒場に顔を出すと、珍しく釧の姿があった。朝だというのに、トーコが起きていることも珍しい。 「来たわね」 「え、ええ。あの、何か……」 うふふふと不気味な笑いを浮かべたトーコが、緩慢な動きでココロの前に立った。今すぐ回れ右をしたい衝動に駆られたが、味噌汁の美味しそうな匂いに負けた。 「これ」 巨大な虫捕り網を差し出され、ココロは目を丸くする。 「え? あ、あの……?」 「覚えてるでしょ? アレがまた出たの」 巨大な虫捕り網。それは、胸の奥深く沈めた記憶を呼び覚ます。 「………………出たんですか? アレが…………」 そういうことであれば、この時間に釧がここにいる理由も察することができた。悲壮感漂う顔をトーコに向ければ、 「出たのよ」 トーコも苦しそうな顔で頷く。 「とりあえず、ここに被害者はいません。一晩、起きて近寄って来たのは片っ端から片付けていったので──」 ふわあとあくびをしながら、イサムが言う。 「頼みたいのは、ここに来なかったやつの捕獲よ。あたしらはちょっと仮眠とってから参加するから」 よろしくッ。びっと親指と立てたトーコは、いそいそとウッドデッキの方へ移動し、ごろんと横になった。 イサムもあくびをかみ殺しながら、ランド・シップへと入っていく。ジャンクと釧は、すでにウッドデッキにて睡眠中であった。 「あ、あの……」 救いを求めて、ココロはカウンターの中で料理をしているユーキに目を向ける。 「ココロちゃん、朝ごはんは?」 「まだ、です」 「んじゃ、食べてから仕事にしよっか」 「──はい」 カウンターに置かれた朝食は、純和風。味噌汁の匂いと焼き鮭の香ばしい匂いが、ココロのおなかを刺激する。 止まり木に座り、少女は「いただきます」と手を合わせた。その隣にユーキが座り、こちらも「いただきます」と手を合わせる。 「真人お兄ちゃん、どこに行っちゃったんだろう?」 艦内の通路を歩きながら、勇矢はキョロキョロと辺りを見回していた。 朝起きたら、部屋はすでにも抜けのから。少年が慕っている青年は、その戦闘力の高さから、個別任務を請け負い、艦外へ出て行くことも少なくない。 けれど、そういう場合は必ず勇矢に「仕事で出かける」と言ってくれるのだ。 「今日は、お仕事があるって言ってなかったと思うんだけど」 仕事の内容によっては、早朝から出かけたり、突発的に仕事を頼まれることも珍しくないので、そういう場合は前日に言ってくれるか、メッセージを残しておいてくれている。 「真人お兄ちゃん……」 ぐすっ。涙腺が緩み始めてきた。こんなことで泣くなんてみっともないと思い、少年は何とか涙がこぼれそうになるのをこらえる。 「どうかしたんですか?」 「うわっ?!」 背後からの声に、勇矢はびくっと肩を跳ね上げた。ドキドキする心臓をなだめながら後ろを振り返ると、少年よりも少し年上の少女、ココロが立っている。 彼女がどこの所属になっているのか、勇矢は知らない。生活班の所属という話も聞くが、本当かどうかは不明だ。 「ごめんなさい。びっくりさせてしまいましたね」 泣きべそをかいている勇矢に、ココロは謝罪する。 少年はふるふると首を左右に振った。ここだけの話、勇矢は彼女に苦手意識を持っている。うまく言えないのだが、ココロは何かが違う気がするのだ。 「涙出てますけど、何かあったんですか?」 「何でも…ないです。大丈夫です」 首をかしげる少女に答えた後で、勇矢は伏せていた視線をあげ、 「あの、真人お兄ちゃんを知りませんか?」 「真人さん……ですか? いえ、今日はまだお見かけしてませんけど──」 何かあったんですか? と知らないふりを装うココロ。勇矢に質問をしながら、十中八九、モスキートが絡んでいるだろうと、予測している。 トーコから虫取り網を渡されはしたものの、ココロはそれを置いて来ていた。というのも、今回は捕縛ではなく、見つけ次第亡きものに……ということだったからである。ここら辺から、前回の痛手がどれほどのものであったか予測できるというものだ。それはともかく、 「よければ、一緒に探しましょうか?」 控えめな口調で、少年に申し出てみる。 「えっと、あの……」 勇矢が返答に困っていると、 「OH! ジャパニーズ、生け花! ワンダフル!」 「ちょっと! あんたねえっ?!」 少年にとっては聞きなれた、ソフィア・ヴァレンティアの声が聞こえてきた。同じ声ながら、言っていることは、まるで違う。彼女の性格からして、1人芝居の練習をしているはずもなかった。 「ソフィアお姉ちゃん?」 何が起きているんだろうと、訝しがりながら、勇矢は声のする方向へ向かって歩き出す。ココロもその後についていった。 そこで見たものは、艦内生け花教室の生徒が活けたお花を見て感激しているソフィアと、彼女の行動を恥ずかしがるソフィア。 「ソフィアお姉ちゃんが2人?」 勇矢は、目をまん丸に見開いて驚いた。その横で、ココロはやっぱりかと、うなだれる。 「勇矢!」 少年のつぶやきが聞こえたのだろう。もう1人の行動を恥ずかしがっていたソフィアが、ぎょっとした顔で振り返る。 「OH! ユーヤ!! 今日もベリーベリーキュートですネー」 変な外国人風ソフィアは、ぱっと顔を明るくすると、勇矢に駆け寄り、ぎうっと抱きしめた。ついでに、挨拶のキスも、頬っぺたにンちぅっ。 「ソ、ソソソソふぃあお姉ちゃんっ!?」 抱きしめられただけでもイッパイイッパイなのに、さらに、頬にキスされたため、少年の頭からばふーっと蒸気があがった。 「ちょっ、あ、ああんんたねぇっ?! 何やってんのよ!? 何考えてんのよ?!」 驚いたのは、もう1人の方である。慌てて、少年をもう1人の自分から引き剥がしにかかった。 「OH! ワタシ、何も悪いコトしてませーん」 「良い悪い、じゃないわよ!」 2人のソフィアがかみ合わない口論をしているころ、 「朝っぱらから、どうしたんだい?」 背中に何かを背負った真人が現れた。 「真人お兄ちゃん!」 探していた人物にようやく会えて、勇矢の表情がぱあっと明るくなる。が、喜ぶ少年とは対照的に、真人は信じられないものを見たような顔になった。 「勇矢君が2人!?」 そう。真人が背負っているのは、電池切れ(体力0)で眠ってしまった勇矢なのである。 「えぇっ? どっ、どうなってるの?」 それを聞きたいのは真人の方であった。説明しようにも、真人自身、訳が分からない。困っていると、 「NO! ユーヤ、そこからおりるデェス!」 ソフィアが青年に近づき、強引に背中の勇矢を引きずりおろそうとする。 「ちょっとあんた! 何考えてるのよ?!」 彼女は、不機嫌さを隠そうともせずに真人の背中にいる勇矢を下ろそうとしているのだ。もう1人の方としては、到底甘受できる行動ではない。 「ソ、ソフィアお姉ちゃん。危ないよ」 「ちょ……ソフィア?!」 「おりるデェス!!」 こんな騒ぎの中でも、青年の背中で眠る勇矢は起きる気配がなかった。 「…………」 彼らのやり取りを見ていたココロは、ため息を1つ。考えるまでもなく、これはモスキートの仕業だ。 そうとは分かっていても、今、この場でモスキートを片付けるのは問題がある。どうしたものかと対応策を思案し始めたココロは、この場所にとある仕掛けがあることを思い出した。 「えっと、確か──」 郵便戦隊の青木神無に教わった手順を思い返しながら、通路の壁をどんどんっと叩き、最後に床をどんっと踏む。 ぱかっ! 「うわぁっ?!」 「キャアっ!?」 床に落とし穴が開き、真人と偽勇矢、2人のソフィアが開いた穴に飲み込まれた。 「真人お兄ちゃん!? ソフィアお姉ちゃん?!」 慌てて本物の勇矢も彼らの後を追いかけようとしたが、開いた落とし穴はスグに閉じてしまう。 「みんな、格納庫のジャンクさんのところにいるはずですから」 ココロは深々と一礼をして「それじゃ、私はこれで」 少年の前から去って行ったのであった。 「ココロ……さん……?」 お願いですから、僕に分かるように説明して行ってくれませんか? 少年の心中を察することなく、ココロの背中は通路の向こうに消えた。 当然のことながら、こんなことは序の口である。スポーツジムへ足を向ければ、 「むふふ。この上腕二等筋のキレ!」 「俺の大胸筋も見てくれよ」 姿見に全身を映し出し、あれやこれやとマッスルポーズを決める男たちがいる。惚れ惚れするぜ、などとつぶやいているあたり、ナルシスト度が高いようだ。 そんなモスキートたちの群れの後ろで、ブレイブナイツの龍門拳火が四つん這いになって嘆いている。 「やめてくれ。俺が一体何をしたっていうんだ……」 彼の偽者は、ナルシストの群れの中でも特にナルシー度が高いようだ。 「もっと日焼けしねえとな。こんなんじゃ、俺の筋肉の魅力は引き立たねえぜ!」 両腕を上に上げて、腹筋を際立ててみせながら、偽者拳火が言う。 「うるせー!」 後ろに向かって怒鳴った本物は、 「こんな姿、水衣姉ぇには見せられねぇ……」 己の境遇に涙したという。 場所が変わって、植物園のオープンカフェ。こちらの店先には、勇者忍軍の風魔楓とブレイブナイツの龍門水衣がお茶を楽しんでいた。 楓は、ピンクハウス系のフリルがたっぷりついたロングワンピースを。水衣は、フェミニンなロングキャミソールとレギンスといういでたちだ。本物なら、とうていありえない服装である。 「ふぅ。私、水衣さんが羨ましくてしかたありませんわ」 拳火の水衣に向ける好意は、とても分かりやすい。それに比べてこっちは……と、楓は小さくため息をつく。 「そうでもないわよ。向こうは、こっちが気づいてるって分かってないし。だったら、積極的にアプローチしてくれても良さそうなもんなのに、何か中途半端でさあ」 「それは、ぜいたくというものですわ。私なんて、どうアプローチすれば良いのか、見当もつかなくて……っ」 ストローの先を噛みながら、楓は唇を尖らせる。 どうやらこの2人、乙女らしく恋の悩みについて語り合っているところのようだ。 ちなみに、本物はこの場にはいない。 本物の楓は武道場にいて、双子の兄である柊と共に、 「2人とも何てスバラシイのっっ!!」 愛情表現の大切さに目覚めた椿の抱擁から逃れられずにいた。 2人とも新手の試練かと、体中に鳥肌をたてながら我慢している。 「あなた達は、私の自慢です! 誇りです!」 椿は、ボロボロと涙を流しながら、双子をぎゅむぎゅむと抱きしめ、頬ずりをする。 姉を疎んじている双子にしてみれば、拷問にも等しい時間であった。 水衣のほうはというと、購買の手伝いをしていて、 「水衣さんっ。僕と一緒にお茶しませんか?」 同じく購買の手伝いに来ている佐々山準に口説かれていた。少年は、水衣の手をそっと握り、わずかに潤ませた目で彼女を見上げている。まるで、子犬にすがりつかれたみたいで、少女は握られた手を振り払えずにいた。 「あっらあ? どうしちゃったのかしらねえ」 たまたま現場に居合わせた西宮麻紀は微苦笑を浮かべながらも、しっかりとカメラのシャッターを押している。 「写真撮ってる場合じゃねえだろ! っつか、何やってんだよ!? 準?!」 麻紀と同様、たまたま現場に居合わせたおとーさんこと剣和真は少年と少女、両方に突っ込みを入れた。 「誰か説明できるやつはいねえのかよ?!」 『ソウデスネー』 「くはっ……!」 はぐれカズマ君1号の合いの手に、和真の腰は完全に砕けたようである。 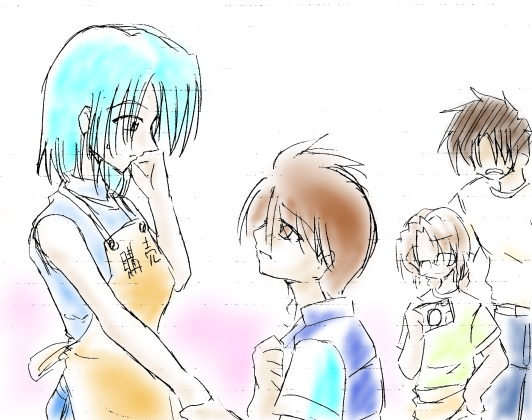 「水衣さん。僕とお茶、ダメですか?」 「えぇと……」 どう返事をしたものやら。夢にも思わなかった事態に、水衣はただただ視線を彷徨わせるのみであった。 「ささ、ジュン! お茶が入りましたよ!!」 「ありがとう。サヤお姉ちゃん」 購買でそんな困ったさんなやりとりが行われているとは露知らず、準はサヤと一緒に、サロン室でお茶をしていた。 「おいしー」 「メイアさんから秘密のレシピを教えてもらったんですよー」 美味しそうに目を細める準を見て、サヤも幸せそうに微笑む。 「和真兄ちゃん、遅いね。麻紀さんを呼んでくるって言ってたのに」 「そうですねえ」 2人は不思議そうに首をかしげていた。 「〜フンフフ〜ン♪」 鼻歌を歌っているのは1人の少女。彼女の足取りはいたって軽やかで、かなり機嫌が良いようである。 ヘッドドレスを頭にのせて、小花模様が散るワンピースにウサギの縫いぐるみを持つという、いわゆるロリータスタイルに身を包んだのは、ブレイブナイツのユマ。  「まっ、やめ……! お願いですからやめてください〜」 ロリータ・ユマにすがりつくのは、いつもの真っ黒スタイルのユマである。真っ黒スタイルユマは、半泣き状態で、「待って」を繰り返し、人が通り過ぎるたびに、 「みっ、見ないでください〜」と泣いている。 ロリータ・ユマはもう1人の反応などどこ吹く風といった感じで、通り過ぎる人々に 「御機嫌よう♪ 素晴らしいお天気ですわね」 にっこりと微笑みかけつつ、愛敬を振りまいていた。 「私が何したっていうんですかー!」 目じりに涙を浮かべながらも、ユマはロリータ・ユマを引きとめようとがんばっていた。 ロリータ・ユマにずるずると引きずられながら、少女は食堂の前を通り過ぎる。涙目のまま食堂の中を覗き、仲間の姿を探す。助けを求めての行動だったのだが…… 「志狼さん! エリィさ……」 ぱっと表情を輝かせたのも、つかの間。 「あーかったりィ」 食堂の椅子にぐてぇっと大の字になって座る志狼を叱り飛ばす志狼。その隣では、エリィが、 「こらこらこらぁっ! 誰と喋ってるのよ!?」 顔を俯かせて、不気味にくすくす笑ったり、ぶつぶつ喋ったりしているエリィに向かって怒鳴っていた。 ぶつぶつエリィは、金髪を結ばずに流れるままにしている。そのせいか、目元がはっきり見えず、余計に不気味さがましていた。  「お2人も苦労してるんですね」 目じりの涙が、ぽろりとこぼれる。ロリータ・ユマの対応は1人でがんばるしかない。 「負けませんっ」 なぜなら、彼女も勇者なのだから!! 艦内のあちこちで、偽者騒動が起こっていても、アナウンス部の木葉則子のペースは揺るがない。本人の性格ゆえか、回りの騒動も「大変ですねえ」という一言で大抵流してしまえるからだ。 出勤すると、先輩の北都仁美が2人になっていて驚いたけれど。2人の先輩は、性格が対照的だったことに2重に驚かされたけれども。 「仕事がはかどるわ……」 もう1人の先輩、安部由希子は、どんなときでもクールであった。 由紀子がそういうなら、大丈夫なのだろうと則子は納得し、平常心を取り戻したのである。回りに影響されやすい、彼女ならでは……といったところか。ちなみに分裂した当人はというと、 「私が2人! これは、神様がくれた幸せの贈り物〜。そんなわけで、行ってきまあすっ」 スキップしながら、どこかへ行ってしまった。待っててねー、私の美少年―♪ なんて叫んでいたから、まぁどこへ行ったのかは、大体想像がつく。 「いいんですか、安部先輩?」 「もう1人いるし、人員は大丈夫。でも、チーフには報告しておくわ」 「はあ」 肩越しに振り返れば、真面目なほうの仁美が淡々とシフトチェンジ間近のアナウンスをいれていた。 増えたのが、仁美ではなく由希子や三咲静だったなら、アナウンス部も上の物を下にの大騒ぎになっていたのだろう。そういう意味では、被害者が仁美であってよかったといえる。 そんなわけで、アナウンス部の業務には何の支障も出ずに、お昼になった。 「すみません、それじゃ……」 「いいわよ。楽しんでらっしゃい」 恐縮する則子に、真面目仁美はにっこり笑う。背丈こそ小さいままではあるが、こうやって余裕のある笑みを浮かべる彼女は、年相応に見えた。 「杉山さん、喜んでくれるといいんだけど──」 彼女がブースを離れたのは、世間でいうところの恋人である撮影班所属の杉山と、一緒にお昼を食べる約束をしているからだ。 待ち合わせ場所は展望廊下である。そこで、則子は一計を案じ、弁当を作ることにした。 出来は、もうちょっとがんばりましょうくらいだが、愛情だけはタップリこめたつもりだ。 「あ、杉山さんっ!」 展望廊下のベンチに座っている青年を見つけ、則子はスピードをあげた。いつもと違って不機嫌そうなのは、何か仕事でトラブルでもあったせいだろうか。 「すみません。お待たせしました!」 ぺこりーと頭を下げてから、則子は杉山の隣に座った。 「今日はお弁当を作って来たんです。その……見かけはちょっと悪いですけど、味の方は──!」 膝の上に弁当を乗せて、則子はいそいそと包みをとき始める。杉山との付き合いが始まってからすぐに購入した男性用の大きな弁当箱を、則子はにっこり笑って差し出した。 杉山は黙ってそれを受け取り、弁当箱の蓋を開ける。と、本人が言っていたとおり、中身は見かけに少々の難があった。 焦げた卵焼きに、真っ黒になってしまった唐揚げなど。プチトマトは洗っているうちに、ヘタが取れてしまったものもあった。 お口に合えはいいんですけどとは、とても言えない出来栄えである。則子は恥ずかしさに顔を赤らめ、うつむき加減になりながら、 「この次はもっとがんばりますから……」 決意を恋人に伝えた。──が、杉山はいつまでも無反応のままである。不審に思った則子は顔を上げ、 「杉山さん?」 隣に座る青年の顔を覗き込む。彼の横顔は弁当を渡す前よりも不機嫌度が上がっているようにみえた。 何か彼の気に障るようなことをしただろうか。 不安に思った則子がさらに声をかけようとしたその時、 「こんな飯が食えるかぁーっっ!!」 杉山が爆発。則子が手渡した弁当をぺいっと通路に放り投げた。 「嘘……そんな、酷い……」 一生懸命作った弁当が宙に放り出される様が、則子の目にはスローモーションに映る。 「うわぁぁぁっっ!!」 ぼろぼろと涙をこぼし、則子はその場から走り出した。膝の上に乗っていた、自分の分の弁当も通路に放り出される。 「杉山さんのばかぁ……っ」 子供のように泣きじゃくりながら、則子は通路を走った。回りなんて見ていない。どこに向かって走っているのかも、分かっていないのだ。 どんっ。わき目もふらずに走っていたから、誰かとぶつかったらしい。 「ふぇ。あ、ごめんなさ……杉山さん!?」 則子がぶつかったのは、たった今別れてきたばかりの杉山だったのだ。 「木葉さん? どうかしたのかい?」 驚いたように目を丸くする杉山には、いつになくまぶしい。動くたびに、キラリキラリと光っているように見えるのは、則子の気のせいだろうか。 「待ち合わせの時間に遅れた僕を探しに来てくれたのかな?」 青年は申し訳なさそうに眉根を寄せ、則子の涙をそっと親指で拭った。 「ごめんよ。待ち合わせに遅れたばっかりに、君に寂しい思いをさせたみたいで。僕は何て罪深いんだろう」 「え……あ、あの……さっきの、あれ? ど、どうなって……?」 ぎゅうっと手を握られた則子は、後ろと目の前にいる杉山を交互に見比べる。驚きに何度も瞬く瞳に、 「うっわー! 遅刻だぁ〜っっ!!」 ばたばたと走りすぎて行くもう1人の杉山が目に入った。 「す、杉山さんが2人?」 先ほどのショックも重なって、則子の何かがGENKAIを突破した。 「も、何がどうなってるのよぉ〜」 「木葉さん!?」 へなへなとその場にへたり込む則子を、キラリ・杉山が慌てて支える。 ラストガーディアン内で起きた混乱は、まだまだ収まりそうにない。 「くすくすくす。キューピッドさん、キューピッドさん……」 「こらこらこらぁ! こんなところで、そんなことをするなあっ!」 食堂にて、1人キューピッドさんを始めてしまったダウナー・エリィをもう1人のエリィが叱る。 「お前、ごそごそやってると思ってたら、そんなことしてたのかよ。よくやるよなー。感心するよ。俺なんて、息すんのも面倒くせぇのに」 「だったら、今すぐヤメロよ! 息するの!! 誰もお前に是非息をしてください、なんて言わねえからよ!!」 タイダー(怠惰)志狼へ、もう1人の彼が指をわきわきさせながら、怒鳴った。 叱り、怒鳴る少年少女の心はただ1つ。 「誰か何とかしてくれぇっ!!」 事件は、時が解決してくれるのを待つのみなのか。 ああ。正義の味方よ、今何処。 「……どうやら、ここが発生源らしいな」 購買の倉庫に侵入したジャンクは、内側から破壊されている荷物の中を覗き込んだ。中身は水槽のようで、今もなおちゃぷちゃぷと水が揺れている。 「ここに幼生がいたということですか……」 しゃがみこみジャンクの横で、立ったまま荷物を見下ろしていたイサムがやれやれとため息をつく。 荷物の中身は水だけになっており、中にどれだけの幼生がいたのか、見当もつかない。成虫の大きさが30センチほどだから、幼生がその半分の大きさだと考えた場合、30匹ほどは入っていそうである。 「ふん。何匹潜んでいようが、発見次第、即始末すればいいだけの話だ」 「まー、そうなんだけどねぃ」 くだらないと言いたげな釧の言に、トーコはぽりぽりと指で頬をかいた。まあ、彼ほどの技量があれば、抹殺の瞬間を常人に見られるようなヘマはすまい。 「しばらくは警戒態勢を続けたほうがいいだろうな」 「そうですねえ」 立ち上がったジャンクの意見に、反論は出なかった。 第2のモスキート事件は、まだ始まったばかりである。 「すっ、杉山さんが3人!?」 昔の頑固一徹風な杉山と軽い杉山。そして、則子が最もよく知る杉山。 「則子!」 「木葉さん」 「木葉さん〜」 3人の杉山から名前を呼ばれ、則子は戸惑うばかり。 (先輩、助けてください〜!) こんな時最も頼りになると思われる女、北都仁美(本物)はというと、 「じゅるじゅる。何だか知らないけれど、ちみっこが増えた〜。うふ、うふ、うふふふふふ」 どす黒いオーラをあたり構わず撒き散らし、ちみっこ観察に余念がなかった。 「あぁ、なんて幸せなのかしら」 今の状況は、彼女にとってパラダイス、らしい。 正義の味方、急募。そんな張り紙が、ラストガーディアンのいたるところで見られるようになったのは、その日の夕方であった。 オマケ 「らんらららあ〜ん♪」 アナウンス部北都仁美はご満悦であった。神様がもう1人の自分をくれたおかげで、今日1日たっぷりと少年たちを堪能することができたからである。 「たっだいまー!」 ご機嫌なまま、アナウンス部のブースに入っていくと、すでに遅番の三咲静が来ていた。ブース内には、自分の分身と由紀子、則子(なぜか冷えピタをオデコに貼っている)がいる。 「静ー! どうしたの? 早いじゃない」 いつもどおりタックルを仕掛けに行くが、静は冷ややかな声でこう言った。 「どちら様?」 「え?」 途中でぴたり動作を止めてた仁美は同僚を見上げ、 「やっ、やだなーもう。そんな冗談、笑えないんだからぁ」 ぱたぱたと手を振りつつ、一応名を名乗る。すると、 「北都仁美なら、そこにいるわ」 もう1人の仁美を指差しつつ、静は言った。もう1人の仁美は、「どうも」と落ち着き払った様子で頭を下げる。 「やっ、やだなぁー。そっちも私だけど、本物は私。偽者さんは、もう帰っていいわよ〜。神様にありがとうって言っといてね」 もう1人の仁美に手を振る彼女であるが、もう1人はてこでもそこを動きそうにない。ひくひくっと頬を引きつらせる仁美に、さらに追い討ちがかかった。 「さ、部外者は外に出てください」 静が仁美の背中を押して、ブースの外に出そうとするのである。 「え? あ、ちょ……ちょっと……え? そんな……ゆ、ゆっこ〜? のん子ぉ〜?」 後輩に助けてくれと視線で訴えるが、2人はさっと目をそらす。 「そ、そんなっ!」 目じりに浮かんだ涙をぎゅっとこらえ、仁美は宙を舞う! 「コピーロボットは、鼻を押せば人形に戻るんだからぁっっ!!」 もう1人の自分の前にオール10点の着地を決めた仁美は、ぽちっと鼻を押す。 「あ、あれ?」 当然のことではあるが、彼女はコピーロボットではないので、鼻を押したところで元に戻るはずがない。ふにふにふにと何度も鼻を押す仁美だが、戻らないものは戻らないのだ。 「……あの、やめてください」 もう1人の仁美は、静かに怒りながら、鼻を押しまくる手を振り払う。 「気が済んだ? だったら、部外者は外に出てちょうだい」 地蔵のように固まってしまった仁美を、静はさっさとブースの外に追い出したのだった。 「あ、あの……幾らなんでもこれはちょっと……」 静の仕打ちに則子は、おろおろとブースの外と彼女とを交互に見比べる。 「大丈夫よ。どうせ、2、3日もあれば立ち直るわ」 ふんっと鼻を鳴らし、静は「それじゃ、今日の引継ぎをお願い」 クールビューティー、健在なり。 「うぇっうぇぇぇぇ〜っ。酷いよーあんまりだぁ〜」 ブースの外に追い出された仁美は、そこに膝を抱えて丸くなって子供のように泣いていたという。 |