ドリームナイツの橘美咲は、1人観客席に座って劇を見ていた。舞台中央には緑色の葉をつけた一本の木があり、その下で妙齢の女性と男性が語らっている。 「この桜が咲く頃には、必ず帰ってくるから」 女性の手を強く握り締め、男性は舞台袖に引っ込んでいく。 「待っているから! ずっと……ずっと待っているから!」 葉桜の下で、女性は男性の消えた方向に向かって大きな声を張り上げる。 「洋介さん……待っているから……」 彼女のつぶやくようなセリフと共に、舞台は暗転した。 「……これは夢……だよね?」 「そう。これは夢」 真横からの答えに美咲はうわっと小さな悲鳴をあげる。声が聞こえるまで、そこに人がいるとは思わなかったからだ。 「わらわは清」 観客席に座っていたはずなのに、美咲はいつの間にか暗闇の中に立っていた。 「きよ……さんですか?」 清と名乗った女性は、美咲よりも2つ3つ年上に見えた。日本髪を結い、桜模様の着物に袖を通している。 美咲の問いに、彼女はうなずいた。清はその場に膝を折って座ると、いきなり美咲に頭を下げた。 「夢の騎士殿! 不躾ながらお願い申し上げる。八千代を助けてたもれ」 「えっ? やちよさんて……?」 もしかして、先ほど舞台に出ていた女性のことだろうか? 美咲が確認しようと口を開きかけたとき、 「お頼み申します。どうか、どうか八千代を……」 清の声がだんだんと遠ざかっていた。どうやら、目覚めの時を迎えようとしているらしい。 「まって! まだ────」 美咲の声は、彼女に届かなかった。 ぱちっと開いた目にぼんやり映るのは、すっかり見慣れてしまったラストガーディアンの天井だった。 桜吹雪の終わる頃 「──っていう、夢を見たんだけど……」 朝食の席で、美咲は同じドリームナイツの仲間たちに今朝見た夢の話をしていた。 「清さんに八千代さん……ですか」 話を聞き終えた田島謙治は難しい顔で、腕組みをする。助けてといわれても、美咲の見た夢からは、八千代という人がどういう状況にあるのか、さっぱり分からない。 「その舞台にあったっていう、桜も関係してそうだけどな」 大神隼人の意見に、謙治は「そうですね」と頷く。 「それに、洋介という名前も聞き逃せません」 「八千代……八千代……」 「どうしたの、麗華ちゃん?」 1つの名前をずっと繰り返し口にしている、神楽崎麗華に、美咲は首を傾げた。 「ちょっとね。どこかで聞いたような気がするのよ」 眉間にシワを寄せて、少女はどこだったかしら? と小さくうなる。 「清、八千代、桜と洋介……調べて何か出てくるといいんですが──」 言いながらも、謙治は難しいだろうなあと内心で大きなため息をついていた。 「あれ? 謙治さんたちも清姫櫻の調査に行くんですか? だったら、早く行かないと」 「え?」 ふいに背後から投じられた声に、謙治が振り向く。そこには、ブレイブナイツの後発組と共にこちらの世界にやってきた獣耳尻尾の少女、鈴がいた。5段重ねの弁当箱を持ち、少女はぱちぱちと瞬きをしている。 「違うんですか? 清って名前と桜って言葉が聞こえたから、てっきり……」 「その話、詳しく聞かせてくれるかな?」 「あたしも良くは……えっと、拳火兄と水衣姉が知ってると思うんですけど……」 2人は定期輸送便の発着場で、鈴が来るのを待っているはずである。 「じゃあ、そっちに行こう。場合によっては、俺たちもついていくことになりそうだしな」 「そうね」 彼らの抱えている事情が分からず、鈴は頭の上でクエスチョンマークが奏でる行進曲を聞いていた。 鈴と一緒にドリームナイツが発着場にゆくと、拳火と水衣が人待ち顔で立っているのが見える。 鈴が呼びかけると、2人は表情を緩めた。 「何だ? ワザワザ見送りか?」 妹分の後ろを歩いている4人に気づいた拳火が口角を持ち上げて笑う。 「そんな訳ねえだろ。聞きたいことがあるんだ」 「鈴ちゃんからちょっと聞いて……清姫櫻の調査ってどういうことかな?」 訝しげに目を見張る水衣に、美咲は夢の話を語って聞かせる。黙って話を聞いていた姉弟は「なるほど」と首肯した。 「そういうことなら、一緒に行ってもらったほうがいいかも知れないわね」 水衣の言葉に重なるようにして、定期便の出発を告げるアナウンスが流れた。 「ヤベ。行くぞ、鈴!」 持ってきた弁当箱をいそいそとリュックに詰めている鈴を小脇に抱え、拳火が走る。 「こっちの説明は、中でするわ」 弁当を詰めるのに、鈴がリュックの外へ出していたレジャーシートなどは水衣が引っさらっていく。 中々のコンビネーションである。 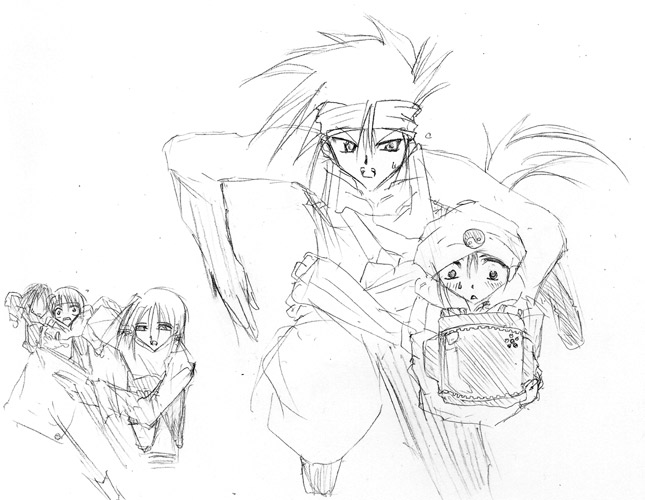 ドリームナイツも彼らに続いて、定期便に駆け込んだ。 定期便に乗り込んで、ちょっと一息をついた頃、 「私たちは、清姫櫻そのものを調査しに行くわけじゃないの」 水衣が話の続きをはじめた。鈴はぱたぱたと尻尾を揺らしながら、楽しそうに荷造りをしている。鼻歌なんかを口ずさんでいるところから、お花見か何かと勘違いしているのでは? との疑問も浮ぶ。それはさておき、 「ここ最近、ある場所で不審人物が目撃されてるらしい」 水衣の後を受け継ぐ形で拳火が口を開いた。 普通ならば、この不審者の目撃情報は警察レベルで処理されるものなのだが、 「その姿がアンドロイドっぽいというか戦隊ヒーローっぽいっていうか……」 「調書を見せてもらったんだけど……中には番組の撮影なら事前に通達があるべきじゃないのかっていうようなクレームもあったわ」 「誰かの悪戯とか、そういう可能性はないんですか?」 謙治の疑問ももっともだが、そういう可能性も視野に入れての調査なのだと水衣は言う。 「これを見て。鈴──」 「あ、うん。はい」 姉と慕う人に促され、鈴はリュックの中から一枚の地図を引っ張りだした。ちょっとしわしわになってしまったそれを丁寧に伸ばしてから水衣に手渡す。 「これは……?」 広げられた住宅地図には、沢山のバツ印がつけられている。このバツ印が不審者の目撃場所なのだろうと推測がついた。 「……ねえ、このバツ印って……」 「この神社を中心に目撃されているのね」 麗華が指差す神社の名前は、清姫神社。麗華の記憶では、この辺りは高台になっていて高級住宅街になっているはずである。 「この神社にあるのが、清姫櫻よ」 ご神木として祭られているほか、一本桜としても知る人ぞ知る名木なのだそうだ。 「不審者の目撃情報が寄せられるようになったのは、この桜の開花時期とほぼ重なるそうよ」 それに、桜が開花する前、この桜を中心に微弱ながらも不可思議なエネルギー反応も観測されているという。 納得顔で頷いた隼人は、ふと顔を上げ 「……3人だけで調査なのか? 志狼たちはどうしたんだ?」 疑問を口にした。とたん、拳火と水衣は決まり悪そうな顔で、顔を見合わせる。 「場所が住宅街だから、志狼さんとブリットさんは遠慮してってことになったそうです。その……武器が見えちゃうから。陸丸は特訓の予定をびっちり入れちゃったって言ってたし、ユマさんは研究に没頭中で……」 2人に変わって説明したのは鈴だった。 「でも、考えてみれば俺たちだけってのはちょっと難しいとこもあったかもな」 人差し指で頬をかきながら、拳火がつぶやく。 「そうね。私たちの住んでいるところと大きな違いがあるわけじゃないけど……」 地元慣れしている者がいるのといないとのでは、心強さが大違いである。 輸送機は間もなく着陸するようだ。 「うわあ……!」 「凄いわね」 現地に到着した一行は、清姫櫻の存在感に圧倒されていた。彼らがいるのは、高台の下の方。これから、坂を上って行かなくてはならないのだが── 「確か一本桜だって言ってましたよね?」 眼鏡の奥の瞳をまん丸にし、謙治がつぶやく。その声を聞き、生唾を飲み込んでから、 「ああ、そのはずだけどな……」拳火がうなずいた。 下から見上げる桜色の塊はどう見ても1本の木によるものとは思えない。 「ここで見上げていてもしょうがないわ。行きましょう」 「神社に行ったら、もっとすごいんだろうね」 先頭に立って歩きだした麗華を追いかけ、美咲が言う。 花見に来たわけじゃないんだぞと、隼人が釘を刺すより早く、 「きっと、もっとすごいよね。水衣姉」 楽しみだなあと、鈴が大はしゃぎで駆けだした。片手でリュックの肩紐を、もう片方の手で獣耳隠しのため、目深に被った帽子を押さえ、急勾配の坂をものともせずに走っていく。 「慌てて転ばないでくださいよ!」 謙治が注意すると、「だ〜いじょーぶ!」 元気に手を振りながら、少女は走っていく。 残された6人は、しょうがないなと苦笑を浮かべながら、軽く肩をすくめた。 「みんな、早く早く!」 「すぐ行くわ」 坂を上りきった妹の声にせかされ、6人は坂を上るスピードを上げた。 坂を延々と上った先に、清姫神社はあった。急な階段の下には、清姫神社と彫られた石塔が立っている。 その階段を上って行くと、桜色の滝があまり広くない境内の中心にあった。柵で囲われた幹は、大人が5人がかりで腕を広げてようやく取り囲めそうなほどに太い。 そんな極太の幹とは対照的に、風に揺れる枝は糸のように細い。ちょっと力をこめれば簡単に折れてしまいそうな枝には、赤みの強い花弁が見事に咲き誇っていた。 幹に手を触れることはできないが、空を覆いつくさんばかりに広がった枝の下には立つことができる。 「すっごぉ〜い……!」 古木の圧倒的存在感に、少年少女はしばし我を忘れて見とれていた。強く風が吹けば、はらはらと花びらが舞う。花吹雪の情景に、鈴は嬉しそうにはしゃいだ。 「とってもキレイ」 「ああ」 美咲の感想に、隼人も頷く。すごいとか、キレイとかそういう月並みな感想しか出てこないところを情けなく思うのだが……清姫櫻の美しさは千の言葉を尽くしても語りきることができないような気がする。 「これは、見事ですね」 坂道をずーっと上ってきたので、謙治はちょっと息が上がっていた。とはいえ、清姫櫻の美しさは、ここまで上って来て良かったと思わせるくらい、見事であった。 「こんなに美しい桜があったなんて」 ほうと小さなため息が、麗華の口から漏れる。 誰もが言葉をなくして、枝垂れ桜の美しさに見ほれていると、 「いい加減にしてください! そんな話、聞いた覚えもありませんから、思い出しようもありません」 まだ若い女性の厳しい声が聞こえてきた。 「本当に!? 本当に何も伝わってないんですか!?」 「伝わっていません!」 何やら険悪な雰囲気である。思わず顔を見合わせるドリームナイツたち。拳火と水衣は声の出所を探して、すぐに動いていた。 男女がいたのは、神社の裏手に作られた階段の中ほどの位置であった。 「染中さん!?」 「え?」 麗華の声に、振り向いたのは二十歳過ぎの女性だった。シフォンのふんわりしたスカートにブラウスという格好は、いかにも育ちの良さを感じさせる。 いかにもお嬢様然とした格好の女性は、白百合のような清楚さを持ち合わせていた。彼女は大きく瞬きをすると、 「もしかして……神楽崎さん?」 「ええ。お久しぶりです」 麗華は、にこりと笑いかける。すると、彼女はあからさまにほっとした様子を見せた。麗華は彼女の後ろにいる男性へ目を向け、 「……そちらは?」 警戒心をあらわにしながら問いかける。 「今日はこれで失礼しますよ、八千代さん」 彼女が答えるより早く、男はさっと一礼して下りて来た階段をまた上って行く。 「河田さん、何度お見えになられても、同じです。あなたの質問には答えられません」 「康治でけっこうですよ、八千代さん。あなたはご存知なくても、お婆さまはご存知かもしれないでしょう?」 階段途中で立ち止まって、男は皮肉げに笑った。 「いけ好かねえやつ……」 拳火の意見に、麗華も心の中で賛同する。 一方、謙治と水衣は男が口にした“八千代”という名前に軽く目を見張っていた。 男が立ち去るのを待ってから、八千代と呼ばれた女性は、困り顔でため息をつく。心の底から困っているといった雰囲気である。 「何者なんですか? あの男」 「河田さんとおっしゃって、桜を専門に写真を撮ってらっしゃるそうなんだけど──カメラを持ち歩いているところなんて見たことがなくて……」 本当にカメラマンなのかしらと、八千代はもう一度ため息をついた。それを気持ちの切り替るキッカケにしたようで、 「ところで、どうしてここに?」 顔を上げた八千代は撫子のような可憐な笑みを浮かべて問いかけてきた。その答えに窮していると、鈴が 「お花見に来たんです、あたしたち」 すかさず謙治がその後を受け持ち、 「立派な木があると聞いて来てみたんですが……話以上ですね」 「本当に。見ているこっちが圧倒されそう」 水衣も賛同の声を上げる。聞くと見るとでは大違いだと拳火や隼人も言い、美咲は「すっごく綺麗ですよね」 改めて枝垂れ桜を見やり、ため息と共に答えた。 「そう言ってもらえると、花守の1人として、とても嬉しいわ」 「花守?」 麗華が首をかしげると、染中の家は代々この桜を守って来たのだと八千代は告げた。 「花を守るから、花守っていうわけですか。でも何故?」 謙治が疑問を口にすると、 「清姫は私のご先祖様にあたるのよ」 八千代は誇らしげな笑みを浮かべる。 「あの……お花見、一緒にやりませんか?」 リュックサックの中からレジャーシートを引っ張りだし、鈴は言う。5段重ねの弁当箱を見せ、 「お弁当、たくさんありますし──」 帽子で耳を隠しているので、今は見ることができないが、もしも見えていたら、きっと後ろに伏せられていたに違いない。鈴は目を少し潤ませ、ダメですか? と八千代に問いかける。これが子犬だったら、きゅぅ〜んと甘えた声で鳴いているところだろう。 「それじゃあ、お言葉に甘えさせてもらおうかしら」 くすっと笑みをこぼし、八千代は広げられたレジャーシートの上に腰を下ろした。 拳火や水衣、ドリームナイツたちも靴を脱ぎ、レジャーシートの上に上がりこむ。 弁当は、志狼のお手製だという。 「どうりで……」 おかずが和食だけになる訳だ。とはいえ、伝統的な花見弁当であるとも言えなくはない。 「あら、美味しい」 にんじんとインゲン豆の肉巻きを口に運んだ八千代の頬が緩む。 他にも海老を細かく刻んだのを大葉で巻いて挙げたのや、菜の花のおひたし、鶏肉の磯辺揚げ、出汁巻き卵やタケノコの煮物。おにぎりも梅やおかか、タラコ、鮭などさまざまなものが入っている。 しばしお花見弁当に舌鼓をうった後、お茶を飲みながら、八千代が清姫櫻の伝説を教えてくれた。 「この桜はね、清姫が姿を変えたものだって伝えられているの」 「え? 清姫なんですか? この木──」 彼女の言葉に、美咲が目をまん丸にする。本当に信じたような彼女の顔に八千代は、笑顔を縦に振った。 「清姫は、この辺りを治めていた豪族の娘だったの。彼女には許婚が居たのだけど、この彼が戦に行くことになったのね」 「それで、清姫はどうしたんですか?」 たとえば自分なら、どうするだろうか? 美咲は考え、多分一緒に行くだろうと考えた。ラストガーディアンに乗艦している他の女性たちもほぼ9割近くがそう答えるに違いない。 「何年でも待っているからって、彼に言ったそうよ」 「一緒に行くって言わなかったんですか?」 意外なことを聞いたと、鈴が目を見張る。すると八千代は「女は足手まといになるもの」と苦笑した。 「でもね、1年もしないうちに清姫は病気で亡くなってしまったの」 清姫が息を引き取ると、彼女を看取った家族や家臣の目の前で、彼女の手が伸びて枝になり、足は根に、身体は幹に変化したという。 「それが、この桜……」美咲のつぶやき 「そう伝えられているわ」 伝説だから、本当かどうかは分からないけれど、と八千代は悪戯っぽい笑みを浮かべる。 「ごちそうさま。とっても美味しかったわ」 もっとゆっくりしていきたいが、これからお花の教室の準備があるので、帰らなくてはならない。 「神楽崎さんも、良かったらまた習いに来てちょうだい」 「ええ、機会があればまたお邪魔させていただきます」 にこりと微笑む八千代に、麗華も微笑み返した。 「一体どういう知り合いなんだよ?」 「彼女のお婆さま、染中千代女先生にお花を習っていたことがあるのよ。彼女はそのお手伝いをしてるの」 階段を上っていく八千代の後ろ姿を見つめながら、麗華は拳火の問いに答えた。 「どうりで、八千代っていう名前に聞き覚えがあったはずね」 「やっぱり、ついて来て正解でしたね。橘さんが見た夢のキーワードがいくつか出てきましたから」 八千代、清、桜。後足りないのは、洋介という名前の人物だけだ。眼鏡の位置を直しながら、 「……図書館にでも行ってみますか?」謙治は言った。 「清姫櫻について調べるのね?」 あの河田という男は何か怪しい。八千代から、清姫櫻の何を聞き出そうというのか、知っておいたほうがいいような気がした。 「ええ。それもありますが……神楽崎さん、染中さんのお知り合いで、洋介という名前の人に心当たりは?」 洋介という名前の持ち主は、きっと八千代の近しいところにいるはずである。 「残念だけど、彼女とはそれほど親しいわけじゃないの」 ただし、八千代は花道家としても少しずつ世間に知られつつあるから、図書館で何か見つかるかも知れなかった。 「じゃあ、清姫櫻と彼女と別々に調べたほうが良さそうね」 お茶をすすりながら水衣がこれからの行動について、話を締めくくった。誰の口からも異存は出てこず、お弁当を平らげた一行は、図書館へと足を向けることにした。 「あった。これじゃないのか?」 図書館の一角に設けられた郷土史のコーナー。片っ端から本を引き出し、目次に目を通し、清姫櫻に関係していそうな項目を探していく。 最初にそれを見つけたのは、隼人だった。 「あったの? 隼人くん」 広げていた本を閉じて、美咲は少年の持つ本を覗き込む。隼人の向かいに座っていた麗華と謙治も身を乗り出してくるので、隼人は見やすいように、机の真ん中に本を置いた。 「これですね」 章のタイトルは、清姫櫻の伝説。そのものズバリだ。 4人は早速、本文を読み進めていく。 清姫は、この辺り一帯を治める豪族の娘だったという。たいそう琵琶が上手く、その音色に人はおろか、小鳥や動物、妖なども聞き惚れたという。清姫の琵琶の腕を伝える伝説はいくつか残されているが、その中の1つにこんなエピソードがある。 清姫が奏でる琵琶の音色が、1人の天狗を改心させたというのだ。この天狗は、清姫の側に仕えていたが、山の神から戻って来いと諭され、泣く泣く彼女の側を離れることになったという。 「その時、天狗は清姫に何でも願い事が叶う珠を渡したといわれている……ねえ。なんだか胡散臭い話だわ」 そんな都合の良いものがあってたまるもんですかと、麗華は口をへの字に曲げた。 「まあ……伝説ですからね」 そんな彼女に謙治は苦笑いを向ける。 ここまでは、清姫櫻伝説の序章のようなものだ。肝心なのはここからである。 八千代の言ったとおり、清姫の許婚はやがて戦へ出て行く。彼女は許婚を待つものの、病気で死んでしまう。 「死の間際、清姫は、天狗からもらった珠に、『桜になって、あの人の帰りを待っていたい』と願ったという……」 珠は清姫の願いをかなえ、彼女の身体を桜に変えた。 姫は突然桜に変わったわけではなく、物語でいう伏線のようなものがちゃんと用意されていたというわけだ。 「なるほどね……もしかして、あの河田って男は、この願い事が叶う珠を捜しているのかしら?」 あの男だけではない。この辺りで目撃されているトリニティと関係がありそうな不審人物も、この珠を探しているのだとしたら──? 「可能性はありますね」 答えながらも、謙治の表情は優れない。 何故、今なのかがはっきりしないからである。 水衣が言っていた、不可思議なエネルギー反応のこと。これの発生源は、願い事が叶う珠とやらではないかと思われるが──科学的に考えればばかばかしいことこの上ない推測だが──何の理由があってエネルギーを発したのかが分からない。 「……洋介さんと関係してるんじゃないのかな?」 謙治の疑問を聞いた美咲は首を傾げながら、言葉を続けた。 「夢の中じゃ、洋介さんは『この桜が咲く頃には帰って来る』って言ってたのに──」 「桜は満開。というか、もう散り始めていたわね」 咲き始めた頃にエネルギー反応があり、その後、不審者が目撃されるようになった。 「それが一番関係ありそうね」 「──となると、美咲さんが見た夢は、トリニティから染中さんを守って欲しいということでしょうか?」 トリニティを河田に入れ替えても問題ないように思われるけれども。 「洋介ってやつについては、どうするんだ?」 「そちらについては、お2人の調査次第でしょうね」 洋介という名前だけでは、高校生程度の調査能力とコネでどうにかできるものではない。せめて、名字が分かれば、別の調査方法もあるかも知れないが…… 「ジャンクさんに調べてもらうっていうのは?」 「あの人だって、タダで調べてくれるわけじゃないだろ」 美咲の提案に、隼人は苦虫を噛み潰したような顔を浮かべた。困り顔で唸っていると、拳火が得意げな笑みを浮かべてやってくる。 「見つかったぜ。たぶん、こいつだ」 そう言って少年が机の上に乗せたのは、街というテーマで、外国の風景を写したミニ写真集だった。 奥付を見ると、カメラマンは麻生洋介となっている。 「どうして、こいつだって分かったんだ?」 「その種はこっち」 拳火が継ぎにテーブルに載せたのは、フラワーアレンジメントの雑誌だった。表紙を見ると2年くらい前の号である。新進気鋭の花道家という特集が組まれ、その中の1人として八千代の姿もあった。 「この雑誌のどこで分かったの?」 美咲の質問に、拳火は編集スタッフからという、コメントページを示して見せる。そこに、特集ページの撮影を担当した者も何人かコメントを寄せているのだ。 その中に麻生洋介という名前もあった。コメントの内容を見ると、数人いる花道家の中で八千代のことを強調して語っている。 「で、俺としてはこっちにも注目してもらいたいね」 悪戯っぽく笑って拳火が指差したのは、同じカメラマンのコメント欄。そこに、杉山という名前があったのである。 「……もしかして、この杉山って……」 麗華の頭の中にぽんっと浮んだのは、広報部の撮影班に所属する1人の青年だった。 「今、水衣姉が確認してる。ハズレてたとしても、同じカメラマンだし、何か知ってるかもしれないしな」 「その彼女は今どこに?」 「艦と連絡取ってるとこってあんまりおおっぴらにできねえだろ? だから、女子トイレに行ってる」 謙治の問いに、拳火がちょっと言いにくそうに答えた。確かに、誰も聞いていないとはいえ、年頃の少年が女子トイレと口にするのは、少々躊躇らわれる。 「トイレの中じゃ、ヘンに思われない?」 美咲の質問に、拳火は 「鈴の符術の助けを借りてる」 「便利だな」 隼人の率直な感想に、拳火は「まあな」と苦笑い。 とりあえず今必要な本だけをここに残し、その他の本は本棚へ戻すことにした。机の上がすっきり片付いた頃、 「お待たせ」 水衣がやって来た。その後ろにくっついている鈴は、符を大事そうに懐にしまっていた。こういうものは、安易に捨てしまってはいけないのである。 水衣と鈴が席につくのを待ってから、謙治が口を開いた。 「──ということなんで、トリニティの狙いは、この何でも願い事が叶う珠ではないかと……」 「なるほどね。胡散臭いって気もするけどな」 けれど己の身の回りを振り返ってみれば、そんなこともあったって不思議じゃないと思わせる環境なのだ。 一般常識からみれば、ありえないことだらけの世界で生きているのだから、そういうこともあるかもしれないと、拳火たちは半信半疑でその考えを受け入れた。 「そっちの方はどうだったの? 杉山さんらしい人がいたそうだけど……」 麗華の問いに、水衣は、 「日ごろの行いがいいのか、それとも清姫のお導きか……大当たりだったわ」 思ったとおり、この雑誌にコメントを寄せていた杉山は、撮影班所属の彼と同一人物だったのである。BANに就職する直前に、頼まれた仕事なのだという。 「麻生って人のことについて聞いてみたんだけど、学生時代からのカメラ仲間なんですって。こちらの事情を話したら、染中さんと付き合ってるはずだって言ってたわ」 BANに就職した杉山と違って、麻生はフリーで仕事をしているという。今は撮影旅行中のはずだとも言っていた。出発したのは1年くらい前で、予定ではもうそろそろ戻って来るころらしいが…… 「僕もあまり人のことは言えないけど、撮影に没頭すると色々忘れてしまうんだよね」 通信の向こうで、杉山は決まり悪そうに言う。 水衣がこちらの事情を伝えると、「そりゃ大変だ」と大慌てし、何とか連絡を取って、すぐに帰るように伝えると彼は請け負ってくれた。 「よかったあ」 話を聞いた美咲はほっと胸を撫で下ろした。 「それと、河田康治っていうカメラマンにも心当たりがないか聞いてみたんだけど……。この人のことは知らなかったわ。桜専門に撮っているっていう話を伝えておいたから、こちらについても知り合いを当たってみてくれるそうよ」 河田の件については、杉山の連絡待ちということになる。 「ですが、多分何も分からないでしょうね」 ただの勘ではあるが、謙治はほぼ確信していた。 「ねえ、今からもう一度清姫神社まで行ってみない?」 美咲の提案に隼人は思案顔を浮かべ、 「……そうだな。今から行けば、神社につくのは夕方くらいか──」 「不審者の目撃情報が、一番多い時間帯になるわね」 ふふっと水衣が笑う。上手くすれば、不審者本人と出会えるかもしれない。 「ならいっちょ夜桜見物と洒落こむか」 好戦的な笑みで、拳火が言う。 一行が高台のふもとにたどり着くと、あたりは夕闇に包まれ始めていた。住宅街なだけあって、どこからか美味しそうな匂いがほわんと漂ってくる。 後1時間もすれば夕食時だ。 「ちょっと辛いかもな……」 小腹が空いたと、拳火がつぶやく。隼人と謙治も気持ちは同じなのか、無言で軽く肩をすくめている。 「とりあえず、目撃情報があった所を歩いてみましょうか」 「うん。桜は途中で見に行けばいいよね」 麗華の提案に美咲がうなずくと、鈴は早速リュックサックの中から地図を取り出してみせた。水衣はそれを受け取ると、早速見回りルートの検討に入る。 「今はここですから……」 それを横から覗き込んで、謙治もルートの吟味に加わった。その時、夕立を告げるような稲光が住宅街を覆う。 「うわ!?」 その光のまぶしさに、少年少女たちは、一瞬、目を閉じた。続けて雷様が太鼓を打ち鳴らすゴロゴロという音が聞こえてくるかと思ったのだが、雷鳴はやってこない。 夕焼け空には、綿雲がぽつぽつと見える程度だ。 「一体何だったんでしょうね?」 人差し指を口元にあて、鈴が不思議そうに首をかしげる。 「桜!」 思案顔を上げた美咲は弾丸のように走り出した。 「ちょっ……!? 美咲?!」 少女が駆けていく様を思わず見守ってしまった、6人だったが 「橘──!」 その後をすぐに隼人が駆け出し、それに続く形で残りの5人も走り出した。 「桜って……今の光は清姫櫻が……?」 「何でも願い事が叶う珠の持ち主ですからね。もしかしたらありえるかもしれません」 水衣のつぶやきに、早くも息が上がり始めている謙治が答える。それでも少年は周辺の観察を怠らなかった。 あんなにまぶしく光ったのに、周辺の住民は家の中に閉じこもって出て来ない。会社帰りのお父さんやOLの姿は見えず、塾へ行くような子供たちの姿もない。買い物帰りらしき主婦の姿や犬の散歩をしている人の姿も見かけなかった。 これは偶然なのか、それとも……。 急な坂道を全速力で駆け上がり、美咲は清姫神社にたどり着いた。最後に階段を上って桜の前まで来ると、 「八千代さん!?」 昼間出会った女性とお婆さんが折り重なるように倒れていた。 「……やはり勇者共の1人だったか」 忌々しげな舌打ちは、河田のもの。彼は清姫櫻を取り囲む柵を乗り越え、幹に直接手を触れている。 「キミは……」 さっと身構え、美咲は男を見据えた。 「美咲!」 「隼人くん! みんな!」 肩越しに仲間が追いついて来たのを確認し、少女は河田の存在を彼らに視線で伝える。 「お前は……」 「ちっ……ぞろぞろと鬱陶しい」 鼻の頭に皺を寄せ、河田は不機嫌さをあらわにした。 「染中さん?! 先生──ッ!」 彼女らが倒れているのは、高台に上がる階段の真下。位置的にみて、河田が2人を突き落としたとも考えられる。 「2人に何をしたの?!」 「清姫が持ってるお宝の力を拝見したくてね」 悪びれた様子もなく、河田はひょいと肩をすくめた。その顔に張り付いている品のない笑みに麗華は、柳眉を逆立てる。 「おお、おっかねえ。おっかねえから、こっちも仲間を呼ぶとしよう」 河田は上着に手を突っ込むと、どうやって持っていたというような、法螺貝を取り出し、それに口を当てる。 「おいおい……」 ツッコミレベルの低さが災いしてか、誰も彼の行動にツッコミができない! 冗談だろと拳火が冷や汗を浮かべるが、最近のボケはボケっぱなしなのである。 案の定、大河ドラマのワンシーンのような法螺貝の音が神社に響き渡った。それに応えるように、鬨の声があがる。 「何の騒ぎですか……?」 ひぃひぃ言いながら、ようやく神社にたどり着いた謙治が見たものは、関が原の合戦などで見られそうな雑兵であった。頭には陣笠。腰に刀、手には槍を携えている。 数は圧倒的に、敵側が有利。 神社周辺は、あっという間に敵の足軽に囲まれてしまった。 「おいおい……」 神龍拳を手に嵌めながら、拳火は目を周囲に向けた。 「どうするよ? 水衣姉」 「どうするもこうするも……やることは1つしかないわ」 「そりゃそうだ」 「鈴──!」 「分かってる!」 水衣に促され、鈴は持ってきていた符を敵に向かってばらまいた。 「倒れてる2人、頼むぜ!」 美咲と隼人に言い、拳火は河田に向かって走りだす。 鈴がばらまいた符は、炎と水の弾丸になり、雑兵たちの陣形を崩していく。 「隼人くん!」 「行くぞ! 田島!」 隼人のセリフ前半は、美咲に、後半は謙治に当てたものである。 「分かってますよ!」 この状況をどうにかする方法を考えろと、隼人は言いたいのだろう。いつもいつもこういう難しい役は、自分に回ってくるのだから、困ったものだ。 「謙治さんッ!」 符を縦長につなげ、鈴は水龍棍を作り出した。作戦担当の謙治が思考に集中できるよう、彼の護衛をかってでる。 「ありがとうございます」 鈴の気遣いを嬉しく思いながら、謙治自身も護衛のために銃をリアライズさせた。人型のモノに銃口を向けるのは、はっきり言っていい気分ではない。しかし、そうも言っていられない時だってあるのだ。 「神楽崎さん! カイザードラゴンを!!」 とにかく、数の不利を何とかしなくては。 「分かってるわ!」 美咲と隼人が、八千代とその祖母を運ぶため、彼女らの腕を肩に回した。雑兵が槍を構えて突進してくるが、 水衣の放つ水の弾が彼らを横から吹っ飛ばす。 その間に、麗華はカイザードラゴンを呼び出した。 〈麗華様!?〉 主の呼び出しに応じた火竜は、雑兵がワラワラと湧き出てくるこの状況に少しばかり目を見張る。1人1人はたいしたことないのだが、さすがにこうも湧いてこられると、少々厄介だ。 「この2人をお願い!」 自らも小銃をリアライズさせ、麗華は雑兵と応戦する。 「お願いね」 「頼む」 美咲は薙刀を、隼人は手甲をリアライズさせて雑兵の群れへ突っ込んで行った。隼人が物質化させた武器では、槍を構える敵を相手にするのは難しいが、刀を持つ者だっている。手甲で刀の軌道を逸らし、生身の部分に拳を叩き込めば、何とかあしらうことはできる。 〈心得てございます〉 彼らから女性2人を託され、カイザードラゴンは群がってくる雑兵たちを尾の一撃で吹き飛ばす。 「てめえ、何が目的だ?」 拳火が放った龍炎気弾をマトモにくらい、河田は桜を囲っていた柵も壊して後ろにぶっ飛ばされていた。 男を桜から引き離す目論見は見事、成功といえる。ちらっと横目に桜の幹を伺い、こちらには何の被害がないことを少年は確認した。 「目的……? 分かってるんじゃないのか?」 げほっと大きく咳き込んでから、河田はしっかりとした足取りで立ち上がる。指で唇の端を拭うと、このままじゃヤバイなとつぶやき、法螺貝を吹いた。 法螺貝から、黄金色の光が飛び出し、河田を包み込む。 「変身でもするつもりかよ?」 口調こそ茶化して聞こえるが、拳火の顔は笑っていない。 「変身と言やあ、変身かな」 黄金の光がおさまると、そこには甲冑に身を包んだ河田がいた。その姿は、戦国武将の一言につきる。面頬も装着しているので、河田の表情を読むことはできない。 「こっちもこれが仕事なんでね。お宝は頂戴していく」 「邪魔させてもらうぜ」 一筋縄ではいきそうにねえなと、拳火は気分を引き締めた。周囲の状況を鑑みると、何処からともなく現れる足軽たちに気を取られ、拳火の援護どころではなさそうである。……もっとも、ハナからそれを頼むつもりはなかったが。 希望としては、さっさとこの男を片付けて、水衣や美咲たちの手伝いに回りたいところだ。 腰の刀を抜いた河田は、できるもんならやって見やがれと、全身で語る。 〈数が多すぎますな……〉 背中に女性2人をかばいつつ、カイザードラゴンが苦々しげに言葉をこぼした。彼女たちの護衛を任された以上、攻撃に加わることは出来ない。 「あ、あなた方は……」 「味方……というのもちょっとおかしいような気がしますけど、安心してください、先生。お2人は必ず守ってみせます」 雑兵に銃口を向け、引き金を引きながら、麗華が老婦人に笑顔を向ける。 「麗華……ちゃん?」 「はい。お久しぶりです、先生」 まさかこんな形で再会するとは思いませんでしたけど。麗華はそう付け加え、悪戯っぽく笑ってみせた。 「ちょっと、キツイかも……」 ぜひ〜っと肩で息をして、鈴が水龍棍を下げる。 「こう…次から次へと湧いて来られては、こちらがもちませんね」 引き金を引く手を休めずに、謙治がつぶやく。先陣を切っている美咲たち3人の顔にも焦りの色が濃く表れている。 気になることといえばもう1つ。これだけ、騒いでいるにも関わらず、周辺が全く騒がしくならないことだ。 「警察に通報されてもおかしくないんですが……」 君子危うきに近寄らずという言葉もある。危なそうな事には近寄りたくないというのが、人間の心理だが、こうも静かだと何かあるんじゃないかと逆に疑いたくなってくる。 「清姫じゃないかしら」 少年の疑問に答えたのは、八千代の祖母だった。彼女は桜の古木を見上げると、 「河田さんに突き落とされた私たちを助けてくださったもの。清姫櫻はこの町の守り神でもあるし……」 町の人たちがここへ来ないように、してくれているのではないだろうか。 「私もそう思いますわ。おばあさま」 祖母の意見に、孫娘は大きく頷いた。 「……さっきのあの光かしら?」 「きっとそうですよ。──しかし、そうなると援軍を頼むのも難しいかも知れません」 ラストガーディアンへ連絡をいれる時間がない。仮にその時間が取れたとしても、援軍がここへ到着するまでの所要時間。それに、町の住民をシャットアウトしているのであれば、援軍も同じ目にあう可能性だってある。 「応援頼めないんですか? カイザードラゴンは来てくれたのに」 〈私は麗華様に召喚されましたので──〉 通常の方法で来たわけではないと、火竜は言外に接げた。 「うぅ〜ん……あ! そうだ!」 丸まっていた背中をぴんと伸ばし、鈴は水龍棍を消す。 〈鈴様?〉 一体何をするつもりなのかと、カイザードラゴンは幼い少女に目をやる。鈴は彼の陰に隠れるよう移動して、手首に巻いていたBウォッチのスイッチを入れた。 「お願い、届いてっ! 緊急、ヘルプ・コールッ!!」 直後、 「出張!」 「何でも!」 「「かん、てい、だぁ〜んっ!!」」 場違いとも言える、若い女と少年の声。 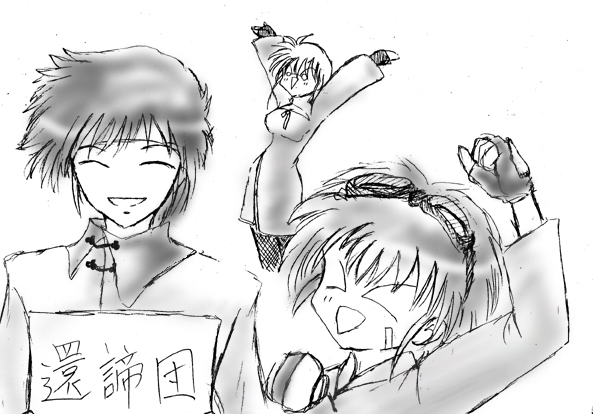 「トーコさんとユーキ、イサムさんまで!?」 ふわりと軽やかにやって来た3人に、麗華が目を見張る。セリフを言っていたのは、トーコとユーキだが、イサムは『還諦団』と書かれたボードを持っている。 帰(還)るのを諦めさせる団とは、恐ろしい。 〈イサム様、そのボードは……〉 そういうノリとは無縁ではなかったかと、カイザードラゴン。しかし、 「付き合いは大事ですから」青年はにこりと微笑む。 「んで、一体、何の騒ぎ?」 法螺貝の音に誘われるように、何処からともなく湧き出る足軽たちを円くした目で見つめ、トーコはカイザードラゴンに問いかける。 〈一働き、お願いいたします〉 「詳しい説明は後で。とりあえず、桜を傷つけないように注意しながら、敵を片付けてください」 謙治の指示に、トーコは「アイアイサー♪」気楽に応じる。 「はい、これ」 《クリエイション》と名づけられた精神物質化能力で作り出したハルバートを弟に手渡し、 「とりあえず、《エアーズ・ブリット》ぉっ!」 寄ってきた雑兵たちへ、風の弾丸をばら撒いた。 「下がって、休んでください!」 持参した偃月刀を構え、イサムは美咲たちのいるところへ走る。15キロ近い重量のある巨大な刀の一撃は、雑兵たちを数人、軽々と吹っ飛ばしていた。 「イサムさん?! どうやって?!」 思わぬ援軍の到着に、美咲は目を丸くする。 「鈴さんから、酒場にある通信機へダイレクトに呼び出しがかかりまして……トーコさんの《テレポート》でここへ」 少女の質問に、青年はいつものアルカイック・スマイルを浮かべたままさらりと答えた。 「そんなこと、できたの?」 ハルバートを垂直に振り下ろすユーキへ、水衣が質問を向ける。敵を縦に2枚おろしにしたユーキは、「やっぱり、手ごたえがないなあ」といぶかしげに眉をひそめ、 「鈴ちゃん、ジャンクさんのところでバイトしてたから。その関係で、直通の番号を教えたみたい」 ちょっと前まで艦内に出没していた、トリニティの怪人の片づけを鈴も手伝っていたのである。艦内に送られてくる怪人は、芸人と呼び変えても差し支えのないレベルの者ばかりだったが、万が一ということもある。 もしもの時はこれで連絡しろと、ジャンクに言われていたのだ。 「ユマさんに、外からでもボタン1つで連絡つくようにしてもらってたの、忘れてて……」 鈴は決まり悪そうに頭をかいた。 通信が出来たんだと軽く目を見張る一方で、このタイミングで援軍が来てくれたことは、ありがたかった。 「水衣姉! 悪ぃ」 横に並んだ姉に一瞥を向け、拳火は短い謝罪を口にする。水衣はそんな弟に「気にしないで」と一言。 何となく言外に責められているような気がして、拳火はぐっと言葉を詰まらせる。 「彼、強いわ」 弟の横に立ち、水衣はすっと身構えた。乱れかけていた息を整え、拳火の呼吸と合わせる。 「おいおい。2人がかりかよ?」 芝居がかった仕草で河田は肩をすくめた。冗談じゃないぜと抗議するが、表情から読み取れる彼の思考は、その反対。むしろ、やる気に火がついたようだ。 「かかって来いよ」 2人を挑発するように、河田は舌なめずりをする。刀を体の横──八相と呼ばれる形で構えた。 マイトを拳に集中させ、拳火と水衣が同時に走る。 2人の一挙手一投足が完全にシンクロしているのを見て、河田が目を見張る。 「回炎天!」炎が宿る右腕より繰り出される一撃と 「氷砕掌……!」 水のマイトが収縮された掌底が同時に繰り出される。 「くっ……!?」 全く同じタイミングでの攻撃に、河田は後ろへ飛びのいた。しかし、姉弟はそれすら見越していたように、2手目、3手目を打ち込んでくる。 「くそ……っ」 反撃に転じる隙を見出すことができず、河田は防戦に徹するしかなかった。 「……つまんなーい。厭きてきたあー」 不満オーラ全快で唇を尖らせ、トーコが言う。不平不満を口にしながらも、撃墜数は随時更新中。 「早いよ、姉ちゃん!」 ハルバートを振り回し、ユーキが姉を叱る。とはいえ、姉の言い分も分からないではなかった。 「手ごたえないし、匂いないし、血もないし、死体転がんないし、中身ないしっ?! 掃除の手間は省けて助かるけど、絶対変だよ、こいつらっ!」 「実体がないんでしょう。だから、温泉みたいにぽこぽこ湧いてくるんじゃないですかねえ」 よっ、と軽い掛け声と共に、イサムが偃月刀を振り下ろす。たとえが温泉なのは、実家のある町が有名な温泉郷だからだろうか。それはともかく── 「実体がない……?」 青年の考えに、謙治は目を見張った。敵を倒すこと、身を守ることだけを考えていたが、落ち着いて考えれば、ユーキの言うとおりである。 彼らが生物であるのなら、血(もしくは体液)が出るだろうし、強制的にあの世へ送られた者は、その抜け殻が残るはずだ。 ロボットであったとしても、そのボディは残骸として残るはずである。 「匂いって何のことかしら?」 訝しがる麗華に答えたのは、鈴だった。獣の耳や尻尾がほのめかしているように、少女は嗅覚も発達しているのである。 「生き物の匂いってことです」 体臭や、汗の匂いなどが雑兵たちにはないのだ。 〈──となると、やはりあの法螺貝が怪しいですな〉 鋭い爪で、雑兵の1人を3枚に下ろしたカイザードラゴン。視線を、河田の腰にぶら下がる法螺貝へ向けた。 貝は今も、ある程度の間をおいて、ぶお〜ぶお〜という独特の音色を奏でている。 そのたびに雑兵が増えるのだから、ほぼ間違いないといって良いだろう。 「でも、あれに手を出すのは難しいぞ」 額から零れ落ちる汗を乱暴に拭い、隼人が龍門姉弟の方へちらりと目を向けた。 炎と水のラッシュに、河田は防戦一方。しかし、身に着けた防具の性能が良いのか、本人が紙一重のところで避けているのか──おそらくはその両方……。 「あれじゃあ、もう一歩踏み出すこともできないよ!」 じれったげに眉根を寄せて、美咲は言う。 決定的な一撃を撃ちだす隙が、河田にはない。 第3者が加勢して、攻防の流れを変えるのも難しい。 彼らの攻防は、非常に危ういバランスの上に成り立っていた。このまま千日手にもなるのではとの予感も、少女の胸を掠めていく。 「だったらっ! これは、どうだっ?!」 水龍棍に変わって作り出していた赤龍刀を消し、鈴は懐に手を入れる。あまり使わない符なので、取り出すのに少々手間取ったが…… 「あった! 陽炎の符!」 少女がばら撒いた紙吹雪は、拳火と水衣の姿に変わる。 「何っ?!」 驚いたのは河田であった。 突然現れた分身に、ぎょっと目を見張る。 それは、彼にとって致命的といえる行動だった。 「水衣姉!」 「分かってる」 言葉少なに姉弟は、互いの思考を確認し合う。妹が作ってくれたこの隙は、最大限有効に使うべきだ。 「「超龍っっ!」」河田から一旦、距離を置く。「後ろの法螺貝! 忘れずに破壊してください!」 謙治の声が2人の耳に届いた。 鈴の作り出した人型が消える。 「「乱打ぁっっ!!」」河田が「しまった」とか言ったように思えたが、もう遅い。超龍乱打は、炎と水の高速連続攻撃を絶え間なく繰り出す技。1度喰らってしまったら、この炎と水の織り成す連鎖から抜け出すことなど、到底叶わない。スタッカートのきいた悲鳴が河田の口から漏れるが、拳火も水衣も頓着しなかった。 謙治に言われたとおり、腰に下げている法螺貝もきっちり破壊する。 「「演目、終了……!」」 炎と水の闘士が、演舞を終えたその場には、見るも無残な河田の姿があった。 チーン。哀悼の意をこめて、トーコが鐘を鳴らす。 「お仕事終了、だね」 ハルバートの石突を地面に打ちつけ、ユーキが言った。どこか嬉しげに見えるのは、早くも出張手当の計算を始めているかだろう。イサムは、 「お疲れ様でした」と軽く会釈をする。 会釈された方も、慌てて「お疲れさまでした」と頭を下げ返す。 「ねえ、こいつ、まだかろうじて息があるから、連れて帰るわよ?」 ぴくぴくと痙攣している河田を桜の小枝でつつきながら、トーコが言う。治療すれば、トリニティの情報源として使うことができるかもしれない。 「それもそうですね。ですが、対応は慎重に……」 と言ったところで、謙治はセリフを止めた。 艦内にいる規格外れの実力者たちの顔を思い出し、言うだけ無駄だと思い至ったのである。 「それでも、トリニティの人間を連れて行くことは、報告しておいたほうが良いんじゃないかな?」 「ジャンクさんには、もう言ってあるから、大丈夫。今頃手配してくれてるんじゃないかな」 小さく瞬きする美咲に、ユーキが首をわずかに傾けながら言う。心の中で、長兄を呼べば9割がた返答があるのだ。通信機など不要である。 「……そういえば、そうだったわね」 小さく息を吐いて、麗華が肩をすくめた。 「便利だな」 隼人はそう言うが、これは、ジャンクが並外れているからこそ出来る芸当だった。 「んじゃまあ、そういうことで」 トーコがひらひらと手を振るので、ユーキとイサムは慌てて彼女の身体に手を触れる。 還諦団、迅速なる撤収。 〈では、私もこれにて失礼させていただきます〉 ぺこりと一礼をするカイザードラゴン。麗華は彼を返還した。 「麗華ちゃん、みなさん……ありがとうございました」 ほうっと胸を撫で下ろしてから、老婦人は、少年たちに向かって深々と頭を下げた。八千代も彼女と同じように、深く頭を下げている。 「あ、いえ、そんな! こっちこそ……その……桜が大分散っちゃって……」 美咲の言うとおり、今の攻防の余波で、桜は半分くらいが散ってしまっていた。 「清姫櫻は、また来年も咲きますわ」 ねえと老婦人は、孫娘に同意を求める。八千代も「そうですわ」とうなずき、「皆さん、どうぞ我が家においでください」 八千代は笑みを浮かべて、少年たちを誘う。助けてもらったお礼に、夕食をご馳走させて欲しいと彼女は言う。 「私たちは……」 礼には及ばないと麗華は断ったのだが、2人は頑として譲らなかった。こうなってくると、断り続けるのも心苦しくなって来て……誰からともなく、 「それじゃあ、お言葉に甘えて……」 ということになってしまった。 結局、この日は夕飯どころか、1夜の宿まで借りることになってしまった7人であった。 数日後。清姫櫻の花は、すっかり散ってしまっていた。葉桜に変わり始めた桜を見上げ、八千代は小さなため息をつく。 「洋介さんの嘘つき……」 「八千代!」 彼女のつぶやきに答えるような若い男性の声。振り返ると、大荷物を背負った男性が、ぜいぜいと肩を上下させている。 「ごめん! 桜前線の情報はちゃんとチェックしてたんだけど──!」 息も絶え絶えに、彼は遅くなった理由を告げた。 桜前線は、ソメイヨシノの開花時期を示すものだ。その情報は全ての桜に当てはまるわけではない。 「清姫櫻は、早咲きなのよ」 目じりに浮ぶ涙を拭い、八千代は彼の元へ駆けた。 「おかえりなさい、洋介さん……!」 「ただいま」 自分の元へ駆けてきた彼女を、洋介はしっかりと抱きしめたのだった。 |
Back>>>