|
擬人化騒動真っ最中のラストガーディアン。戦力が低下しているからといって、トリニティは遠慮なんてしてくれない。むしろ、今がチャンスだというように普段よりも多いブロンが投入された。 勇者たちは苦戦を強いられることになったわけだが、そこはそれ。勇気とか友情とかそういったもので補って、これを撃退することに成功した。しかし、その直後から天候は悪化。現段階での高高度維持は、難しいとの判断から、ラストガーディアンは人里離れた場所に着陸し、天候の回復を待つことになったのである。 WINTER WORLD ラストガーディアンが地上に降りてから4日目の朝。 昨日までの吹雪がウソのように、外は晴天に恵まれていた。当然、外出許可もおりている。 それを聞いたウィルダネス組の最年少ラシュネスは、日課のラジオ体操を終わらせると、早速外に出ていた。 「うわあ〜、すごぉ〜い。真っ白ですぅ〜」 見渡す限り一面の銀世界。雲間から顔を覗かせた太陽の光に反射して、世界がきらきらと輝いて見える。 艦のすぐ側には大きな湖があるようだ。その上に人がいる。テントもあった。 「うに? なんでしょうねえ、あれ」 人はともかく、テントなんてなかったはずである。 「いってみましょ〜」 好奇心を刺激され、ラシュネスは氷の上に踏み出した。 湖にはった氷はかなり分厚いらしく、ラシュネスがジャンプしてみても、全く割れそうにない。 「すごいですねえ」 氷の厚さに感心しながら、こけないように慎重に歩いていく。 氷の上にはってあるテントは小さいものから大きいものまで、サイズは色々。明るい黄色や緑、青など、けっこう目立つカラーリングである。 「何でこんなところにテントが?」 首を傾げながら、テント群の中を歩いていると、その中の1つから人が出てきた。 「あ、イサムさん」 「おや、ラシュネスさん。おはようございます」 同じウィルダネスからやって来たイサムが、テントの中にいたことにラシュネスは驚く。それでも、律儀に「おはようございます」と頭を下げて、改めてここで何をしているのかたずねてみた。すると、 「ワカサギ釣りをしてます。トーコさんもいますよ」 手招きされて、テントの中に入ると、裾の長い半纏を着たトーコがイスに座って釣り糸を垂れているのに出くわした。 「あら、おはよ」 「おはようございます」 トーコは氷に穴をあけて、釣り糸を湖の中に垂らしている。 「お魚、釣れるんですか?」 氷の穴を覗き込むと、下には冷たそうな水がちゃぷちゃぷと揺れていた。 「釣れるわよぅ。そこのバケツん中覗いてごらん」 「どれどれ? わ〜たくさんいますねぇ」 トーコの後ろに置かれたバケツの中を覗き込むと、15センチほどの魚が30匹ほど泳いでいる。 「すごいですねぇ。こんなにたくさん。いつからお魚釣りしてるんですか?」 「夜明け前くらいかな」 「トーコがそんな早起きしたんですかッ!?」 長姉の返答に、ラシュネスは目を丸くした。となりで聞いていたイサムがぷっと吹きだす。 「早起きしたんじゃなくて、寝ないで起きてたんですよ」 外出の許可が出てすぐに、トーコとイサムは購買に走って、ワカサギ釣りに必要な物を調達してきたのである。それらの準備を進めているうちに、丁度いい時間になり、今に至るというわけだ。 「まあでも、そろそろ引き上げ時かしらね?」 垂らしていた釣り糸を引き上げながら、トーコはイサムを見上げる。熱いお茶を飲みながら、イサムは外の様子を伺い、 「そうですね」うなずいた。 「これだけ釣れれば、十分おかずになるでしょう」 「そうね。じゃあ、ラシュネス。悪いけどこれ、ユーキかジャンクに渡して、天ぷらにしてって言っといて」 トーコからバケツを受け取り、ラシュネスは素直にうなずいた。 「あたしらは、テント片付けてから帰るから。転ばないように気をつけんのよ」 「は〜い」 朝早くからトーコとイサムが釣ったのだからと、ラシュネスはここへ来たときよりも慎重な足運びで格納庫へ戻った。 「ただいまで〜す」 「おかえりなさい、ラシュネスさん。外はどうでした?」 居住スペースに戻ったラシュネスを出迎えたのは、ショールを羽織ったグレイスだ。 「真っ白でしたよ〜」 「そのままですわね。そのバケツ、中はワカサギですの?」 「あたりです〜。見てください、すごいんですよ。こんなにたくさんいるんです」 まるで自分が釣ったかのように、ラシュネスは誇らしげな顔でバケツの中身を見せた。グレイスはくすくすと笑いながら、中を覗き込み、「まあ、こんなに」と目を丸くした。 「おはよう、ラシュネス。外に行ってたんだって?」 「おはようございます、ユーキ」 シップの中から出てきた少年に、にっこり笑いかけたラシュネスは、早速バケツを彼に差し出す。トーコの伝言を伝えると、 「いないと思ったら、そんなことしてたの」 ユーキは軽く笑って肩をすくめた。 「OK。リクエストどおり、天ぷらにするよ」 ラシュネスからバケツを受け取ったユーキは、早速下ごしらえにとりかかった。ラシュネスとグレイスは、その隣で味噌汁の具材の準備に取り掛かる。 下ごしらえが終わった頃、トーコとイサムが帰ってきた。ジャンクとBDが起きてきたのは、朝食の準備がすっかり整ってからである。 朝食を食べ終えた少年少女達は、鉄砲玉のように外へ飛び出した。早速チームに分かれて雪合戦を始めたり、雪だるまを作り始める子供たちがいる。中には、真新しい雪の上に足跡をつけて回る子や、雪の上に倒れて自分の形をとる子供もいた。 「見てくださいジュン! 真っ白ですよ!!」 コートにマフラー、耳あてに手袋と防寒対策に余念がないのはアークセイバーチームのサヤである。白い息を吐きながら小さな子供のようにきゃっきゃっとはしゃいでいた。 「こんなに沢山の雪を見るのは初めて!」 彼女の隣に並んだ佐々山準も、大きな目をキラキラ輝かせて周囲の光景に見入っている。  「気持ちは分かるが、あんまりはしゃぎすぎるなよ」 サヤと準の保護者(?)剣和真が釘をさしたものの、 「ジュン! 何をして遊びましょう?!」 「雪だるま! 雪だるま作ろうよ、サヤお姉ちゃん!!」 2人は大はしゃぎで雪を丸めはじめた。 「聞いてねぇな、おい」 「ま、しょうがないんじゃない?」 使い捨てカメラのシャッターを切りながら、西宮麻紀が苦笑いを浮かべる。いつものことだ、という言葉は飲み込んでおく。 「カズマ! 見てないで手伝ってください!」 こいこいと手招きするサヤだが、彼女が作っている雪玉は、まだ手のひらに乗るくらいの大きさしかない。準の方を見れば、こちらもまだ手のひらサイズである。 「……しょうがねぇな」 どこをどう手伝ってよいのか、見当もつかなかったが、断ると後が怖い。軽く肩をすくめた和真は、麻紀に「お前はどうするんだ?」と聞いてみた。 「私は撮影班よ。他のコたちも写さなきゃ」 答える麻紀の表情は何故かアンニュイである。 「……なんかあったのか?」 「何にもないわよ、ええ、何にもね」 和真の問いに、麻紀は視線を逸らして答えた。 「それが何にもないやつの態度か」 おとーさんは心配そうにしているが、こればかりは正直に答えるつもりはない。こうしている今も、あの猛禽類のような視線が突き刺さるような気がしてならないのだ。 少女を無言で責める視線の持ち主、名を北都仁美という。 アナウンス部に所属している彼女は、艦内でも有名な年下好きである。仕事をうっちゃって雪と戯れる少年達を愛でていたいところだろうが、本日のシフトではそれが無理らしいのだ。 広報部撮影班から手伝いを頼まれた麻紀が、彼らと共にアナウンス部のブース前を通過した時、 「ちょっと待ったあっ!」 仁美の妙に迫力ある声に引きとめられた。全員で振り向けば、妙に血走った目をしている仁美が仁王立ちで立っていた。 全員が今すぐこの場から回れ右をして立ち去りたい衝動に襲われる。しかし、同時に今のあれに逆らっては命が危ないとも思われた。 「北都さん、何か?」 恐る恐る問いかければ、 「キミたち」 有無を言わせぬ迫力ある声とは裏腹に、仁美はにっこりと可愛らしい笑顔を見せる。ただし、目は血走ったままでちっとも笑っていない。 「キミたちなら、私の言いたいことが分かるわよね」 確信に満ちた口調で彼女はきっぱり言い切った。 「え〜っと……はい、なんとなく」 仁美と視線を合わせないようにしながら、班長が代表して答えた。その全身からは、関わりあいたくないなあというオーラが出ている。麻紀も気持ちは同じだった。 「なんとなく?」 その時、少女は確かにしゃ〜っという、蛇の鳴き声のような威嚇音を聞いた。とたん、撮影班全員がびしぃっと背筋をただし、 「分かります! 大丈夫です!!」 その場から猛ダッシュで逃げた。 「期待してるわよ〜」 背中から、仁美の上機嫌な声が聞こえてくる。これは責任重大といえよう。 ほんの20分ほど前の出来事に思いをはせた麻紀の顔は、もう怖いものは何もない、って感じだった。 「……なあ、本当に何にもなかったのか?」 「ないってば。大丈夫よ」 まるで自分に言い聞かせるような口調で答えた麻紀は、それじゃあねと、他の子供たちのところへ向かっていく。 「あれは、ロードチーム……とフェリスヴァインチームね」 フェリスヴァインチームはともかくとして、ロードチームの6人は、半纏にワラ沓という雪ん子のような格好をしていた。 「何やってるの?」 ベニヤ板を囲った中に雪を投げ入れているのを見て、麻紀が彼らに声をかける。 「雪像を作るんだよ。雪を固めてブロックにして、それを削っていくんだ」答えたのは、道産子・北山雷人。 「へえ、雪像ってそうやって作るの」 麻紀が感心すると、棒などにじかに雪をつけていく方式は難しいので、簡単なブロック式でチャレンジするとの答えが返ってきた。 「そうなんだ。あ、写真、撮らせてもらっていいかな?」 無断で撮影するわけにはいかないので、許可を求めると全員快く承諾してくれた。麻紀は早速カメラを構え、シャッターを切った。 もくもくと雪を運んで来るショベルたん。ダイバーたんは、小さく丸めた雪玉を、運動会の玉入れの要領でベニヤ板の中へ放り込んでいた。 ベニヤの中の半分くらいは、すでに雪で埋まっているようだ。「よいしょ、よいしょ」と声を出して、雪を固めているのは、星崎瞬と草薙沙耶香の2人である。時々、ダイバーたんが投げた雪玉に当たってしまうようだが、2人ともあまり気にしていないようだ。 ドリルたんはいつ用意したのか、紙粘土でこれから作る雪像のミニチュアを持ち出していた。それを見ながら、ファイヤーたんと雷人が、羽丘リリィを通訳に、あれこれと今後の予定について話し合っているようである。 残る2人、アタッカーたんとレスキューたんであるが……どうやら、アタッカーたんは雪像作りよりも、雪そのものに興味があるらしい。足元の雪をかき集めては、わ〜いといった感じで放り投げている。それをレスキューたんが、必死で止めようとしているようだが──今のところうまくいっていないようだ。 「がんばってね」 またしばらくしたら、撮影に来るわねと言い残して、麻紀は次の被写体を求めて歩き始めた。 湖の側では、勇者忍軍が陣取っている。大人ほどの大きさもある氷の柱を前にして、風雅陽平と風魔柊の2人が、ふふふと不気味な笑みを浮かべ合っていた。 「……何してるのかしら?」 好奇心の赴くまま、彼らに近づいていくと── 「アニキには負けないかンね!」 「へっ! 俺を甘くみるんじゃねえ」 どちらも自信満々といった雰囲気でばちばちと火花を飛ばしている。桔梗光海と風魔楓は、そんな彼らをため息交じりに見物していた。翡翠だけは、ぱちぱちと拍手をしながら、期待のこもった眼差しを2人に向けている。 「これから、何が始まるわけ?」 麻紀が光海に尋ねると、何がどうなってこういうことになったのか分からないものの、どっちが上手く氷像を彫れるか、競争することになったのだそうだ。 「もう……すぐに熱くなるんだから……」 「男の人ってどうしてこう……」 愚痴をこぼす2人の少女は、呆れと諦めを同じ量だけ混ぜ合わせて、顔に広げたような感じである。 彼女たちの肩を、麻紀はぽんぽんと叩いた。それは励ましにも受け取れたし、諦めなさいと言っているようにも受け取れそうな、微妙な強さ加減であった。 娘さんたちがそんなやり取りをしているうちに、男2人は、クナイを使って、ずがががっ! と氷柱を削りにかかっていた。 およそ30分後。 「どうだい、アニキ!!」 柊は、鮭をくわえた立派なクマを彫り上げていた。アイヌの伝統工芸を思わせるそれは、立派な芸術作品と言っても良かった。 早速麻紀は、カメラのファインダーを向けた。製作者である柊は、得意満面の笑みとVサインでそれに応える。 「……ヨーヘー。これは……クマ?」 「何だと?! どっからどう見ても、立派なクマじゃねえか!」 ここが顔で、ここが足だろと、陽平は光海に説明する。 「……クマに見えなくはないですけど…………」 学校の授業レベルくらいだと、楓は評価した。ちなみに授業名は、美術ではなく図工である。 「ようへい、かわいい」 それでも、翡翠は陽平が彫ったクマが気に入ったらしい。麻紀の袖をくいくいっと引っ張って、一緒に写してほしいとおねだりをする。 「いいわよ。ほら、陽平君も並んだ、並んだ」 光海と楓の評価にヘコんでいた陽平だったが、翡翠が気に入ってくれたので気を取り直したようだ。お姫さまと並んだ彼の笑顔は、満足感一杯であった。 結局、2人の勝負はうやむやになり、 「せっかくだから、集合写真も1枚!」 麻紀のリクエストに応えて、2体のクマをバックに5人が並び、冬の思い出を飾る写真がまた一枚増やされたのだった。 さて、氷像コンテストが催された会場から湖の上へ進めば、高校生メンバーが中心になって、スケートをしていた。 分厚い氷がはった湖の上は、スケートリンクの代わりにちょうどいいらしい。 ほとんどのメンバーが器用に滑っている中で、ブレイブナイツは、メンバーの半分が苦戦しているようだった。 「くっ……ぬぬぬぬ……」 氷の上に踏ん張った両足を細かに震わせながら、御剣志狼は眉を逆のハ字に、口をへの字に結んでいる。 「シロー、変な顔! っていうか、そんなに力まなくても大丈夫だよ」 くすくすと笑うのは、彼の幼馴染であるエリィだった。 「そ、んなこと、言っても、よ……」 妙に足元が安定しないのである。力を入れていないと、今にもすっ転びそうだ。 「お前、そんなんじゃ、足の筋肉が辛いぞ」 呆れ顔の龍門拳火はこの寒空の下、タンクトップ1枚という季節感を無視した格好をしている。 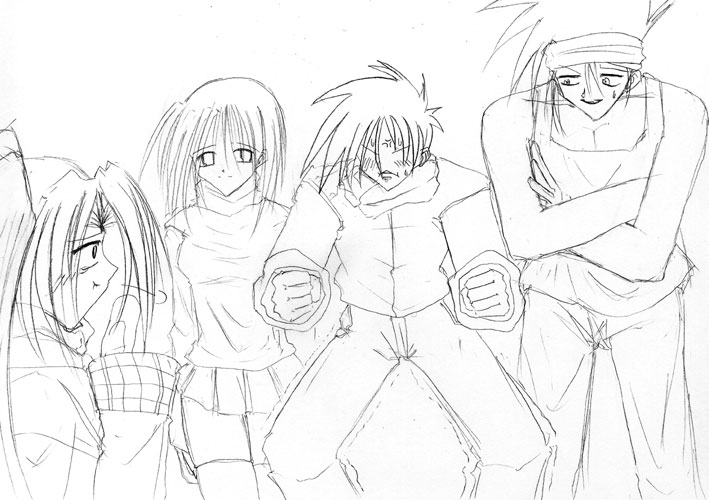 「立ち方も違うわ。踵をくっつけて、つま先を90度くらいに開くの」 「お、おう」 水衣のアドバイスを受けて、志狼は立ち方を変更しようとした。とたん、派手にすって〜んと後ろに転倒。後頭部を強打した。 「ってぇ……!」 「だっ、大丈夫!? シロー」 心配そうに近づく幼馴染に、志狼は大丈夫だと答え、立ち上がり……またこける。 「こりゃあ、時間がかかりそうだな」 「あっちも、だけどね」 肩をすくめる弟に、水衣は別のペアを指差した。 1つは、獣虎陸丸と鈴のペア。もう1つは、ブリットとユマのペアである。 「ほら、思い切ってどーんと行きなさいってば!」 「うわ!? ちょ、押すなよ、鈴!? うわぁっ?!」 獣耳獣尻尾の少女に背中を押され、陸丸は大いにうろたえた後、志狼にも負けぬこけっぷりを披露した。 「ったー! 何も押すことないだろ!?」 したたかに打ち付けた腰をさすりながら、陸丸は後ろの少女に抗議する。少女はぷいっとそっぽを向き、 「あんたがトロいから悪いのよ」 ふんっと鼻を鳴らす。 「何をー!」 鈴に向かって突っかかっていこうとした陸丸だったが、バランスが上手く取れずに転倒。ほら、やっぱりと少女に笑われるハメになってしまった。 笑っちゃダメだろうと、鈴をたしなめるのは、紅麗。ヴォルネスは陸丸を起こすのに手を貸している。 実は、ブレイブナイツのパートナーたちも、侍チームを除いてスケートに参加しているのだ。残る蒼月は羨ましそうな視線を、残るもう1組のペアに向けていた。 志狼や陸丸と同じく上手く滑ることができずにいるユマは、ブリットに手を引いてもらいながら、慎重に歩を進めていた。 ブリットもスケート初心者だったのだが、拳火や水衣、他の少年少女が滑っているのを見てスグにコツをつかんでしまったらしい。 ほんの1時間ほどの練習で、後ろ向きに滑ることもできるようになっていた。 「はっ放さないでくださいね」 ぐらぐらと身体を揺らしながら、ユマがブリットに訴える。2人は今、しっかりと手を繋ぎ合っているわけだが……ユマはそれどころじゃなかった。 「分かっている」 少女の練習に付き合うようになってから、このやり取りをするのは何度目だろう。ブリットはパートナーに気づかれないよう注意をしながら、こっそりとため息をつく。 ちなみに、スケート不参加の侍チームは何をしているのかというと…… 「かあ〜っ。旨ぇっ」 展望廊下にゴザを敷き、雪見と称して熱燗をくいっと引っ掛けていた。雪景色だけではなく、パートナーたちの姿も見えているので、申し分ないロケーションである。 「暖かい部屋ん中で旨い酒を引っ掛けるなんざ、最高だね!」 「同感です。今日が休みで本当に良かった」 鋼牙の独り言に答えたのは、土熊でも石鷹でもない。郵便戦隊最強(?)の鉄面皮・青木神無である。 「な!? いつの間に?!」 彼女は、3人に気配すら感じさせなかったというのに、正座して、手酌できゅっとお猪口を傾けていたのだ。 「あぁ、ご心配なく。自分の分は持参しております」 驚く石鷹に、神無はすぐ側に置いてあるチロリを指差す。チロリというのは急須に似た、金属製の酒器である。最近は徳利に変わられて全くといっていいほど見なくなった代物だ。 「いや、酒のことを言ってるんじゃなくてよ……」 顔の前でぱたぱたと手を振って、土熊は彼女の言を否定する。神無はすまし顔でお猪口を口に運び、 「ああ、大丈夫。仕事をサボっている訳ではありませんので」 今日は休みですと、付け加える。 「いやだから、そうじゃなくてよ……」 神出鬼没の噂は本当だったのかと思いつつ、何と聞けばよいものかと鋼牙は首を捻った、その時だ。小さいものが動く気配を感じ、何気なくそちらへ顔を向ける。と、 「待て、小動物!!」 鋼牙の視界の端を投げ縄の輪がかすめ飛んでいく。 「うにゃぁ!? かんっ、神無ちゃん!?」 神無が投げたのだろう投げ縄の輪は、郵便戦隊の 「なっ、何で、ここにっ!?」 「私を嘗めるなよ、小動物」 ぐいぐいと縄を手繰り寄せ、神無はふふふと凄んで見せた。その恐ろしさと言ったら、百戦錬磨の侍チームでさえ、思わず土下座をしたくなるほどである。 「いや〜ん。ごめんして〜」 「ゴメンで済めば、裁判なんていらんだろう?」 何とか逃げようとあがく皐月だったが、神無から逃れることは2階から目薬をさすよりも難しい。 「バカは死ななきゃ治らないと言う言葉は知っているか?」 「神無ちゃん、怖いぃ〜」 ひぃっと恐怖に顔を引きつらせる皐月。それを目撃した侍チームは、夢に見そうだと思った。 「今度こそ地獄まで送ってやろうな。小動物」 あまり表情を変えることのない神無が、にっこりと微笑んだ。少女は、神無にずるずると引きずられながら、郵便部へと連行されていくのでありました。 「達者でな〜」 鋼牙が手を振って見送る後ろで、石鷹は「成仏してくださいね」と手を合わせ、土熊は鈴のかわりか、お猪口の縁をチンと弾いた。 「たっ助けてよぉ〜っ!?」 自分たちも命は惜しい。サボるお前さんが悪いんだろうと、3人は我関せずを決め込むのであった。 さて、湖の上である。スケートをしている若人たちの後ろでは、ワカサギ釣りに興じている集団がいた。年齢層は高く、釣り糸を垂らしている大半が男性である。彼らの側にあるバケツの中を覗き込むと、朝と違って成果ははかばかしくないようだった。それでも、誰一人気にした様子もなく、釣り糸を氷の下に垂らしている。 アナウンス部唯一の男性職員にしてチーフを勤める森本康之も、そんな釣り人の1人だった。 「いい天気ですねえ」 『ソウデスネー』 チーフの隣で釣り糸を垂らしているのは、すっかりおなじみとなってしまったカズマ君1号である。ツッコミ以外のセリフを口にしているところを見ると、また進化したらしい。 「若い人たちは元気でいいですねえ」 『ソウデスネー』 まるでお昼の某生放送番組の1コマのようである。 「お?」 チーフの竿がぴくぴくと上下に動きはじめた。 「大物みたいですよ」 『ソウデスネー』 どんなときでも、カズマ君の語調は変わらない。 慎重に糸を手繰り寄せ……水から上がったのは……下駄。  『ナンデヤネン!』びしっ。 真冬の厳しい寒さの中では、カズマ君1号のツッコミもやや鈍るらしい。 「……なんだか、漫画のようですねえ」 チーフは変わらず、のほほんとしているのであった。 「さあ〜って、晩飯に向けて一働きしねえとなあ」 うぅ〜んと大きく伸びをするのは、ウィルダネス組の1人、BDである。もこもこしたミリタリー風のジャンパーを着て、口には火のついた細いシガーをくわえていた。 「は〜い! って、何をするんでしたっけ?」 毛糸の帽子にマフラー、もこもこジャンパー、手袋、長靴と防寒対策バッチリのラシュネスが、右手を上げて、首をかしげた。彼の頭の上では、クエスチョンマークがサンバを踊っている。 「イグルーを作るんだよ」 ラシュネスの横にいたユーキが、目を細めて笑う。 イグルーとは、氷のブロックを積み上げて作るカマクラのようなもののことだ。今回、氷は手近なところにあるものの、アイススケートをしていたり、ワカサギを釣っていたりするので、雪を固めて作ることにする。 「っつーわけだから、お前は雪を固めろ」 「は〜い。分かりました〜!」 BDの指示を受けて、ラシュネスは早速雪を固めにかかった。と言っても、雪の上で飛び跳ねるだけである。それにユーキも加わって、2人でぴょんこぴょんこ跳ねた。 「俺らのところで6人……その倍くらい入れるくらいのがいいかねえ」 片足を引きずるようにして歩きながら、BDは雪の上に円を描いていく。この円にそって、雪のブロックを並べていくのだ。BDが大きな円を描いたとき、仮眠を取っていたイサムがグレイスを連れてやって来た。 「どんな具合です?」 「どんなも何も、まだ始めたばっかりだ」 イグルー作りに着手する前に、ラシュネスが雪合戦に参加したり、雪だるまを作ったりして遊んでいたからである。 「そうでしたか」 なるほどとうなずくイサムの顔には、「やっぱり」という文字が見て取れた。グレイスも同じ思いらしく、「ラシュネスさんらしいですわねえ」と苦笑いを浮かべている。 「──俺たちも手伝おうか」 担いで来たのこぎりを持って、イサムはラシュネスとユーキが飛び跳ねているところへ向かう。グレイスも持って来た大型スコップを手にパートナーの後ろを付いていくが、 「力仕事は男に任しときな」 言外にスコップを渡しなと、BDが言う。一瞬目を見張ったグレイスだったが、女性扱いしてもらえるのは嬉しいことである。 「では、よろしくお願いいたしますわ」 笑顔と共に、グレイスはスコップを差し出した。 年少2人が飛び跳ねた箇所に、イサムがさいの目にのこぎりをいれていく。 「よっこらしょ」 それを横からBDが掬い上げ、1つずつ取り出していった。このまま積み上げるにはちょっと大きいので、さらにのこぎりを入れて、積みやすい大きさに整える。 「何やってるんですかあっ!?」 湖の氷の上から大きな声をはり上げるのは、好奇心一杯のお転婆娘鈴であった。少女の尻尾が左右に大きく揺れている。 「いぐるーっていうのを作ってます〜!」 飛び跳ねるのを中断してラシュネスが答えると、少女は聞きなれない単語に首をかしげた。 「氷のブロックを積み重ねて作る家のことですわ」 今回は雪のブロックで作るのですけれどねと、微笑みながらグレイスが説明する。さらにユーキが 「夜はこの中でお鍋をするんだってさ」 「氷の家!? お鍋!?」 とたん、鈴の目はきらきらと輝きだした。 「あ、あの! あたしも混ぜてもらっていいですか!?」 「えぇ、どうぞ」 「今なら大歓迎だ」 イサムとBDが、笑って答える。 「じゃ、すぐに靴を履き替えて来ますねー!」 鈴は大急ぎで、反対側の岸に向かった。 「とはいえ、全員連れて来られると……これじゃあ、小せえなあ」 先ほど足で簡単に描いた円を振り返り、BDは苦笑いを浮かべる。同じように円を振り返ったイサムは、 「その時は、もう1つ作ればいいんじゃないですか? 人手が増えれば作るのも楽ですよ」 と、前向きな発言。それもそうかと、BDは肩をすくめた。 「ラシュネスさ〜ん!」 「あら、サヤさんですわね」 満面の笑顔と共に、ぱたぱたとサヤがやって来る。その後ろには準と和真もいた。 「見てください、これ。かわいいでしょう?」 サヤが差し出したのは雪ウサギとミニサイズの雪だるまである。 「うわぁ、かわいいですねえ。あれからまた作ったんですか?」 「はい。たくさん作りました! ね、ジュン」 「そう……だね」 にこにこと嬉しさ全開で笑うサヤと違い、準の表情はかなり疲れていた。どうなさったんですの? とグレイスが和真に聞けば、 「作りすぎだ、あれは」 彼はがっくりと肩を落とす。雪だるまの群れができたと、和真はうんざり顔で答えた。 「うわあ……」 その様子を想像しただけで、どっと疲労感に襲われる。お疲れ様と、ユーキは思わず和真と準の肩を叩くのであった。 「ところで、ラシュネスさんは何をなさってますか?」 「いぐるーっていうのを作ってます」 以下、鈴の時と同じやり取り。こちらも、目に星を輝かせて「私も参加させていただけないでしょうか!?」 拳をグーにして、ずずいっとラシュネスに詰め寄った。 「え……えっとぉ……」 迫力に圧倒されて、ラシュネスが視線を泳がせていると、 「おう、人手があるとこっちも助からあ。いっちょ頼むぜ」 横からBDが助け舟を出した。 「はい! がんばりましょう、ジュン!」 「うんっ」 サヤと準は、早くもやる気満々のようである。 「それじゃあ、このブロックをその円にそって並べていってもらえますか?」 「は〜い」 イサムの指示に従って、2人は雪のブロックを運び始めた。 「お前さんは、こっちな」 「……おう」 ノコギリを手渡され、和真は自分の役目を理解する。イサムが切り、BDが掬い上げたブロックを、和真が運びやすい大きさに整えていく。 それを、サヤと準、ラシュネスが運び、円に添って並べていく。ユーキとグレイスは雪の上で跳ねてブロックとなる雪を固めていく作業を続ける。 「すいません、遅くなりましたっ!」 息を弾ませてやってきたのは、陸丸をつれた鈴だった。 「あれ、鈴ちゃんと陸丸だけ? てっきり、志狼たちも来ると思ってたのに──」 飛び跳ねるのをやめてユーキが軽く眉を持ち上げる。 「志狼兄ちゃんたち、スケートに夢中みたいで……」 一応声をかけてみたのだが、聞こえていないようだったので、そのままこっちに来たのだ。 「そうなんだ。志狼も負けず嫌いっていうか、1度始めるとけっこうこっちゃうよね」 「あ、そうかも」 ユーキの評価に、陸丸は苦笑を浮かべる。 「えと、このブロックをそっちに運べばいいんですか?」 「そうですよ。この円に沿って並べていくんだそうです」 すでに積んである雪のブロックの上に新しいブロックを乗せたサヤが、完成が楽しみですよねと、拳をぐぐぅっと握り締めた。 「よぉっし! あんたもしっかり働きなさいよね!」 腕まくりをした鈴は、横にいる陸丸にしっかり釘をさしてから、運びやすい大きさに揃えられたブロックの置かれているところへ向かう。 「分かってるよ! 偉そうにっ!」 むすっと頬を膨らませ、陸丸も少女の後に続く。 「そっちの小さめのやつな」 「はーい」 和真が大きさを調整したブロックを手に、2人はラシュネスたちにまじって作業を開始した。 ブロックのある場所から、イグルー建設予定地までの距離はそれほどあるわけではないのだが、何度となく往復していると身体はぽかぽかしてくるし、汗もかく。 「ふぅ。けっこうタイヘン……」 「そう……ですね」 額に浮ぶ汗を拭き拭き、準がつぶやく。サヤの顔にも玉のような汗が浮んでいた。鈴も陸丸も、頬をうっすらと上気させている。そこへ、 「よう。進み具合はどうだ?」 タバコをふかしながら、足取りも軽くジャンクがやってきた。手には、オタマの柄がはみ出た鍋を持っている。 「半分ってところでしょうね」 ブロックの切り出し作業を中断して、イサムが答えた。 彼が見ているものをジャンクのサファイアの目も見つめる。 「ずいぶん、でかいのを作るんだな」 「この参加人数見ろよ」 ちょうどいいくらいじゃねえかと、BDが胸をはった。 積み上げられたブロックの高さは、準のお腹くらい。完成までには、まだ時間がかかりそうである。 「いい感じじゃないの」 「あ、トーコ!」 「がんばってるわね〜。そろそろ休憩したら?」 兄が鍋を持っているので、妹はお椀と箸、それからアウトドア用のコンロを持っていた。 「善哉だ。食えるだろ?」 いそいそと妹がセットしたコンロの上に持参した鍋を置き、ジャンクが問いかける。食べられないという人はおらず、しばし、善哉が温まるのを待つ。 「あつッ……でも、おいしー」 温まった善哉の中には焼いたお餅が入っていた。お椀を通して伝わってくるぬくもりにほっこりしながら、準は気をつけながら、箸を進めていく。 「美味しー。やっぱり、外で食べると違うわね」 「あちち」 お餅の熱さと格闘しながら、陸丸も美味しそうに善哉をほおばる。サヤは伸びるお餅にちょっとびっくりしたようだ。 「ラシュネスさん、伸びますよ、これ!?」 「そうなんですよ〜。お餅は伸びるんですよ〜。あ、そうだ。今度はサヤさんも一緒にお餅つきしましょう! すっごく楽しかったんですよー」 「お餅つきですか!?」 餅をほおばり、どこまで伸びるか限界に挑戦しながら、サヤが目を丸くする。準と鈴、陸丸の子供3人組は、それも面白そうと目で訴えていた。 「イベント増やしてんじゃねえよ」 とはいえ、根っこがお人よしであるため、今のツッコミにキレはなかった。そのことを自覚しながら、 「そんなことしてたんすか?」 側にいるイサムに聞いた。 「郵便戦隊の皐月さんから、お餅は美味しいと聞かされたらしくて……」 「だったら、買うんじゃなくて、1からやった方が面白いとトーコさんが言い出したんですの……」 どこか面白がっている雰囲気のイサムと違って、グレイスの方は心の底から疲れたようなため息をもらした。 「やっぱりか」 「──何よ、そのお前が全部悪いみたいな目は……」 善哉の入ったお椀を口につけながら、トーコがジト目を和真に向ける。青年は、 「何でもねえよ」と答え、ワザとらしくそっぽを向いた。 「あ、何その態度。ちょっと傷つくわよ、それ」 むっと頬を膨らせるトーコの後ろで、 「今更ちょっとくらい傷ついたところで……なあ?」 「分かんねえだろうなあ」 ジャンクとBDが、こっそりとつぶやく。 「こらあ!」 ちゃぶ台をひっくり返すような仕草で、怒りを表現するトーコだが、もちろん誰もフォローはしなかった。 「おかわり、おかわりっと……あれ、麻紀ちゃん」 2杯目をお椀に入れようとしていたユーキは、誰かを探しているような感じで歩いている麻紀を見つけた。どうかしたのと声をかければ、 「あー! みんな、こんなところにいた!!」 どうやら和真たちを探していたらしい。 「ちょっと、みんなで何を食べてるのよ?」 「善哉ですよ、マキ。見てください、お餅がこんなに伸びるんですよ!」 「餅が伸びるのは分かったから。っつか、アタリマエだから」 ほらほらと、餅を引っ張ってみせるサヤにツッコミをいれ、和真は麻紀の分があるかどうかを、ジャンクに問い合わせる。 「まだまだあるぞ」 「お椀もお箸もあるわよ。大丈夫」 トーコが差し出したお椀にユーキが善哉をよそう。 「はい、どうぞ」 「ありがとう」 差し出されたお椀を受け取り、麻紀は笑顔を浮かべた。写真撮影のためにあっちこっち走り回っていたので、ちょっとくたびれているのである。 「……暖かいし、甘いし美味しいわ〜」 疲れたときには甘いものよねと、麻紀は幸せ顔で善哉をすすった。それでも、持ち前の好奇心はちっとも損なわれることがないようで、 「ところで、準君。みんなで何作ってるの?」 「えっと、氷の家だよ。イグルーって言うんだって」 「へえ……そうなんだ」 餅を飲み込んで、麻紀はうなずく。だったら、その製作過程も写真におさめなくてはならないだろう。 「和真君たち探してなかったら、危うく見逃すところだったわね」 ヘルプとはいえ、それでは撮影班の沽券にかかわる。さいわい、カメラのフィルムにはまだまだ余裕があった。 「……ところで机はどうするんだ?」 タバコの煙を口から吐いて、ジャンクが首を傾げる。 「あ! ……そいつぁ考えてなかったなあ……」 ぺしっと額を叩いてBDは、イグルーの建設現場へ目を向けた。壁はまだそれほど高くないので、今ならまだどうとにでもなる。 「はい! だったら、机も雪で作りたいです!」 尻尾を元気に揺らしながら、鈴が挙手をして発言する。 テーブルの回りに、足を入れられるくらいの溝を掘る。余分な雪はテーブルの上に乗せて高くすればいいと、少女は言った。 「そうですね。1度それでやってみますか」 「高さがたりなければ、回りから雪を集めて乗せてもいいですし」 そういうことになった。 「というわけだから、姉ちゃん、スコップ」 差し出した両手をくれくれと上下に揺らしながら、ユーキはトーコに向かって言う。 「分かったわよ」 呆れ顔で弟を見やりながら、トーコはご要望どおり、大型スコップを3つ造る。 「氷のおうち作りは中断して、先にテーブル作りですね!」 口のまわりに餡子の粒をくっつけたサヤが、ぐぐっと拳を握る。それを見たラシュネスも、彼女のやる気に即発されたようだ。やっぱり、口のまわりに餡子の粒をくっつけたまま、 「美味しいお鍋料理のためですからね! がんばりましょー!」 エイエイオーと、拳を高々と振り上げる。 「あんた、口のまわり……」 何やってんのよと言いながら、トーコはラシュネスの口のまわりの餡子粒を取って自分の口に運んだ。それだけでは餡子のべたべたが取れないので、濡らした手ぬぐいを物質転送能力で取り寄せる。 「ぅにぃ」 口元を濡れ手ぬぐいで拭いてもらっている間、ラシュネスはおとなしくじっとしていた。サヤの方は、 「サヤお姉ちゃん、ここに餡子がついてるよ」 準に指摘され自分で取っていた。その後は、トーコが取りよせた手ぬぐいを借りて、自分で口のまわりを拭く。 「なかなか食べるのが難しいですね」 「それは、お前らだけだ」 はーっとため息をつく和真であった。 「──大体の人数も分かったし……引き続き頑張れ」 空っぽになってしまった鍋に、お椀やお箸を入れて、ジャンクは引き上げていく。トーコはこの場に残るようだ。 「日暮れまでに作業を終わらせないとね」 「そうですね。机も作らないといけないですし……がんばりましょうか」 作業、再開である。 ユーキ、グレイス、イサム、BDは引き続き、雪のブロック作りを行う。机作りは、ブロック運び担当者に任されることになった。 「机なあ……どれくらいの大きさがいるだろうな?」 ざくっと雪の上にスコップを突き刺して、和真が首を捻る。この人数がつける机となると、そこそこの大きさが必要だ。 「動けるスペース確保して残りを机ってことにすれば?」 「そうだな。そうするか。ちょっと、中に入ってテキトーに並んでみてくれよ」 「はーい」 いそいそと中に入ろうとする子供たちだったが、自分たちのお腹と同じくらいの高さの壁は、なかなか越えられるものではない。サヤも壁を越えることができなくて、おろおろしている。 「え〜っと……トーコぉ、中に入れてくださ〜い」 助走をつけてジャンプをすれば中に入れそうな気もするが、失敗がこわいので、ラシュネスは長姉にお願いすることにした。 「はいはい」 軽く肩をすくめたトーコは、《フロート》でラシュネスとサヤ、和真の3人を中に入れる。イグルーの中に入ったラシュネスと和真は、子供たちのわきの下に手を入れて抱き上げ、中へ運んだ。 「出来上がりが楽しみだね」 外から見るのと内から見るのとでは、雰囲気も違う。ぐるりと回りを見回して、準は期待に目を細めた。 「ここが中心ですよ〜」 イグルーの真ん中に立って、サヤが意味もなく万歳をした。 「お鍋って1つじゃないですよね?」 溝堀り係に抜擢された陸丸が、スコップにもたれかかりながら、首をかしげる。 「そりゃね。2つか3つはいるでしょ。この人数だもの」 「じゃあ、お鍋はどのへんに置くんですか?」 やっぱり真ん中だろうから、この辺かなと、準が移動する。 「1つそこに置くんなら、もう1つはここかな?」 準の立つ場所から少し離れたところに鈴が立った。少女は自分が立っているところに指で丸を描いて、さらに鍋と書く。準もそれにならって同じように丸と鍋という字を書いた。 「んじゃあ、そことそこに置くと仮定して、陸丸、あんたどこからなら手が届く?」 「えっとぉ……ここら辺かな?」 「鈴はどうだ? 届くか?」 「う……あ、あたしは、もうちょっと近くないと届かない」 「じゃあそっち側を子供席にするか」 「私はここからで大丈夫です!」 子供たちとは反対側の方に回って、サヤがわきわきと指を動かした。その半歩後ろで、ラシュネスが「私はここで〜す」とやっぱり指をわきわき動かしている。 「あんたらはいーのよ、別に」 「分かった、分かった」 これで机の大体の大きさが決まったようだ。早速、目安をスコップでつけて、掘りにかかる。 「深さはどれくらいだろうな?」 「後でラシュネスに座らせたら?」 答えるトーコもスコップを使って雪を掘っていた。彼女の反対側では、ラシュネスも掘っている。 掘った雪は机の上に盛られ、準とサヤ、鈴が平らに伸ばしていく。ある程度掘ったところで1度ラシュネスを座らせた。 「どう?」 「ん〜……高さはこれくらいでいいと思いますよ。あと、机の下を少し掘ったほうがいいと思いますー」 今のままでは机と少し距離が開いてしまい、ちょっと不便なような気がする。 「なるほどね。よし。掘れ、ちみっこ」 トーコがパチンと指を鳴らすと、上からガーデニング用の小さなスコップが降ってきた。これを使って掘れ、ということらしい。 「よおっし!」 腕まくりをしたい気分で、鈴はスコップを手に取った。準もそれを手に取り、「もうちょっとだもんね!」と気合を入れなおす。 「どう? 机はできた? って、うわ、張り切ったねえ」 ブロック作りの作業を抜け出してやって来たユーキは、イグルーの中に現れた机に目を見張る。 「立派なのができましたよ〜」 にこにこと笑いながら、ラシュネスが振り返った。初めはサヤの思いつきだったのだが、鈴や準もその気になって、机に装飾を施し始めたのである。結果、 「すごいね」 机の縁に雪だるまや動物のレリーフが浮かび上がることになったのだった。 「今までで一番張り切ってたからな」 途中で見学に回っていた和真が、肩をすくめる。熱心にレリーフを彫っていた子供たちは、照れくさそうに顔を見合わせた。 「そろそろ休憩しない? 今、イサム兄さんとグレイスがお茶を淹れてくれてるんだ」 「本当ですか!?」 指先がだいぶ冷えてきていたので、温かいものが欲しかったところである。子供たちは、嬉しそうに目を細めた。 レリーフ作りが始まった時点で外に出ていたトーコを呼んで、外に出してもらう。 「うわ、すごい!」 ずらりと並ぶ雪のブロックに、イグルーの中にいた和真たちは目を見張る。 「これだけあれば、十分なんじゃねえか」 「オレたちだってがんばったんだから」 ふふんと得意げに胸をはり、ユーキは答える。そこへ、お茶の入ったカップの並ぶお盆を手に、グレイスがやって来た。 「みなさんもどうぞ」 湯気をたてるカップを彼らに配る。 「あったかーい」 カップを両手で持った鈴が、ほっこりと表情を緩めた。 「ふふふ。作業の様子はばっちり写真に撮ってあるわよ」 使い捨てカメラを見せながら、麻紀がにっと笑う。 「いつの間に……?」 全然気づかなかったと陸丸がつぶやけば、麻紀はますます得意げに笑うのだった。 「さて、後はブロック積んで、隙間を雪で埋めて、入り口の穴をあけるだけだな」 カップの中に残っていたお茶を一気に飲み干して、BDはぐるぐると肩を回した。 「入り口って、どうやって作るんですか?」 「ああ、中に入ったヤツがのこぎりで穴開けるんだよ」 上目遣いでたずねてきた準に答え、BDはトーコの肩をぽんと叩いた。「なあ、トーコ姉ェ」 「……何が『なあ』なのか疑問だけど、言いたいことは分かったわ」 苦虫を噛み潰したような顔で、トーコは一番上の弟の顔を見上げた。 「では、あと一息ですし、がんばりましょうか」 からになったカップを置き、イサムはブロックを置いてあるほうへ歩き出す。その後をBDが続き、 「カップはそこのお盆のところへ置いていてくださいな」 グレイスとユーキも追いかけていく。 「あたしも最後くらいは手伝わないとねえ……」 やれやれといった表情のトーコが、のんびりとした足取りでユーキについていった。 さすがにこれだけ人数が揃えば、作業はスムーズに進んでいく。子供たちが積み上げにくい高さになると、 「よっし。チビ共はブロックの隙間に雪を詰めてけ」 隙間風対策なので、しっかり詰めるように指示を出す。 「もう一息だね!」 早速その場にしゃがみこんで雪をかき集め、ブロックとブロックの隙間に埋め込んでいく。 「ちょっと、陸丸! あんた、大雑把すぎ!」 「え? そうかな?」 自分が担当したところと鈴が担当したところを見比べる。違いは、表面がデコボコしているか、いないかくらいだ。要は隙間風が中に入ってこなければいいのだから、問題はないように思う。けれど、 「そうよ! もっと丁寧にやんなさいよね!」 鈴のお気には召さないらしい。どいてよと、陸丸を退かせ、丁寧に表面を撫でていく。 「分かったよ」 こうなると少年の立場は非常に弱い。ほら、こうやるのよ! と見本を示す少女のやり方を、黙ってみていた。 「準、肩に乗れ。上の隙間も詰めなきゃな」 「うんッ」 しゃがんで背中を示す和真にうなずき返した準は、早速その肩に足をかけた。せぇのの掛け声で、和真は立ち上がる。 「うわあ!」 視線が高くなると、同じ世界も違って見えるものだ。それが嬉し楽しくて、「すごいや!」と歓声をあげる。 「カズマ……!」 「おまえはダメ」 期待のこもった眼差しで、袖を引っ張るサヤに、和真は即答した。彼女を肩車するのは、難問中の難問なのである。 「サヤさん……」 こめかみに指を当てて、グレイスはため息をついた。そんな年じゃないだろうというのは、稼働時間半年ほどの彼女にはふさわしくないような気がするし、重量について触れるのは乙女最大の禁忌である。 少し考えて、説教は諦めることにした。 「肩車は、大きい人にやってもらうといいですよ〜」 にこにこと笑いながら、ラシュネスが候補に上げたのは、アースパンツァーであった。 「なるほど! それもそうですね!!」 「そういう問題じゃないと思うけど……」 「天然って怖いわねえ」 作業の手を休めたユーキと麻紀が、呆れ顔できゃいきゃいとはしゃいでいる2人を眺めた。 「いくらなんでも、準さん、1人じゃ大変でしょう」 肩車の件に関してはノーコメントを貫くイサム。 「あ、じゃあ、オレが……!」 立候補したのは陸丸である。出遅れた鈴はちょっと残念そうな顔をしていたが、それには気づかず、陸丸はイサムに肩車をしてもらう。 今度は鈴に怒られないよう、グレイスが渡してくれる雪を丁寧に隙間に詰めていくことにする。 「トーコ姉ェ、これが最後のブロックだ。よろしくな」 台形に切ったブロックをスコップの上に乗せ、BDがイグルーの中にいるトーコに声をかけた。 「はいよ」 中にいるトーコは、子供たちが作ったテーブルを踏まないよう、宙に浮きながら最後のブロックを支えつつ、隙間にはめ込んだ。 「さあってと、それじゃあ、穴あけて脱出するとしますか」 ノコギリをくるりと手の中で回転させ、トーコは口角を持ち上げて笑う。 隙間に雪を詰め終わった子供たちは、出たり入ったりするノコギリをじーっと見つめていた。上から下へ、右半分、左半分とノコギリの刃は進み、 「とりゃっっ!」 両手で切り取ったブロックを押して、トーコが中から出てきた。 「開通したわよ!」 「やったあ!!」 トーコが外に出てくるのを待って、子供たちが順番にイグルーの中に入っていく。氷の家の中は不思議と暖かい。 「うわー。すごい、すごい!」 「机もいい出来ですよ〜」 ぱちぱちと手を叩き、子供たちは大はしゃぎである。 そこへ、荷物を満載にしたソリを引いてジャンクがやってきた。 「お、できたのか」 「ええ、何とか日暮れには間に合いました」 夕焼け色に染まった空を示しつつ、イサムは笑顔で彼を出迎える。 イグルー作りの後は、鍋料理作りが待っていた。シンプルに水炊きということになったのだが、この出汁を作るのにジャンクはほぼ一日中コンロの前に立っていた。 手羽先やら鳥の足を何時間も煮込んだおかげで、コラーゲンタップリである。ポン酢に好みの薬味を入れて召し上がれ。 「おいし〜っ!」 グーにした拳を上下に小刻みに揺らしながら、鈴が幸せオーラを全身から放出する。それは彼女に限ったことではなく、 「ちょっと熱いですけど、美味しいです〜」 サヤも気に入ったようだ。 「一杯どうよ?」 「おっと、すまねえな」 BDが差し出した徳利をお猪口で受けて、和真は中身を口に運ぶ。鍋を食べながらの熱燗もまた格別である。 「〜っ……旨い」 お猪口の酒を一息飲み干した和真は、BDに返杯をする。 「……たまにはこういうのもいいやな」 「ですわねえ」 お酒を飲んだせいか、頬を少し赤くさせて、グレイスも同意した。トーコは1人手酌でくぴくぴと飲んでいる。 イグルーの外を見回せば、他にも鎌倉が点在していて、そこでも鍋料理などが行われているようである。また、湖の上では夜釣りを楽しむ火も見受けられた。 いつもと違った冬の一日がゆっくりすぎていく。 |