戦力低下による著しい損傷を負ってドックに寄港していたラストガーディアンは、ほとんどの機能を回復しつつあった。慌ただしかった艦内も、ようやく落ち着きを取り戻し始めている。 そんな頃の草木も眠る丑三つ時。ひっそり静まり返った艦内だが、とある1区画だけ異様な熱気に包まれている場所があった。 扉には、『M同盟集会』なる張り紙がはられている。気後れしつつも扉を開ければ、喧々囂々たる議論が繰り広げられていた。 まるで悪の秘密結社の総会さながらの雰囲気で、集会はますます過熱していく。 「我々に必要なもの。それは、出会い! それは、きっかけではないでしょうくゎっ!」 「おー!」 「そしてぇっ! 現在っ、これらを得ることのできるぅっ、最善の状況にあるとワタシは推測するのでありますっ!」 「おおー!」 購買印の紙袋を被った男の熱演に、同じく紙袋を被った男たちの間にどよめきが広がる。 「今回、ドック駐留の同志たちの協力を得て、ワタシたちは、このような企画を立ちあげたのでありますっ!!」 ばばーんっ。 男の後ろにするすると広げられていく模造紙には、『ラストガーディアン勇者ロボ交流ダンスパーティー』と荒々しい筆文字で書かれていた。 彼いわく、勇者ロボの大半は召喚タイプであるため、日頃の交流が少ない。しかし、擬人化した今、ロボ間はもとより、他チームの人間、一般スタッフとの交流を深めるチャンスのはずだ。 一部のロボは親睦を深めようと、積極的に行動しているようだが、あくまで一部でしかない。そこで、交流の場を設け、強制的に参加させようというのである。 「むぉちるぉん、これはただの名目、建前であります! ダンスパーティー! それは乙女たちの憧れ(のはず)! 我々には、何一つ気後れすることなく、乙女たちに触れることができるというすんばらしいメリットがっ! それはつまり、我々の求める、出会いとなり、きっかけとなるのではないのでしょうくゎっ!?」 「おおーっっ!!」 M同盟集会は、一気に盛り上がる。 こうして、彼らが立ちあげた『勇者ロボ交流ダンスパーティー』は、購買部の協賛を得てブリッジに申請され、企画承認のハンコをぽんっと押してもらったのであった。 M同盟。正式名称を、マゾ同盟──ではなく、もてない同盟と言う。 |
オリジナルブレイブサーガSS お手をどうぞ |
|
「おはようございます」 格納庫の一角にある、ウィルダネス組の生息地。そこが、ココロのバイト先であった。いろんな意味で油断ならない職場ではあるが、いろんな意味で気楽でもある。何せ、雇い主には隠し事をしてもムダなのだ。“心”を演じなくても良いというのは、こんなに救われることなのかと、少し意外に思う。 「オハヨ。で、アンタはどうすんの?」 「は?」 持って来たエプロンを身につけながら、ココロは目をテンにした。質問の主は、雇い主の妹、トーコである。 「あの、何のことですか?」 「何って、これよ、これ。来る途中に見かけなかった?」 ぺらん。ココロの前に示されたのは、一枚のポスター。踊る男女のシルエットが描かれたソレには、『勇者ロボ交流ダンスパーティー開催!』と書かれている。 特筆すべきは、人間ロボ問わず全員参加と書かれているところ。つまり、ココロも参加しなくてはならないということだ。 「…………」 「アンタ、足きれいだし、足出さないともったいないわよねえ。スリット入ってるのがいいかしら? どう思う?」 「足に異論はないが、スリットはな──。ターゲットがあれだから、効果は望み薄かも知れん」 酒棚に並べた酒ビンを磨きながら、ココロの雇い主であるジャンクが答える。 「あ〜、そっか。そうよねえ」 ぺしっと額をたたいて、トーコ。 「じゃあ、膝丈のスカートかしらねぇ。プリンセスラインのやつでさあ」 「髪は上げるんだろ?」 「当然。ローブデコルテも外せないわよ」 兄妹の会話は続く。色は柔らかめの黄色かしらねぇとか、ヒールが高いのはやめたほうがいいだろうなとか。 「──はっ! あ、あの……何の話を?」 プリンセスラインとかローブデコルテとか、ココロには、さっぱり分からない。 「何って、アンタの着るドレスの話」 「それぐらいは出すから、心配するな」 「え!? あ、あの……私、踊れないんですけど……」 だから、参加しなくてはならないのなら、目立たないようにすみっこでひっそりと息を殺していようと考えたのだが── 「手ぇつないでくるくる回ってりゃ、それらしく見えるって」 ぱたぱたと手を振って、トーコはあっけらかんと笑う。 「いいんですか? そんなので……」 「上で講習会もやってるけど──。何ならあたしが教えたげてもいーわよぅ?」 カウンターにほおづえをつき、トーコはニマニマとココロを見ていた。 「トーコさん、踊れるんですか?」 「イエース。イイ男と踊りたくて覚えたし、可愛らしい娘さんと踊りたくて練習したの」 どうしてそんなに誇らしげに答えるのだろう。晴れ晴れと笑うトーコに、ココロは疑心の目を向けた。しかし、講習会に出る気にはなれなかったので、トーコに先生をお願いすることにする。 「……練習相手は、ユーキがいるから大丈夫ね」 「踊れるんですか? ユーキさん」 「とーぜん」 ココロの疑問に、トーコが胸を張って偉そうに答えた。ちょうどその時、ユーキが「ただいまぁ」と帰って来たのであった。 さて、格納庫でのやり取りとほぼ同じ頃。ダンスパーティー開催に向けて、踊れないメンバーのためのダンス講習会が開かれていた。 男性陣メイン講師は、パーフェクト執事、長瀬倉乃助とカイザードラゴン。それに白馬の騎士エリオス。女性陣のほうは、セレナ王女と神楽崎麗華、黒羽根暦。 開催日まで日数的余裕がないせいか、講習はびしびしと厳しく行われた。また、女性陣の中には、講師以外にもダンスを踊れる者もちらほらといて、 「左足前、右足斜め前、左足そろえて、少しターンしながら右足前──そうです」 「左足そろえて、右足後ろ……しーちゃん、うまいうまい」 空山姉妹と秋沢兄弟ペアのように、マンツーマンの指導が行われているところもあった。 しかし、指導を受けている秋沢兄弟は、動きがぎこちない。特に飛鳥のほうは、油が切れた機械のようであった。 「飛鳥さん、そんなに緊張すると、体がへんにこってしまいます」 「あ、ああ──」ぎくしゃくぎくしゃく。 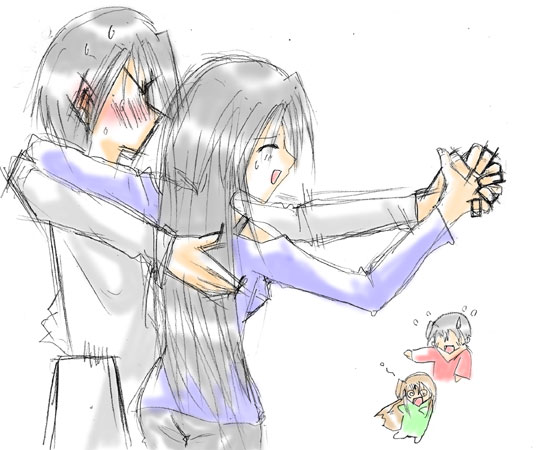 緊張しないでと言われても、触れた指先から伝わってくる体温、間近にある顔、聞こえてくる息遣いなどが、そうはさせてくれそうにない。 そんな彼らを、休憩ついでに見学しているのは、ドリームナイツの面々であるが、ダンス講師を担当している麗華の姿はない。 「大丈夫か?」 「えぇ、まあ。でも、いつ頭がパンクしても不思議じゃありませんよ」 大神隼人の気遣いに、田島謙治は、疲れ切った返事を返す。それを聞いた橘美咲が心配そうな顔を浮かべている。 「そんな顔しないでください。僕なら、大丈夫ですから」 日頃運動しないので、体のあちこちがガタピシ言っているような気がするだけだ。少しだけ、ブレイブナイツの御剣志狼の苦労が分かったような気がする。 「頑張って覚えないと、神楽崎さんにフラレちゃいますからね」 そうなのだ。ダンスの講座開催が決まった時に、「あんまり下手だと他のパートナーを探すわよ」と、彼女からハッパをかけられているのである。 せっかく格好つけられるチャンスが巡って来たのだから、これをフイにしては男が廃るというものだ。 「無理しないでね。謙治くん」 「えぇ」 とはいうものの、多少の無理をしなくては、麗華の試験をクリアできそうにない。頭では分かっているのだが、体がついてきてくれないのだ。初日とはいえ、先が思いやられる。 彼と同じような状況にある者は、ほかにもいた。例えば、ブレイブナイツのユマ。 「右足後ろ。左足斜め後ろ。右足、左足後ろ。右あ──ちが、左足! ああっ」 彼女がステップを間違うのはしょっちゅうである。 「気にするな」 恐縮するユマに、そっけない返事を返したブリットは彼女にバレないように、こっそりとため息をつく。 「うぅ……えぇと左足後ろで……」 「右に回れ」 「あぁ、そうでした」 ブリットの声に、ユマはしゅんとうな垂れる。 彼が、ダンスパーティーに乗り気でないのは百も承知だった。おそらく、参加するだけのつもりだったはずである。しかし、エリィが言うところの乙女ぱわ〜を発揮して、ユマがそこを強引に曲げさせたのだ。 「右のつま先で回転」ぼそ。 「はぅ」 誘っておきながら、この体たらく。ユマは眉間に力を入れて、きっと前を向き──またもや、ステップを間違えた。ブリットは彼女に足を踏まれないよう、ちゃっかりとステップを変更している。その結果…… 「──二人とも、それはワルツじゃないわ」 水衣のツッコミ通り、ブリット・ユマペアのダンスは、何やら別のものへと進化しつつあった。 そんなペアがいる一方で、すぐにコツをつかんで踊れるようになったペアもいる。龍門拳火・水衣ペア、並びに風魔柊・楓ペアがそうだった。 「くっそ〜。ずりぃぞ、お前ら!」 「抜け駆けかよ!?」 恨み節を口にするのは、御剣志狼と風雅陽平だ。志狼はエリィを相手に、陽平は光海を相手に練習に励んでいる。ちなみに、翡翠はすみっこにちょこんと座って見学中。 ダンスなんて柄じゃないという思いがあるのか、志狼と陽平からは、ぎこちなさがなかなか抜けてくれないのである。2人が口にした恨み節は、半分以上がやっかみである。 「うるせえな。俺だって、たまには格好いいところを見せとかねとだなぁっ──!」 「拳火のアニキの言うとおりだよ」 男性陣が反論すれば、 「いかなる場所でも忍びこめるようでなくては、忍者の名折れです」 「双龍舞踏拳は、舞踊だもの」 女性二人も反論する。さらに、 「はっはっは〜。楓ちゃんの言うとおりだぞ。馬鹿息子」 「頑張ってくださいね〜」 優雅にくるくる回転しながら通り過ぎる、風雅雅夫・風魔椿ペア。からかいに来たとしか思えない。 「おのれ、クソ親父」 陽平がわきわきと指を動かしていると、 「懐かしいねえ、リィス」 「ホントね〜」 エリク=ベルとリィス=ベルの別動隊が現れた。からかってやろうというオーラがありありと見えた父雅夫と違って、ベル夫妻は、幸せオーラを大放出中。 「エリィ〜、しっかり志狼君を鍛えるのよ〜」 「任せて、ママ!」 ワルツのリズムに乗って遠ざかって行く母親に、娘はぐっと親指を立てて見せる。 「おばさん……」 志狼は、がっくりとうなだれた。 パーティー開催の話を持ちかけられたとき、マッコイ姉さんは、1つの条件を出した。 「購買意欲を刺激する何かを──!」ずががが〜んっ。 背景に雷を落とし、マッコイ姉さんは主催者に訴えた。そこで主催者が出した提案は、『パーティーには盛装で参加すること』 それを聞いたマッコイ姉さんは、大満足し、早速、さまざまな衣装を調達してきた。 衣装はミーティングルームに運ばれ、さまざまなタイプのドレスが所せましと並ぶ。 「知り合いに声をかけたっすから、専門スタッフも派遣してもらってるっすよ〜!!」 ダンス講習会から遅れること1日。マッコイ姉さんは、意気揚々と衣装屋を開店させた。 「……こんなに気軽に出入りしてもらっては困ります」 ため息交じりに艦長は苦情を述べたが、マッコイ姉さんは、口のかたいスタッフばかりだからと太鼓判を押した。しかし、それだけの理由ですんなりと彼女たちを受け入れられる訳がない。ああ言えばこう言うといおうか、ブリッジ側の主張に、マッコイ姉さんは、 「しょうがないっすね。ここは、MIBもビックリな対策を実行に移すことにするっすよ」 にこやかに笑いながら、さらりと恐ろしいことを口にした。対策の具体的な方法を聞いてみたい気もするが、聞けば後でオソロシイことになりそうだ。 ありとあらゆる方法で、他方面のニーズに応えてしまう。それが、マッコイクオリティ。 上の方のやり取りなぞ露知らず、日常生活では、とんと縁のないドレスの数々に、女性たちはきゃっきゃとはしゃいでいた。 「あ……あの……」 花や星やらハートやらが飛び交っていそうな空間は、ココロにとって縁のないものである。居心地はかなりよろしくない。今すぐ回れ右をして帰りたいところなのだが── 「どうかされまして?」 淡い紫色のワンピースを手にとっていたグレイスは、小さく目を見張りながら、ぱちぱちと瞬きをした。 「どこかお加減でも悪いんですの?」 「いえ。そういうわけじゃないんですけど……。場違いって言うか……」 グレイスには色々とよくしてもらっているので、逃走するのは気が引ける。これがトーコだったりすると、「こういうトコロはだめなので、失礼しますっ」と逃げられるのだが。 「そんなことありませんわよ」 「そうでしょうか」 「そうですわ。それに、早めにドレスを決めてしまわないと、トーコさんの押し付けドレスに袖を通さなくてはならなくなりますわよ」 「あ……!」 グレイスの言葉に、ぴき〜んとココロが凍りつく。パーティーの開催を知らされた日、トーコが言っていた数々の専門用語がココロの胸中を通り過ぎる。 「あ、あの、プリンセスラインとかローブデコルテとか、よく分からないんですけど……」 これは一体、どういうものなんでしょうかと、グレイスに聞いた。 上半身を体にフィットさせて、腰から裾にフレアで広がった型のことをプリンセスラインと言い、ローブデコルテは衿を大きくあけ、胸や背をあらわにしたドレスの総称であると、グレイスは教えてくれた。 それを聞いて、ココロの顔色がさーっと青ざめていく。プリンセスラインはともかく、ローブデコルテは困る。 「分かっていただけたようですわね」 グレイスの確認に、少女はこくこくと何度も頷いた。そこへ、 「心ちゃん、顔色悪いけど大丈夫?」 ドリームナイツの橘美咲がひょっこりと顔を覗かせる。 「調子が悪いんなら、医務室に行ったほうがいいよ。心ちゃん、体弱いんだし……」 「あ、大丈夫です。何でもありませんから」 「本当?」 「本当です」 疑わしげな視線を送ってくる美咲に、ココロはニコリと笑いかけた。 彼女がココロを心配してくれるのは、本来の性格によるものが大きいのだろうが、どういうわけか、美咲の中で、ココロは病弱であると認識されているようなのである。 以前、美咲の前でココロは倒れたことがあった。その原因は空腹である。もちろん、美咲もそのことは知っているはずだった。 しかし、いつの間にやら、ココロが倒れたのは貧血によるものだと、彼女の中で認識が変わっていたのである。 「大丈夫ならいいんだけど、ムリはしないでね?」 本当に心配そうな顔をしている美咲に、ココロの胸がチクリと痛む。お気遣いありがとうございますと礼を述べ、ココロは話題を変えることにした。 「ところで、美咲さんもドレスを選びに?」 「そうなんだけど……こういうのってよく分からなくて」 麗華に相談できればいいのだろうが、あいにくと彼女はダンス講師のほうで忙しい。 「だったら、グレイスさんにアドバイスしてもらったらどうですか?」 「う〜ん……」 「わたくしでよろしければ、お力添えいたしますわよ」 「じゃあ、お願いしようかな」 「喜んで」 ほっと胸を撫で下ろしている美咲に、グレイスは優しげに微笑みかけた。 彼女たちから離れたところで「きゃー」という黄色い悲鳴が上がったのはそのときである。 「なんだろうね?」 「何でしょう? 隣から……みたいでしたけど」 女性に解放された部屋の隣は、男性に解放されている。あちらでも、パーティーに向けて、衣装選びが行われているはずだった。 「かったりぃ……」 誰もいないことをいいことに、剣和真はぼやく。あと10メートルも行けば、男性に解放された衣装室がある。とはいえ──ダンスぱぁてぃなんて参加するような柄ではない。 「全員参加なんて、誰が決めたんだよ」 もちろん、主催のモテナイ同盟である。そうでもしないと、参加者が激減してしまいそうだったから、というのが彼らの主張だ。 「盛装って言われてもな……」 面倒でしょうがないのだが、和真は20歳。友人知人の中には結婚するとか言う者が出現し始めてもおかしくない年頃である。 冠婚葬祭用のスーツを選ぶのだと思えば、少しは気が楽になるはずだ。そんな気構えで、ほてほてと衣装室に入りかけた時、 「カズマ! ちょうどいいところに」 「どうかしたのかって、なんつー格好をしとるんだ、お前はっ!?」 女性用衣装室から出て来たのは、ベルサイユのばらに出て来そうな、ごてごてしいドレスに袖を通したサヤである。 ごていねいにも、髪形もそれらしくいじってあった。パールチェーンを飾り、薔薇の造花を飾り──一体何を考えているのやら。 「メイアさんまで……」 御機嫌なサヤの隣では、同じようにごてごてしいドレスに袖を通したメイアがいた。彼女は、気恥ずかしそうに俯いている。 「これが正しいドレスだと、サヤが──」 「ドレスにゃ違いないだろうが……でも違うだろ」 とたん、えぇ!? とサヤの顔が引きつる。 「違うんですか?!」 「某歌劇団じゃねぇんだからよ」 言いながらも、和真の頭の中には一人の少女の顔がよぎっていた。その時、 「んん。似合ってるじゃない〜」ぱしゃっ。 カメラのシャッター音と共に西宮麻紀が現れる。きこきこと使い捨てカメラのフィルムを巻きながら、 「メイアさん〜、笑って笑って〜」 ぱしゃっ、ともう一枚。再びきこきことフィルムを巻き始めた時、男性用の衣装室の扉が勢いよく開き、閉められた。 ずるるる〜っとその場にへたり込むのは、短髪のオスカル──ではなくて、ブレイブナイツのヴォルネスである。 「こっちもお前の仕業か!?」 叫ぶ和真に、違うわよと麻紀は反論した。 「何でも私のせいにしないでよね」 ぷんすかと怒りながら、麻紀は唇をへの字に結ぶ。しかし、過去の実績があるだけに、いの一番に疑われるのは自業自得だと思われる。 「とても疲れてらっしゃるようですけど、大丈夫ですか?」 疲労の色濃いヴォルネスの顔を、メイアが気遣わしげに覗いた。ついでにどうしてそんな格好をしているのかもたずねる。 「こういう方面には詳しくないのでね、見立てて欲しいとスタッフの女性に頼んだのだが────」 「その服を勧められたと?」 ヴォルネスが着ているのは赤い襟に白のジャケット。銀糸の紐飾りに房飾り。背中にはマントまであった。まるで舞台衣装のようである。 「いや、強引に着せられた」 げんなりとした表情で、ヴォルネスはうなだれた。彼は、100人が100人とも振り返るような超絶美形である。誰が見ても文句なしに、白馬の王子様はハマリ役だと太鼓判を押してくれるに違いない。 となれば、こういう格好をさせてみたいという女性の1人や2人いても不思議ではなかった。さらにスタッフはマッコイ姉さんの知人の紹介によるものだと考えれば、その思いのたけを実行に移したところで、驚くようなことではなかろう。 ヴォルネスの肩を軽く叩いて、和真は一言。 「ご苦労さん」 返って来たのは大きなため息であった。 「まぁまぁ、いつまでも落ち込んでたってしょうがないし。ヴォルネスさんも立って立って。他の人のじゃまになっちゃう」 「あ、あぁ……」 自分が座り込んでいた場所を思い出し、ヴォルネスはのろのろと立ち上がった。 彼の手を引いて立たせた麻紀は、ヴォルネスをサヤとメイアの間に押し込む。 「はぁ〜い。3人とも笑って笑って〜」ぱしゃっ。 満面の笑顔と共にピースサインを作ったのはサヤだけだった。ヴォルネスとメイアは、疲労感いっぱいの表情で、はぁと大きなため息をつく。 「信哉?」 「お、ヴェイル。どうかしたのか?」 男性用衣装室から、現れたのは盾の勇者ヴェイルであった。どうやら試着途中らしく、ブラウスの袖ボタンを留めながら、通路にひょっこりと顔を覗かせている。 「信哉を知らないか? 一緒にここへ来たんだが──」 いつの間にかいなくなっていたんだと、ヴェイル。信哉の性格を考えれば、彼に内緒でいなくなるようなことはないはずだ。 「俺は見てねぇけどな……」 回りを見回しながら、和真は答える。麻紀やメイア、ヴォルネスも知らないと顔を横に振ったその時── 「助けてー!」 女性用衣装室から転がり出てきた2つの影。1つは、ヴェイルが探していた道野信哉。もう1つは、和真の弟分とでも言うべき、佐々山準である。 「お前ら、何てカッコしてるんだ!?」 2人の少年の格好は、一言で言うなら、ドレスアップ魔女っ娘。信哉は明るいピンク色の基調にしたスカート姿で、胸には大きなリボン。ベルトのバックルはハート型である。準は白いスカートを穿いていた。腰には淡い青色のリボンを巻いている。 全員がアッケにとられる中、麻紀の記者魂だけは正常に稼働していた。持っていた使い捨てカメラのシャッターを押し、袖口から別の使い捨てカメラを取り出してぱしゃっ。さらにスカートのポケットからもう一つカメラを出してぱしゃっ。流れるような連続技は、名人技のようである。 「麻紀さんっ!?」 涙目で抗議する準から視線を外し、麻紀は、おほほほとわざとらしく笑う。 「今、写真撮ったでしょ!?」 「ええ?! そんな──」 被写体二人は、麻紀に駆け寄り、カメラを没収しようと立ち向かった。しかし少年たちは、自分たちをこのような目に遭わせた、首謀者の存在を失念していた。 「ふみゅぅっ。2人ともかーいいよぅっ」 淡い緑色のワンピースを来た空山ほのかが、少年二人を背後から捕獲。幸せそうな笑顔と共に、すりすりとほお擦りをする。 「ほのかちゃん、ナーイス」ぱしゃっ。 にんまりと笑いながら、麻紀は再びシャッターを切った。 「いい加減にしろ」 ぱこんと麻紀の頭を軽く叩き、和真は、ほのかの拘束から抜け出せないでいる少年二人を見やる。 「ほのかっ」 「ふみゅ?」 後ろから彼女を呼んだのは、リオーネであった。その瞬間、ほのかの腕の力が緩んだのをこれ幸いと、和真は少年二人を救出。 「返すぞ」 信哉をヴェイルに渡し、準は自分で抱え上げる。 「二人とも困ってるじゃないですか」 「ふみゅぅぅぅ」 呆れ顔のリオーネに引きずられ、未練たっぷりながら、ほのか退場。ヴェイルさんなら、魔女っ娘信哉くん&準くんの良さを分かってくれるよねッ?! という問題発言を残していった。 「…………分かるのか?」 信哉と準を交互に見比べてから、ヴォルネスはヴェイルに聞いた。 「──────いや」 聞かれた方は、まじまじと信哉を眺めてから、ほのかの発言を否定する。 その妙に長い間は何なんだよ、というせりふが喉元まで出かかっていた和真だが、今後のことを考えて、それは自重。ツッコミをため息に変えて、 「サヤ。2人の着替えを取って来てくれ」 「あ。そうですね」 言われて気づいたらしく、慌てて一歩踏み出したサヤは── べち。 盛大にコケた。ドレスの裾を踏ん付けてしまったらしい。 「あぅぅぅ」 「大丈夫ですか? サヤさん」 「はいぃぃ」 メイアの手を借りて、サヤは立ち上がる。いたたと、手で顔を押さえながら、サヤは衣装室へ入りかけて、またコケかけた。 「麻紀」 「分かったわ」 名前の後ろに隠れた和真の心情を的確に察し、麻紀は二人の後を追いかけて行った。 通路で悲喜こもごものコントが行われていた頃、男性用衣装室。ハンガーラックの谷を行き来しながら、陽平がパーティーで着るスーツを物色していた。 「どうも、ピンと来ないんだよなぁ」 何着か袖を通してみたが、動きやすいとは言えない。羽織袴も並んでいたが、こちらは論外だった。 「やっぱりあれだな。忍者の正装っつったら忍者装束……」 ひゅっ。 どこからともなく飛んできた矢が、陽平の頬をかすめ、 「うお!? 何やぁ?!」 遊び半分でラメスーツに袖を通していた西山音彦の頬を掠めて壁に突き刺さった。 びぃぃぃん……と揺れる矢は、『真面目にやれ!!』と鬼気迫る文字が踊るわら半紙をぬいとめている。 「ど、どこから?!」 あたりを見回せど、矢の発射ポイントは不明のまま。 陽平の背筋が、ぞぞーっと寒くなる。 彼から少し離れたところでは、ブリットがスーツを着用し、同じくスーツを試着している紅麗に「それはちょっと……似合いすぎていてコワいです」とか言われていた。 そんなこんなもありまして、パーティー当日。開催時刻は、夜の7時からということになっている。会場は、ラストガーディアンが収容されているドックがそのまま使用されることになった。 夜のパーティーに向けて、ダンスに自信のない者たちは、ミーティングルームで最後の練習に余念がない。 ラストの1音が奏でられるとほぼ同時に、室内に喧噪が戻ってきた。 そこにある顔は十人十色。ほっとした様子だったり、不安そうな顔、気難しげに唇を結んでいたり、満足そうに微笑んでいたり。 そんな中、田島謙治は、パートナーをつとめた神楽崎麗華の顔色を緊張した面持ちでうかがっていた。 「あ、あの……」 「まあ、これなら、ぎりぎり及第点といったところかしらね」 合格の言葉をもらい、謙治はほーっと肩の力をぬいた。心配そうに二人を見つめていた橘美咲も、麗華の答えを聞いてほっとしたようである。 「よかったね、謙治くん」 「ええ。努力した甲斐がありました」 「ギリギリ合格よ。ギリギリ!」 柳眉を逆立てるものの、麗華の頬にはうっすらと朱がさしていた。ツンとそっぽを向いて鼻を鳴らすが、照れ隠しなのは明白である。 日ごろ彼女にやり込められている大神隼人は、顔を反らして小さく吹き出した。直後、 獲物を狙う猛禽類のような視線が飛んで来る。 つい逃げ腰になった所、ため息をつきながら、カイザードラゴンがやって来た。 「麗華さま……」 「カイザー。どうだった?」 「はあ……それが、パーティーの開催はご存じでしたが、全員参加とは気づいておられなかったようでして……」 「……らしいと言えば、らしいわね。あなたに確認して来てもらって正解だったわ」 額に手を当て眉間に皺を寄せて、麗華はため息をつく。 「分かったわ。早急に支度を整えてもらいましょう」 瞬時に自分のすべきことを判断したお穣様は、カイザードラゴンに問題の人物を連れ出すように言い付けた。 ドリームナイツから少し離れた所では、西山音彦が、どよ〜んとした雨雲を背負って丸まっている。壁の方を向いて、床に渦巻きをぐるぐる描いていた。 「そんなに落ち込まないでください」 その背中に話しかけるのは、セレナ王女である。彼女は、音彦が落ち込んで理由を、正確に理解していた。その隣では、道原大地が大丈夫だって、と握りこぶしを作っている。 「パートナーがいらっしゃるのは、ごく一部の方だとうかがっておりますし、パーティーが始まってから、どなたかお声をかけてみてはいかがでしょう?」 「マッコイ姉さんが、花屋を開くらしいしさ、それで何とか──」 音彦が落ち込んでいるのは、要するにパートナーがいないからである。そこのアナタ。いつものことだとか、言わないように。 「おおぉぉっ。リーダー発見!」 入り口からひょっこりと顔をのぞかせて、中をぐるりを見回していたのは、生活班の一人だった。彼は、あからさまにほっとした様子で、「いたぞ〜!」と外に向かって呼びかける。 どどどどっという騒々しい足音がしたかと思うと、数人の集団が室内に乱入。春嵐のような勢いで部屋の中をかき回して行った。 「何だったんだ?」 訳が分からず、大地はぱちぱちと瞬きをする。その横にいる王女も「さあ?」と首をかしげるばかりだ。 「あ、あら? 音彦さんは?」 「え? あ、あれ? どこに行ったんだ?」 周辺を見回してみても、音彦の姿はどこにもない。それもそのはずで、音彦は春嵐の集団の手により、室外に連れ出されていたのだ。 「何や何やぁ?!」 「我々には、やっぱりリーダーが必要なんすよッ」 御神輿よろしく、数人の男に担がれて、ああ、西山音彦、どこへ行く──。 音彦がなぞの集団に拉致られた頃、会場の設営準備は着々と進んでいた。手のすいているものは、積極的に手伝いを申し出ている。 そんな中、購買部のマッコイ姉さんは、せっせと花屋の開店準備に精を出していた。 「これはすごいな」 ずらり並んだ色とりどりの花たちに、白馬の騎士エリオスが目を見張る。 「こういう日に相応しくて、女の子が気軽に受け取れそうな贈り物っていうと、ミニブーケくらいしか思いつかなかったっすよ」 ブーケを並べる手を休めて、マッコイ姉さんは苦笑いを彼に向けた。普段の購買の品揃えレベルでは、花束などの需要には応えられない。そこで今回は、少し張り切って仕入れてみたのだ。 「エリオスさんは、沙耶香さんにっすか?」 「さすがというか──すっかりお見通しか」 悪戯っぽく笑うマッコイ姉さんに、エリオスは苦笑を向けた。 「個人的オーダーの受付は、あっちっすよ。私は品だしで忙しいっす」 彼女が指さした先には、ウィルダネスから来た異能力者の一人、イサムがいた。 彼はずらりと並ぶ切り花の前に立って、大きめのブーケを作っている。 「花屋の手伝いか?」 エプロンをつけて花バサミを下げた姿は、本格的だ。エリオスの声に振り向いたイサムは、報酬につられましたと苦笑する。 「報酬?」 「そこに、より分けてあるものですよ」 切り花は種類毎に分けて並べるものだが、イサムが示したバケツには、百合を中心に白や淡いピンク色の花が生けてあった。 「……ひょっとして、レディ・グレイスにか?」 「分かります?」 エリオスの予測に、イサムは恥ずかしそうに笑う。グレイスはロボットだから、物を贈っても仕方がないし、お菓子などでは味気無い。いろいろ考えた結果、花束を贈ることにしたのだと、彼は目を細める。 「なるほどな。それはいいかも知れないな」 「でしょう? エリオスさんは、沙耶香さんにですか?」 「分かってしまうか」 二人に連続して言い当てられると、何となく気恥ずかしいものがある。それをごまかすようにエリオスは、苦笑いを浮かべた。 その気持ちが分かるのか、イサムも細い目をさらに細めて微笑む。 「ええ。沙耶香さんに贈るなら、白でまとめたほうがいいでしょうか?」 「そうだな。他に水色も入れてくれないか。濃い色は避けて、淡い色合いの──」 「そうですね。スイートピーとかスターフラワーとか……そのあたりでしょうか?」 適当に花を取りながら、イサムは慣れた手つきでブーケを作っていく。エリオスはその手つきに感心しながら、時々言葉を挟む。 各自、いろんな思惑を抱えつつ、パーティーの時間が迫って来た。 「さあって、それじゃあ、そろそろ行きますか」 背中も胸元もばっくりVの字にカットされた、真っ赤なドレスに身を包み、ウィルダネスから来た異能力者、トーコは手にした扇を優雅にあおぐ。体のラインにぴったりと沿うドレスは、スリットがきわどい位置まで入っており、ゴージャスなドレープのしっぽもついていた。 「トーコ姉ェ、頼んどいたこと、覚えてるよな?」 「覚えてるわよ。でも、本気?」 「当然じゃねぇか」 飾り気のないブラウスとベスト、スラックス、という格好のBDは、腕を組んでふんと鼻から息をはく。 「要は、ダチを作れっつーことなんだろ?」 だったら、俺らみてぇなのはべっこに騒いだ方がいいに決まってらぁとBD。 「まぁ、アンタがいいんなら、いいんだけど」 軽く肩をすくめ、トーコは後ろのランド・シップを振り返る。シップの搭乗口から出てきたのはピンク色のエプロンドレスを着たグレイスだ。フリルやレースがあしらわれたそれは、彼女によく似合っていたが、グレイスを見るトーコの表情はどこか不満げだ。 「ローブデコルテはぁ?」 「着ませんと、申し上げたはずですっ」 唇を尖らせるトーコに、グレイスはそっぽを向いてキッパリ答える。 「ココロ嬢は? 出て来ないけど」 「──おかしいですわね」 グレイスがシップを出るときは、ココロも身支度を整え終えていたはずだ。 「ココロさん? 何か不都合でもありまして?」 「あ、あの……。本当にこの格好で行くんですか?」 シップの中をのぞき込むと、ココロはうつむき加減でドレスの裾をつまみ、じっと眺めていた。彼女が着ているのは、グレイスと一緒に選んだ淡い黄色のドレスだ。 衣装を合わせただけの先日とは違って、今日はグレイスが髪をいじっている。後ろ髪をアップにまとめ、髪に花をあしらったのだ。 「何を気弱になってますの。大丈夫。自信を持ってくださいましな」 ため息と共に呆れ顔を浮かべたグレイスは、強引にココロをシップの外に連れ出した。 彼女は、女の子としての自分を過小評価しているように思える。複雑な事情を抱えているのは、知っているが、そういう考えはよくない。これで、少しは自信をもってくれればいいのだけれど。 「きゃっ?!」 どうも、グレイスが相手だと、ココロの警戒心も薄れてしまうようだ。シップの外に引っ張りだされてしまったココロは、思わず体を硬くする。頭に浮かぶのは、マイナスイメージばかり。しかし、実際はその反対だった。 「ココロちゃん、似合ってるよ」 「かわいいです〜」 ぱちぱちと拍手をするのは、ユーキとラシュネスだ。 「ほら、ごらんなさいな。胸をはって堂々となさっていれよろしいんです」 「うつむいてると、せっかくのかわいい顔が台無しですよ」 思わぬ賛辞に、ココロは頬を赤くした。 「イサムの言うとおりだぜ。これから、ぱーっとやろうって時に、ショボくれた顔はするもんじゃねえ」 BDがからからと笑いながら言う。そんな顔をしてたら、何かあったんじゃないかと心配されるぞと、付け加えられ、ココロは顔を上に上げた。とたん、 「これで本命攻略は叶ったも同然!!」 ぐっと強く握った拳を振り上げて、トーコが言う。その隣で、ジャンクはこくこくとうなずいていた。 「あう……」 ココロは、がっくりとうなだれる。 「気負わなくても大丈夫。気楽に行こう」 ぽんと肩を叩いて、ココロを元気づけてくれたのはユーキだった。にっこりと笑いかけてくれる少年に、ココロはほっと胸を撫で下ろす。 ほぼ同時刻。別の場所。 「……小鳥遊さんお1人?」 ワインレッドのドレスを着た麗華は、ため息まじりにたずねた。案の定、問われた本人は、何のことでしょう? と不思議そうにしている。 やはり、肝心なことは、すこ〜んとキレイサッパリ抜け落ちているようだ。麗華のこぼしたため息には気づかず、小鳥遊は、 「おや、隼人君、きれいな花束ですねぇ」 隼人君が作ったんですかとのんきにたずねた。確かに隼人が持つ白の花束は、花屋のバイト経験を生かして彼が作った(作らされた)ものである。 「これは、おっさん用だ」 ため息をつきながら、隼人は花束を小鳥遊に押し付けた。 「え? 私……ですか?」 訳が分からなくてきょとんとしていると、 「あ、来ましたね。橘さん、成功したみたいです」 謙治が眼鏡のズレを直しながら言った。振り向くと、美咲がラストガーディアン艦長、綾摩律子の手を引っ張ってこちらに駆けて来るのが見えた。 「橘さん!? どこへ行くつもりなの?!」 「もう着いちゃいました」 律子を小鳥遊の前にずずぃと押し出し、美咲はにこにこと笑う。小鳥遊と律子は、ぱちぱちと瞬きを繰り返しながら、お互いの顔をまじまじと見つめている。 「では、小鳥遊博士、私共はこれにて失礼いたします」 ぺこりーと頭を下げたカイザードラゴン。ここから先の見物は、野暮というものである。さっさと撤退を始めた彼らだが── 「え? ちょっとみんな、どこ行くの?!」 美咲だけは、分かっていなかった。 「良いから来い!」 彼女の手を引き、隼人は「しょうがねぇなっ」と小さく悪態をつく。 肩越しに後ろを見ると、残された2人は、ぎくしゃくとぎこちない様子ながら、ぽつぽつと言葉を交わし始めていた。 その頃のパーティー会場。こちらは、すでにたくさんの人でにぎわっていた。主催者側からのお願いで、参加者たちはいくつかのグループに分かれて円を作っている。 ココロが振り分けられた円には、本命の呼称をいただいた獣虎陸丸の姿もあった。ダンスに不安があるのか、そわそわとしていて落ち着きがない。 隣にいる鈴から何か言われ、少年はあぅあぅ言っている。 そんな様子をココロは遠巻きに眺めているだけだ。 「姉ちゃんたちは、ああ言ってるけど、本当に嫌ならやめたっていいんだよ?」 「え? あ……その……」 不意に顔を覗き込まれ、ココロは下を向いた。隣にユーキがいるのをすっかり忘れてしまっていたようである。ウィルダネスの異能力者たちは、驚くほど場に溶け込むのがうまい。そこにいるのに、存在を感じさせないことが多々あるのだ。 「本当に嫌がってることをさせるほど、姉ちゃんだって鬼じゃないし」 嫌とか、嫌じゃないとか、そういうことじゃない。 「そうじゃなくて……いいのかな……って」 「いいに決まってるじゃない」 ココロの戸惑いを、ユーキはばさっと切り捨てた。ココロが複雑な事情を抱えているのは知ってるけどと前置いて、 「それでも、自分にウソをつくことほど辛いことはないと思うよ。そりゃあ、義理とか人情とか色々あるし、人の心って複雑にできてるからさ、単純にはいかないだろうけど。でも、まだ結論を出さなくちゃいけない時じゃないでしょ?」 「…………」 「だったら、悩めばいいじゃない。あせって結論出したって、いいことないよ」 「でも…………! 私はっ……」 彼らの敵なのだ。どんなに悩んでも、そのことはずっと変わらない。カインの指令内容が変われば、ラストガーディアンにもキバを向けることもあるのだ。 「はい。もう悩むの終わり」 「え? あの……今、悩めって……」 肩透かしをくらったようだ。ぽかんと口を開けるココロに、ユーキは頷き返す。 「うん。たくさん考えなくちゃいけないと思うよ。でもね、考えてばっかりいるのもよくないと思うんだ。だから、今日はもう悩むの終わり。楽しむことだけ、考えようね」 にーっこりと笑って反論を封じるところは、イサムにそっくりである。血はつながっていなくても、似通うところはあるらしい。 『れでぃーす あ〜んど じぇんとるめぇん! ただいまより、第1回交流ダンスパーティーを開催いたしまぁすっっ!!』 流れて来た放送に、「第1回?」と小さなツッコミが入った。 『まずは、この曲!! みんな、緊張をほぐしてくれぇい!!』 放送が切れると同時に、音楽がスピーカーから流れてくる。 ♪ ちゃららっちゃちゃららららっちゃっちゃっ ♪ 運動会などではおなじみの、フォークダンス定番曲オクラホマミキサーであった。 「わっ私、これ知りません!」 「簡単だから、大丈夫だよ」 うろたえるココロの肩を軽く叩き、ユーキは彼女の手をとってステップを踏み始めた。 「……盛装でオクラホマミキサーってのは、どうなのよ?」 整備班の青年に送られて次のトーコの相手になったのは、アースパンツァーであった。ロボットの時からの巨体がそのまま引き継がれたのか、トーコの兄ジャンクよりもさらに大きい。一言で言うなら、人間エベレスト。 「あぁそうか。これなら、アンタでも踊れるのか」 「ま、そういうこったな。けど、いつまでもオクラホマミキサーってわけにもいかねぇだろ」 けらけらと笑いながら、アースパンツァーは言う。社交ダンスは、身長差がありすぎると踊りづらいのである。それに、正直なところ、社交ダンスという柄ではない。 「だったら、BDと遊んでやってよ」 「何?」 「ダンスなんて柄じゃないって考えるのは、アンタだけじゃないってことよ。これが終わったら。隅っこの方で酒盛りするんだってさ」 「は! そいつぁいいことを聞いたぜ。そりゃ、ぜひともまぜてもらわねぇとな」 「そうこなくちゃ。んじゃ、後でね」 音楽はまだ少し続きそうだ。 ♪ ちゃっちゃらららっちゃ〜 ちゃっちゃっ ♪ 最後のちゃっちゃっに合わせて手を叩くのが、オクラホマミキサー終了時の定番である。曲が終わったとたん、会場は騒がしくなった。参加者のほとんどがパートナー探しに場内を移動を始めたからだ。 「トーコ姉ェ」 人と人の間をすり抜けて、BDがやってきた。そんなに酒盛りを心待ちにしていたのかと思うと、トーコの顔から笑みがこぼれる。「早いわね」 「まあな。あっちにあいてる場所があったからよ、そこで酒盛りしようかと思ってな」 「はいはい。あぁ、そうそう。アースパンツァーも誘っといたから」 雑踏をかき分けながら、2人は会場の隅っこに移動する。その途中、ブレイブナイツの侍チームと遭遇した。 「なんだ、お前ら居心地悪そうだな」 「悪そうじゃなくて、悪ィんだよ、実際」 ぱたぱたと手を振りながら、鋼牙は肩をすくめた。洋装の者が9割近い中、羽織袴姿の彼らは幸か不幸か人目を集めている。 「盆踊りなら誰にも負けねェ自信はあるんだがなァ」 「……初耳ですよ、土熊」 土熊のせりふに石鷹が、がっくりと肩を落とした。 「何が得意だろうが構わねェけどよ、居場所がねぇんなら、隅っこで酒盛りといこうや」 「何!? 酒盛り?!」 「居場所がねぇと思うのは、お前らだけじゃねぇってこった」 からからと笑いながら、BDはばしばしと彼らの背中を叩いた。 「そういや、アンタらだけ? 他の連中はどうしたのよ?」 トーコが問いかけると、侍3人は無言で、別方向を指差した。その先には、たくさんの女性に囲まれて狼狽しているヴォルネスと、蒼月に振り回されている紅麗の姿がある。 「……え〜と……ま、十人十色っつーことで」 あえてコメントはさけ、トーコはBDが見つけた酒盛りポイントへ向かった。 「よっ……《アポート》」 物質転送能力により、下に敷くレジャーシートが召喚された。4人がそれを敷いている間に、続けて樽酒を召喚する。そのうち人も増えるだろうと、酒樽山脈を創作した。 「こいつぁすげぇな」 レジャーシートの上に上がりこんで1つ目の樽を開けようとしたとき、アースパンツァーがやって来た。 「遅ぇぞ、大将」 早くこっちに来やがれと、鋼牙が彼を手招きする。アースパンツァーは「悪かったな」と苦笑いを浮かべながら、シートの上に上がりこんだ。 「それじゃあ、まずは1杯」 酒を受けるのは、杯やコップではなく枡である。 「踊りにいかねぇのかい?」 「1杯ぐらい、ケチケチしないで飲ませなさいよ」 土熊の疑問に、トーコはふんと鼻を鳴らした。 「まぁまぁ」 唇を尖らせる彼女を、石鷹が慌ててとりなす。 「そうとんがるなよ、トーコ姉ェ」 「せっかくの酒の席だ。楽しくやろうぜぇ」 「分かってるわよ」 BDとアースパンツァーが苦笑をもらしながら言うので、トーコも小さく吹き出した。本当に腹を立てたわけじゃないので、機嫌もすぐ元に戻る。 改めて仕切りなおされ、全員が枡を片手に、「乾杯!」の言葉を口にした。 トーコがBDたちに混じって1杯飲んでいる頃、ラシュネスは、会場に用意された料理の数々に目を見張っていた。 「うわぁ〜すごいですぅ〜」 「あ! ラシュネスくんだ。あのねあのね、これっ。これがすんごく美味しいんだよ〜」 どてててっと近づいて来たのは、郵便戦隊の桃井皐月だ。1人なのかとたずねれば、 「みんなまだおナカすいてないからって、踊りに行っちゃった」 「そうなんですかぁ。あ、これ、おいしーです〜」 「でしょでしょ?!」 まだまだ(?)色気より食い気な2人であった。 ラシュネスたちから少し離れたところでは、勇者忍軍の姫翡翠が落胆した様子で飲み物のグラスが並んだ一角を見つめている。 「どうかしたのか? 翡翠」 「メロンソーダ……」 陽平の問いかけに、翡翠はふるふると首を振りながらぽそりとつぶやいた。 時間の経過と共に、会場はますます賑やかになっていく。特に女性陣のパワーはすさまじく、あの神崎慎之介を取り囲んできゃいきゃいやっていた。おかげで、ラスガー1の苦労カップルは2人の時間を満喫できたとか。 「もうっ。何回あたしの足を踏めば気がすむのよ!?」 「ごめんってば」 その一方で、鈴はぷりぷりと腹を立てていた。その理由は本人も言っているとおり、陸丸が足を踏むからである。 怒られている陸丸は、しゅんとうな垂れていた。 「鈴ちゃん、み〜つけたっ……と、どうしたの?」 「うわひゃっ?! ユッ、ユーキさんっ?!」 ふいに後ろから抱きつかれ、鈴は目を白黒させた。 「眉間にシワ寄ってるよ、鈴ちゃん。せっかくのかわいい顔が台無しになってる」 「かわっ……」 尻尾や耳がかわいいと言われたことはあったが、顔がかわいいと言われたのは初めてのような気がする。酸素を求めて池から顔を出す鯉のように、鈴は口をぱくぱくさせた。 「ねぇ、陸丸。鈴ちゃん、借りていい?」 「え? あ、う、うん。ていうか、オレが良いって言うのも変な話だし……」 「それもそっか。鈴ちゃん、1曲でいいからオレと踊って?」 ユーキはにこりと笑いながら、鈴を見た。 「えっ? いっいいですけど、別に──」 「やった! じゃ、行こう行こう」 いつにない強引さで、ユーキは鈴を引っ張っていく。訳が分からずに、陸丸がぽかんと口を開けて2人を見送っていると、あのっ! と緊張感一杯の声が後ろから聞こえた。 振り向くと、菜の花色のドレスを着た少女が頬を紅潮させて立っている。 「きみは……」 「ジャンクさんのところのバイトですっ!」 「あ、うん。そっか、そんな服着てるから一瞬誰だか分からなかったよ」 「……似合いませんか?」 「え!? あ、いや、そうじゃなくてっ! その……かわいいから」 最後の方は、ごにょごにょと口ごもってしまう、陸丸だった。一方、少女は少年の褒め言葉に、嬉しそうに表情を緩める。 「あ、あの……よかったら、私と踊ってくださいませんか?」 「え!? オ、オレ?!」 「だめ……ですか?」 「あ、いや、そうじゃなくてっ。オレ、下手くそだからさ」 「私もです。それに、手を繋いでくるくる回ってれば、それらしく見えるって、トーコさんが……」 「そうなんだ……」 楽しければいいのよ、というトーコの声が聞こえてきそうである。 まじまじと自分の手を見詰めた陸丸は、一度きゅっと握ってから、少女に手を差し出した。 「オレなんかで良かったら」 「ありがとうございます」 差し出された手を取って、少女──ココロは花のような笑みを浮かべた。 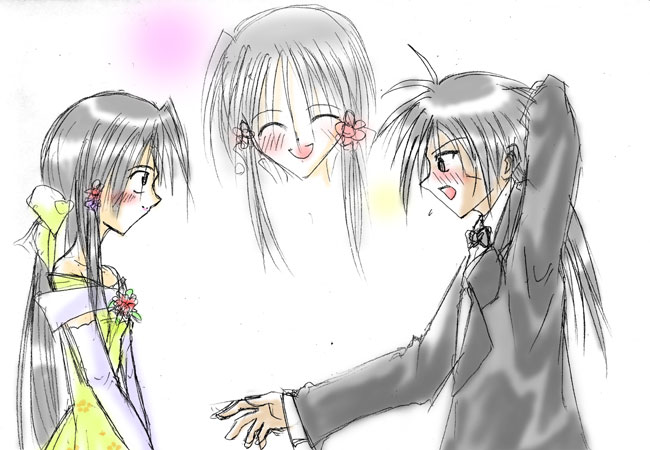 ココロが本命攻略に成功したころ、BDたちが酒盛り場から少し離れたところで、ジャンクはシェーカーを振っていた。彼が普段過ごしている格納庫の定位置がそうであるように、現在ジャンクが立っている場所も酒場のようになっている。 「助かった」 ぽつりつぶやいたのは、カオスであった。隣には、ほっとした様子の釧もいる。 こんなパーティーなど、参加する気はかけらもなかったのだが、いつの間にやら、パートナーの釧ともどもこの場に立たされていたのだ。 ラストガーディアンに戻ろうと思っても、何故か戻れない。仕方なく、釧と共に隅っこのほうで忍んでいたわけだが……ジャンクが酒場を設けたと聞き、逃げ込んで来たのだ。 「全員参加ってのは、ある意味酷だな」 シェイクした中身をグラスに空けながら、ジャンクは喉の奥を鳴らす。 「キサマ、向こうはいいのか?」 釧があごでしゃくって示した先では、トーコが楽しそうに和真を振り回していた。 「飽きた」 「……そうか」 ジャンクのしれっとした答えに、釧はそれ以上の返す言葉を持たなかった。所在無く無為に時間を過ごすよりは、心地よい沈黙のあるこの場で時間を過ごすほうが何倍もいい。 グラスを持ち上げ、1口2口と中身を喉に移した時、 「水をもらえないだろうか?」 矢尽き刀折れといった風体で、ヴォルネスが転がりこんできた。戦闘があったというわけでもないだろうに、かなりよれよれである。 その様たるやかなり悲惨で、あまり他人には興味を持たないカオスでさえ「何があった?」とたずねたほどだ。 「女性というのは、恐ろしいものだな」ぼそ。 ジャンクから水を受け取った、ヴォルネスは今にも儚くなりそうな風情で、視線を遠くに向ける。 何がなんだかよく分からないが、女性絡みで苦労したらしい。そんな彼の背中に、「あ!」という嬌声まじりの声が突き刺さる。 何かと思って振り向けば、20前後の女性たちが3人ほど、ヴォルネスの姿を見つけて、嬉々とした表情を浮かべていた。彼女たちは、今にもこっちへ駆け寄って来そうである。そうなれば、この居心地のいい空間は消えてしまう。 そう思ったとき、3人の背後から冷たいものが一瞬にして駆け抜けて行く。 「キサマ……何をした?」 ぎぎぎとぎこちなく振り返りながら、釧はジャンクにたずねる。心の温度が零下まで下がったような気分だった。 「うるさいのは嫌いだ」 グラスを口につけ、ジャンクはふんと鼻を鳴らす。用心深く、先ほどの女性たちを見れば、ヴォルネスへの興味など失ったかのように、全く別の方向に向かって歩いて行った。 具体的なことは分からないが、彼女たちの精神に手を入れるか何かしたに違いない。何のためらいもなく、他人の精神に手を入れてしまうジャンクの思考を恐ろしく思いながら、釧はふと浮かんだ疑問を口にした。 「あっちはいいのか?」 彼の言うあっちとは、BDやアースパンツァー、鋼牙たちの酒盛り組である。いつの間にやら整備班の面子などが増えていて、法隆寺がどうのと訳の分からない話題で盛り上がっていた。その話題には、郵便戦隊の赤沢卯月が顔を赤くしながら積極的に参加している。 「あれは、賑やかって言うんだ」 「そうなのか」 違いが分かるような、分からないような。むぅと口をへの字に結んでいると── 「あにうえ」 翡翠が現れた。後ろには、恐縮顔の孔雀と、むっつり顔の陽平、複雑そうな表情のクロス、センガがいる。 「あにうえ」 もう一度釧に呼びかけ、翡翠はくるりと回って見せた。一体何がしたいのだろう? 不思議に思いながら、釧は妹の姿を眺め続ける。 「褒めてやれよ」 「何?」 呆れ口調で言ったのは、ジャンクであった。彼はカウンターに肘をつくと、軽く身を乗り出して、 「お前さんがあんまりかわいいもんだから、褒め言葉も浮かばんらしい」 勝手なことを言う。 「キサマ……」 殴ってやりたい衝動と戦いながら、釧はジャンクを見る。 「あにうえ、ほんとう?」 下を見れば、妹が期待のこもった眼差しを向けてきていた。答に窮していると、ジャンクが強引に後ろから頭を押した。 「キサマ……」 後ろを振り返り、ぎっと睨めば、 「女を褒めてやるのは男の仕事だぞ」 そっぽを向いて、しれっと一言。グラスを傾け、中身を1口2口。加えて、陽平が必死で笑いをかみ殺しているところが腹立たしい。この憤りをどうしてくれようともてあましていると、 「お前も笑ってる場合じゃねぇだろ」 小さな豆のようなものが、すこんと陽平の頭に飛んだ。 「男の仕事、きっちり見せてもらおうか」 ニヤリと笑ったジャンクの視線は、陽平の後ろにいる桔梗光海に向けられている。清楚な白いワンピースを着た彼女は、気恥ずかしそうにうつむき加減で、陽平を見ていた。 「う……」ごくん。 思わず生唾を飲み込む陽平であった。冷や汗が額に浮かび、指がわきゃわきゃと動く。何と言えばいいものやら。釧の時のようにジャンクが助けてくれまいかと、すがるような気持ちで陽平は視線を後ろに向けた。 「何か飲むか?」 ジャンクの声に、翡翠は嬉々として「メロンソーダ!」と、答えていた。 一気に崖っぷちまで追いやられた気分である。五指が、わきゃわきゃ動く。そんな陽平の様子をまるっと無視して、カウンターは和気藹々とした雰囲気に包まれていた。 「ひでぇ」 思わずつぶやいた少年の肩を、クロスがぽんと軽く叩く。 「ヨーヘー……」 「なっ……何だよ」 遠慮がちな光海の声に、陽平は上ずった声を返した。変に動きがぎくしゃくする。と、 「今さらお見合いなんてするようなガラじゃないでしょうが! ほれ、さっさと踊っといで!!」 ど〜んと背中を突き飛ばされた。うわったったと、ずっこけるのをこらえれば、光海と急接近。 「おわぁっ!?」 陽平は慌てて飛びのき、突き飛ばした犯人に食ってかかる。 「何すんだよ、トーコっ!? って、いねぇ!!」 犯人はクロスとセンガの腕を引いて、「これだけの面子が揃ってりゃ、このコたちは大丈夫よね〜」などと言いながら、酒場のカウンターに向かっていた。 しかも、メロンソーダを受け取って幸せそうにしている翡翠に向かって、 「釧がいれば、陽平が側を離れてても平気よね?」とたずねたりしている。たずねられた翡翠は、こっちを見てしばらく考えた後、「へいき。あにうえといる」 「翡翠……」 陽平はがっくりとうな垂れた。 「ヨーへー……そんなに嫌なの?」 「え?! あ、いや……嫌とかそおいうんじゃなくてだな……」 上目遣いで視線を送ってこられ、陽平はどぎまぎする。 「キミがとってもキレイだから、ボクのハートはラテンのリズム。美しさは罪と言うけれど、あぁ! ボクにその罪は裁けない!!」 「べん、べんっ」 「お前らぁっっ!!」 芝居がかったキテレツなせりふは、トーコのものだ。その後を引き継いだのは、少し離れたところにいる酒盛り組である。どうやら、しっかり聞いていたようだ。「踊ってやれよぉ!」とか「困ってるじゃねぇか!」などの野次やら口笛やらがやかましい。 「うるせぇよッ!!」 ココから逃れたい一心で、陽平は光海の手を引き、ずかずかと踊りの輪の中へ消えていった。 「YEAH!」 「グッジョブ!!」 トーコと酒盛り組は、親指を立ててお互いを褒める。 「ほっほっほっほ。ぐずぐずしてンのが悪いのよ」 右手を腰に、左手を口元に当てて、トーコは悪女のごとき勝利のポーズ。何故か翡翠も同じようにポーズをとって、「ほっほっほっほ」それを見た釧が「真似をするな」と苦々しくつぶやいていた。  カメラは変わって別の場所。 「ほぅっ…………」 陸丸とワルツを踊った後、ココロは逃げ出すようにしてその場を後にしていた。どうして逃げ出したのかは、自分でも分からなかった。 会場の隅っこの物陰に隠れるようにして、ココロはその場に座り込む。 正体不明の暖かいもので、胸がいっぱいだった。 「シンデレラみーっけ」 「え? あ……ユーキさん……」 陰りに顔を上げると、笑顔を浮かべたユーキが立っている。シンデレラという単語に、ココロは目を丸くした。 「ガラスの靴を落とし忘れてるから、シンデレラにはなり損ねてるけどね」 身元もバレちゃってるしと、ユーキは言う。 「はい、これ。今日のこと、簡単に忘れちゃわないように」 さっと後ろから取り出したのは、黄色とオレンジの花束だった。出張花屋に並んでいたミニブーケより2回りほど大きい。 ココロはびっくりして、ユーキの顔を見た。 「あの……これ……」 「陸丸のかわりってところが、申し訳ないけどね」 苦笑いを浮かべてる少年に、ココロはぶんぶんと首を左右に振った。 「あ、ありがとうございます」 頬を紅潮させ、ココロは嬉しさ半分恥ずかしさ半分で、花束を受け取った。 「いい風ですわね」 パーティー会場からこっそり抜け出したグレイスは、人気のない岩場に来ていた。ここは、このドックの職員に教えてもらったスポットである。 海辺にほど近い岸壁の中に作られたドックなので、このような場所があるのだそうだ。 目を閉じて周囲に気を配れば、彼女と同じように会場を抜け出して来た者たちがいることに気づく。 「グレイス」 名前を呼ばれて振り向くと、目の前に大きな花束が振ってきた。驚きのあまり、口から小さな悲鳴が漏れる。 「──これは?」 花束を差し出しているのは、彼女のパートナーのイサムだった。彼は花束の他にもグラスを二つとカゴを1つぶら下げている。 「日ごろの感謝を込めて、グレイスに」 花束は、白と淡いピンク色が中心である。顔を近づけると、百合の甘い香りがした。 「ありがとうございます」 隣に腰を下ろしたイサムに、グレイスは幸せそうに笑いかける。 「こっちは食事とお酒──甘くて軽いやつを頼んだから、グレイスにも飲めると思うよ」 「そうですか」 イサムが差し出したのは、ピンク色のカクテルである。名前は、カクテルの色そのままに、ピンクレディと言うのだそうだ。イサムが持っているのは、真珠のような色合いのカクテルである。こちらは、ギムレットといって、辛口なのだそう。 もらった花束を膝に乗せ、グレイスはイサムに寄り添うようにして座った。 「こうして、一緒にいることの出来る奇跡に──」 「乾杯」 グラスがカチンと音を立てる。2人は幸せそうに微笑みを交し合う。 「何故だ……何故なのだ!?」 いくつかの幸せカップルが、会場の外で2人きりの時間を楽しんでいる頃のパーティー会場。主催者であるもてない同盟のメンバーは、悲しみに打ちひしがれていた。 理由は簡単。出会いのきっかけを作る、という本来の目的が果たされずに終わってしまったからである。 パーティー進行にあれこれ関わっているうちに、宴もたけなわ。参加者のほとんどは、すでに部屋に戻ってしまっている。残っているのは、会場の隅っこで酒盛りをしていた1部の者たち。こちらは、まだまだこれから、と言った雰囲気である。ちなみに、その半数以上が男性だ。 「くそぅ。一体何が問題だったんだぁっ?!」 もてない同盟の苦悩は続く。 |