オリジナルブレイブサーガSS うわさのカノジョ イラスト:阿波田閣下氏 |
|
「ヘーックショイ!」 万能戦艦ラストガーディアンの通路に、大きなクシャミがこだました。 「風邪か?」 ずずっと鼻をすすり上げたのは、御剣志狼。マイトと名付けられた不思議な力と艦内でも有数の剣の腕を誇る騎士である。 「やっぱ、上着を着てくればよかったな」 ほんの10分ほど前まで、彼は食堂の厨房を手伝っていた。お昼のピークも過ぎて、そろそろ休憩を取ろうかという時、郵便部に行って、食堂宛の荷物を受け取って来てほしいと、食堂の主、ハチミツおじさんこと八道から頼まれたのである。 志狼は二つ返事で了承し、着ていたエプロンを外して、食堂を出た。その時、エプロンをするのに邪魔で脱いでいた上着を着て来なかったのである。 今から戻るよりは、郵便部に行って戻った方が良い。それに、これくらいで風邪を引くほどやわな鍛え方をしているわけでもないのだ。 「ちわーッス」 何げなく郵便部のドアを開けた志狼は、 「くすッ」 という、不気味な笑い声に出迎えられて、ちょっと──いや、かなり驚いた。  窓口に座っているのは、タレ目と口元のほくろがチャーミング。さらに加えてその雰囲気が、すさみがちな現代社会のボクたちを和ませてくれるんだと、一部で評判。郵便戦隊の心のオアシス、緑川弥生であった。 しかも、彼女がカッターを握っているのに気づいて2度ビックリ。何でそんなアブナイものを握り締めて、「くすッ」なんて笑いがもれるのか。 疑問である。 緑川弥生は、癒し系ではなかったのか。 これでは、癒し系というよりは、電波系とか奇人変人の類いである。 逃げ出したい衝動に駆られた志狼だが、任務を放棄するわけにもいかない。志狼は勇気を振り絞って、 「あ、あのー?」恐る恐る声をかけた。 「あら、私としたことが……」 イスカ〇ダルまでイッていたかと思われた意識は、比較的簡単に戻ってきたようである。弥生は気恥ずかしげに頬を赤く染めると、 「ごめんなさいね」 上目使いプラス軽く首を傾けるという小技を使って、少年に頭を下げた。 「あ、いや……いいんスけど………」 志狼は顔の前でぱたぱたと手を盛大に振って、「気にしないでください」と彼女に伝える。 ついでに、さきほどの奇妙な光景については何かの見まちがいだろうということに落ち着いた。 「今日はどういったご用件でしょう?」 「ああ、あの……食堂宛の荷物を取りに来たんスけど」ハチミツおじさんに頼まれて。 しどろもどろで、志狼が用件を伝えると、 「ああ! そうでしたか」 この「ああ!」の後、弥生は、ぽむっと両手を軽くたたいている。彼女は、ラストガーディアン内ではあまりみないタイプのようだ。 なあんか、ペースが狂うよな。 かりかりと後頭部をかきながら、志狼は思う。 「卯月、お手伝いが来てくれましたよ〜」 「はいよ! 待ってました!」 弥生の声に答えたのは、ちゃきちゃきの江戸っ子娘であった。江戸っ子娘、赤沢卯月は、窓口横のドアを開ける。 「志狼が来たのか。んじゃあ、大丈夫だな」 「手伝いって、荷物は一つじゃないのか?」 ドアの下にストッパーを挟み込み、卯月は再び中へ戻って行った。 「一つだったらあたしが持ってくって。台車が全部出ちゃっててサ。食堂なら力のあるやつを誰か適当に捕まえられるだろうって思って、誰か手伝いを寄越してもらえないかって、連絡したんだ」 答えながら、前室へ出て来た卯月の頭には、ねじり鉢巻きが巻かれている。勇ましくも、頼もしく思える姿だ。 卯月は大きな荷物を一つ抱えていて、 「はい、これ。結構重いよ」 と言いながら志狼に差し出した。『重い』と彼女は言うが、とても重そうには見えないので、志狼はそれを何げなく受け取り── 「うお!?」 後悔した。 彼女が言うとおり、結構重かったのである。 危うく落としかけたが、マイトで筋力を強化させることで何とか持ちこたえさせた。 「ん? どした?」 「何でもねぇ」 ほーっと一息ついたところで、卯月を見る。 「なに?」 「何でもねぇ」 志狼の返事は、少しだけ呻き声にも似ていた。卯月は不思議そうに首を傾げたが、どうでもいいやと判断したらしい。 「そんじゃ、行こうか」 卯月は、両方の小脇に荷物を抱えている。そこそこに大きな荷物ではあるが、彼女は平然と笑っていた。 「ああ」 志狼はうなずくと、郵便部から出て行く。 「それじゃあ、行ってくる」 「行ってらっしゃい。そのまま、休憩を取ってくださいね〜。それと〜」 「分かってる。皐月を見つけたら、戻るように言っとく」 「お願いします〜」 簡単な業務の確認を終えて、卯月は志狼の後を追いかけて来て、 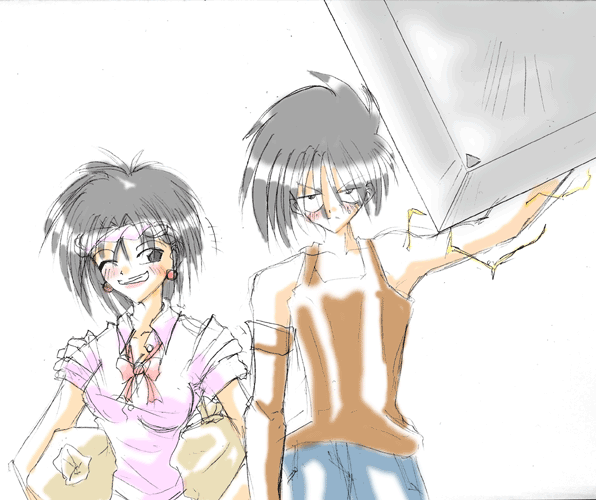 「そうでもねぇよ」 志狼の答えがぶっきらぼうなのは、マイトで筋力を強化して荷物を一つ持っているからだ。マイトで筋力を強化できない卯月が、平気な顔でこの荷物を持っていたことを思うと、「まあな」なんて、言う気にはなれない。 「……なあ、お前って異能力とかないんだよな」 「あるわけないじゃん」 「だよなあ」 一縷の望みをかけてみたが、あっさりと一蹴されてしまった。 「……ところで、この荷物。中身は何なんだ?」 「ハチミツおじさん厳選素材。マッコイ姉さんの目利きは信じてるけど、自分の目でも食材を吟味しないと〜、とかなんとか」 そう言えば、休みを利用して時々、朝市に出掛けるとか何とかいっていたような気もする。 「ふーん」 「あたしは料理なんて、あんまりしないんだけど、やっぱりそうなのかな?」 「そうだなあ」 はじめは料理の話題から始まって、次に食堂の厨房事情や、志狼の剣の稽古の話なんかに話題は変わっていた。 自分のことばかり話すのも何だしと思って、志狼は郵便部の仕事についてきいてみる。 「あの手紙のスクラップブック作るのって、結構大変そうだよな」 「そうなんだよ〜。毎日毎日、これでもかって量が来るからサ、片付けても片付けても追いつかなくって」 大変だと言っているわりに、卯月の顔は楽しそうに笑っている。どうやら大変なりに、楽しんでやっているようだ。 ペースが似ているのか、卯月との会話は全く苦痛がない。同じ年頃の女のコだと意識せずにすむのも志狼としては、ありがたかった。 そんなときである。 「あー! しろーくんはっけぇんっ!」 甲高い声が、前方から聞こえて来た。 「げ。皐月」 ぎょっと目を丸くしたのは、卯月である。 「しろーくぅんっ!」 皐月こと、桃井皐月は卯月の同僚であった。ツインテールにした髪が、ぴこぴこと上下にはねる。皐月はテテテーッと走り、 「あのねぇ、しろーくんっ。あたしね、しろーくんにお願いがあるのっ!」 「うわ、ばか! よせ! とまれ!」 卯月の制止も聞かず、ミニマムな小娘は志狼に突進。タックルをぶちかました。 「うお!?」 皐月のタックルに耐えられず、志狼は危うく引っ繰り返りそうになる。そこを── 「足でゴメンっ!」 卯月の足が背中を支えてくれたので、何とか引っ繰り返らずにすんだ。 「あのなあ!」危ねぇじゃねぇか! 志狼は、皐月を見下ろして抗議したが、 「しろーくん。お願い、お願い。この間のお昼に出てたお芋の煮物あるじゃない? あれのレシピを教えてほしーの」 全然聞いていなかった。 「ねぇねぇ、しろーくんってばあ。お芋の煮物のレシピ、教えてー」 志狼にくっついたまま、皐月が訴える。くっついているので、目線は真上に向かっており、おまけに瞳は期待でキラキラと輝いていた。 「皐月! あんた、まだ仕事中だろ!」 「お芋の煮物のレシピ聞いたら、戻るよ〜」 注意する卯月の方には顔も向けず、皐月は答える。 「煮物のレシピなんていつでも聞けるだろ!? 今、弥生しかいないんだから、早く戻んなよ!」 「ぶぅ」 「ぶぅじゃない! 志狼だって困ってるじゃないか!」 「ちぇ〜」 皐月は心底残念そうに眉尻を下げ、唇をとがらせた。名残惜しげに志狼から離れると、キッと卯月をにらみつけ、 「卯月ちゃんのバカあっ!!」 大声でどなりつけ、二人の前から去って行く。 残された志狼は、ただ唖然とするばかり。今のは卯月の言い分が正しいからである。 「ごめん。あたしじゃ、皐月はコントロールできないや」 「何もお前が謝らなくたって……それよりいいのか? ケンカしちまって」 しょぼんと肩を落としている卯月を、志狼は気遣わしげに見やった。 「あぁ、それは大丈夫。皐月のやつ、嫌なことは3歩歩いたら忘れるから」 ソレハ、彼女ガ鳥頭ダッテコトデスカ? その疑問は、飲み込んでおいた方が賢明に思える。志狼は「そっか」とヘンな返事を返して「とりあえず行こうぜ」とか何とか。 卯月も気を取り直したらしく、 「そうだな」と、笑顔をのぞかせた。 「ところで『あたしじゃ』ってことは、あのコをうまくコントロールできる人がいるってことなのか?」 真っ先に志狼の頭に浮かんだのは、郵便戦隊の隊長、白神葉月であった。が、卯月の口から出て来たのは別の名前。 「神無がね、皐月のコントロールは一番うまいんだ。あるかもしれない28の必殺技を使ってね──」 「あるかもしれない28の必殺技?」 何だそりゃ。 志狼が首を傾げると、 「や、あたしと葉月が勝手に言ってるだけなんだけど。ああも見事に皐月をコントロールできるのは、何か特殊な技があるに違いないって」 卯月は、ケラケラと笑いながら答えた。 「神無って……あのコを『小動物』呼ばわりしてる人だろ。もしかして、イジメられてるんじゃないかって、ウワサも聞くけど」 やや気難しげな顔立ちをした青木神無の顔を思い描き、志狼は卯月にたずねる。すると、卯月は「まっさかあ」とケラケラ笑い、 「神無はね、確かに取っ付きにくそうだけどサ、話してみると全然違うよ。第一、皐月がおとなしく苛められてるわけないって」 「まあ、苛められてるってヘコむタイプには見えねぇな」 皐月が走って行った方向へ顔を向け、志狼はつぶやいた。 「だろー?」 ちょうど厨房についたので荷物をハチミツおじさんに引き渡す。 「あ、シロー! お帰りぃ」 にこやかに手を振って志狼を出迎えたのは、彼の幼なじみ、エリス=ベルことエリィであった。どうやら、昼食を一緒に食べようと待っていてくれたらしい。 「じゃあね」 「おう」 卯月が手を振って離れて行ったので、志狼も手を振り返した。 「ねね、今のって郵便部の卯月ちゃんだよね? 何の話してたの?」 「何のって……別に」 必殺技、なんて単語を聞いてしまったので、できたらもう少し詳しく話を聞きたかったのだが。 志狼はそんなことを思っていたので、エリィの質問に対する答えは実に素っ気なかった。 素っ気なかった上に、目は卯月の姿を追いかけていたので、 「シローのバカ」 エリィは小さくつぶやき、幼なじみの足を思いっきり踏ん付けてやったのである。 「痛ッ!? 何すんだよ!?」 「あぁ〜ら、ごめん遊ばせ♪」 ちっとも悪いと思っていないカオで、エリィはしれっと答えた。 「…………」 エリィの虫の居所が悪くなったようだと察した志狼は、無用のトラブルを避け、それ以上何も言わなかった。 虫の居所が悪くなった理由については、志狼に理解しろ、という方がムリかもしれない。 それから、数日後。志狼は、格納庫に来ていた。暇なので、ウィルダネスから来た異能力者たちの所へ顔を出してみるかと、思ったのである。 近すぎず、遠すぎずの絶妙な距離感が、居心地よかったりするのだ。トーコに遊ばれることも少なくないが、格納庫だと、遊ばれる率は少ない。恐らくグレイスという、彼女の天敵とでも言うべき存在がいるからであろう。 それはともかく、格納庫をほてほて歩いていると、 「か・ん・な・ちゃ〜んっ!!」 皐月の甲高い声が、志狼の耳に飛び込んで来た。思わずそちらに目を向けると、 「何の用だ。小動物」 皐月の顔面を右手でつかみ、彼女のタックルを阻止している神無の姿が見える。 「デェトは、どうだったぁ〜?」 じたばたじたばた。 近づくなと、行動で示されているにもかかわらず、皐月は神無に抱き着こうとしているようだ。 「阿呆。そんな可愛らしいものじゃない」 神無はフンと鼻を鳴らす。 「え〜、でもでもでもぉ、いつもいってるカレシと旅行だったんでしょぉぉぉ?」 じたばたじたばた。 「電波の人は、彼氏じゃない」 「え〜、ちがうのぉ? カレシじゃないのぉ?」 じたばたじ──ごつん。 神無が、皐月の顔をつかんでいた手を放したため、少女は前につんのめり、コケた。 「うあ」痛そう。 彼女たちの様子を見ていた志狼は、思わず小さな悲鳴を上げた。 「ふや〜」 起き上がった皐月は、頭をぐらぐらと前後にゆらしている。医務室へ行った方が良いんじゃないかと、志狼は思ったが── 「ねぇねぇ、旅行は楽しかったの?」 「まずまずだな」 皐月は何事もなかったように立ち上がり、質問を続けていた。 「楽しかったってことはぁ、今はお友達のカレと、しょーらいてきに付き合うかのー」 足払い。ぼて。むく。 「ねねね、今はお友達のカレって、どー」 内股。ぼて。むく。 「旅行って、ドコに行って──」 大外刈り。ぼて。むく。 「……………」 卯月が言っていた通り、神無には28の必殺技とかあってもおかしくなさそうである。 彼女は、とても軽やかに皐月を転ばせていた。あの絶妙なタイミングは、真似をしようと思ってもできそうにない。 「おいしーもの食べて──」 「小動物」 「何?」 ぽんぽんと頭を軽く叩かれ、皐月は小さく首を傾げた。神無は生ぬるい笑みを浮かべて、 「土産をやろう」 さっと紙袋を一つ、少女の前に差し出した。 「うわあ♪ お土産? いいの? くれるの? ほんとに?」 皐月はぱあっと顔を輝かせ、大きな目で神無を見上げている。 「それはお前の分だからな。お前にやる」 「わっほ〜い♪ あんがとう。神無ちゃんっ! 愛してるよぉ、だぁい好きっ」 土産を受け取った皐月は、ほくほく顔で去って行った。 「………」 いーのか、それで。 るんたったった♪ とスキップで格納庫から出て行く皐月の背中を、志狼は何とも言えない複雑な表情で見つめていた。 そんな彼の肩を、ぽんと叩く人物がいる。振り返れば、たった今、鮮やかに皐月を追い払った青木神無であった。 すらりと長い手足の彼女は、いつもの気難しげな顔を少々崩して、フッと志狼に笑いかける。 「気にするな」 「はあ、でも……」 「気にするな。気にすると禿げるぞ」 「はあ………」 「君が気にしたところで、どうなるものでもないだろう。なら、気にしない方が良い」 「……そんなもんスかね?」 「そんなものだ」 こうもきっぱり言われると、そんなもんなのかと思えてくるから不思議だ。 「気にしないことにした君には、私からささやかなご褒美をあげよう」 「………はあ」 神無の言うご褒美とは、皐月に差し出した紙袋と同じ物であった。要はお土産ということらしい。 「君の父上や幼なじみの親子もびっくりの品だ。心して味わってくれたまえ」 やや時代がかった口調で言い添えて、神無は「ではな」と去っていった。 「…………」 一体何をくれたんだろうと、紙袋の中をのぞき込み─── 「──ッ!? これっ?!」 志狼は愕然となった。 紙袋の中に入っていたのは、志狼の家の近所にある和菓子屋の包みだったからである。 神無の姿を求めて顔を上げた時にはもう彼女の姿は格納庫から消えてしまっていた。 「ど……どーなってるんだ?」 何が何やらサッパリ分からず、志狼は呆然と格納庫に立ち尽くす。 「ふむ」 物陰に隠れて、志狼の反応を観察していた神無は、満足そうにうなずいた。 その後すぐに自室へ戻った彼女は、艦外へ向けてメールを発信。 『君のプレゼントは、我々にとって、とても有意義な物になりそうだ。感謝する』 送信が完了すると、満足そうにうなずき、自室から出て行った。 これからしばらく、郵便部の業務とは別件で忙しくなりそうである。 |