「そっちに行ったわ!」 「分かってる……って、うそだろ!? V字ターンかっ!?」 わぁわぁ、きゃあきゃあ。 普段は牧歌的なアイニー村が、ここ2カ月ばかりとても騒がしい。 村人はもちろん、ギルドを通じて雇った冒険者たちも一緒になってある物を捕獲しようと追いかけまわしている。 「くっそー……木馬だから表情は変わらねえはずなのに──何かムカつく……!」 握り拳を地面に叩きつけ、赤い髪の少年、拳火がチッと舌打ちをした。 彼が睨みつけているのは、50メートルほど離れた所に浮いている木馬である。 木馬はへとへとになって倒れ込んでいる捕獲者たちをあざ笑うように、1メートルほどの高さの所を悠々と浮いてウイニングランを決め込んでいた。 「ああ、もうっ! 何なのさ!? あの木馬っ!!」 拳火から少し離れた所で、怒りに指をわきわきさせているのは、ユーキである。 彼らがこの村を訪れてから早3日目。木馬を捕獲してほしい、という依頼は未だにはたせずにいた。 捕獲! 風の木天馬 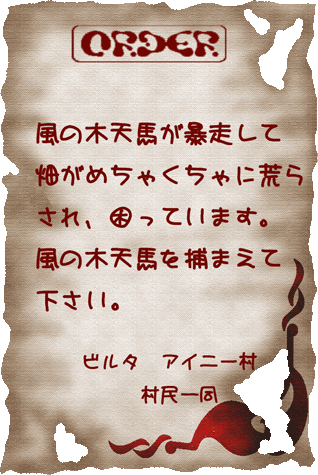 初めは簡単な依頼だと思ったのである。風の木天馬という玩具の暴走を止めるだけ。 たかが玩具の暴走である。それくらい簡単──そう思っていたのだが、拳火たちがアイニー村に到着して、早3日、結果は惨敗に終わっている。 「くそー。何の考えもなしに追いかけたんじゃ、絶対捕まえられねえぞ」 アイニー村に1軒だけある酒場兼宿屋。その酒場で、拳火はむすっとした仏頂面で豚肉のソテーをつついている。同じテーブルには水衣とユーキ、ラティアという、何とも珍しい組み合わせだ。 暴走する玩具の捕獲、という依頼遂行メンバーにラティアの顔があるのは珍しい。が、もちろん自主的に参加したわけではなかった。ブリザール一家の長であるマリーが、 「ワーウルフが家ン中にこもって本ばっかり読んでんじゃないよ! たまには運動してきたらどうなんだい」 と、半ば偏見に基づく好意を発揮し、強引に同行させられたのである。 マリーたちが暮らす浮遊島には、バノブルーが集めた魔法書や彼が書きとめた記録書などが山積みになっていた。その充実ぶりは素晴らしく、レクスやライフも1個人の所有物とは思えない、と驚くくらいである。思想が過激だからと言って発禁になった物や、秘密結社の秘術書、とある魔法使いの手記など、滅多にお目にかかれないような希少本が揃っているのだ。 真理の探究にいそしむ者としては、玉石混合ながら宝の山に遭遇したようなものである。ラティアは、寝食を忘れて読書に耽溺していた。 結果、マリーが指摘する通り、運動不足になってしまったのである。 「うう……まだまだ読みたい本がいっぱいあったのに……」 一家の長に追い出されては、従うしかあるまい。渋々外へ出たラティアではあったが、拳火と水衣、ユーキというメンバーを見てすぐに帰れそうだと思ったのだ。 拳火やユーキが、楽勝ムードだったのも理由の1つである。 アイニー村に到着するまで、ラティアは気分転換に来たつもりでいた。──が、日が暮れる頃には、この依頼は簡単に終わりそうにないなと察したのである。 「何か作戦を考えないとダメですよね」 大好きなハンバーグを切り分けながら、ラティアは頭の上の耳をぴくぴく動かす。 「楽勝って思ったけどさ、先読みが難しいんだよねー」 帳簿を左手で押さえながら、ユーキがハーブティーをがぶりと飲む。彼が持っているのはティーカップなどという可愛らしいものではなくジョッキであった。ヤケ酒ならぬヤケハーブティーである。フルーツビールが飲みたいと主張した彼だが、それは拳火に却下されてしまった。 「明日、捕獲に失敗すると採算が取れないね」 「明日捕まえれば、利益は出るということ?」 サラダを咀嚼してから、水衣が財布係のユーキにたずねる。 「一応ね。それでも出る利益は俺達の1日分の食費になるかな〜って言うぐらい」 「まあ、ないよりはマシってことか」 拳火の口からため息がこぼれた。 「私、思ったんですけど、あの木天馬には妖精がいるのかもしれません」 「妖精?」 3人の視線を受け止め、ラティアはうなずく。 そもそも、妖精はこの世に存在する物質・現象・概念・感情の数だけ存在する。つまり、人が認識できるかできないかは別問題として、風の木天馬という物がこの世に存在した時点で、風の木天馬の妖精というものが生まれるのだ。 「私たちは、玩具が暴走していると思っていたけれど、そうではなくて、玩具の妖精が暴走しているのが正しいと?」 「──多分。風の木天馬の動力になるマナは、それで遊ぶ子供が供給するものなんです。なのに、あれは供給する子供がいないのに動いています」 「子供の代わりに木天馬の妖精がマナを供給してるってこと?」 「そうじゃないかと……デッドリーマナの影響で妖精がおかしくなってしまうケースがあると何かの本で読んだ覚えがあるんです」 「なるほどなあ──って、それが分かったからって具体的な対策が思い浮かぶわけじゃねえけど──」 拳火の言うとおりであった。 風の木天馬という玩具は、子供がまたがると1メートルくらい浮き上がり、時速20キロほどのスピードで移動できる、という代物だそうだ。ちなみに、アイニー村をわがもの顔で闊歩している木天馬は、1メートルほどの大きさの物で、この手の玩具としてはやや大型の部類に入る。 拳火たちがいう先読みというのは、筋肉のはり具合やわずかな動き、視線や相手の思考などから次の行動を読みとるものだ。 しかし、木天馬には筋肉がない。 目玉も動かないので視線が読めない。 喋らないので、何を考えているのかも分からない。 まさに、3重苦! 人型であれば、ある程度の行動予測ができるものの、それすらできないのだ。 困ったものである。 翌朝、4人は今日が最後だと気を引き締め、風の木天馬を捕獲すべく、入念なストレッチを行っていた。この依頼を引き受けたのは彼らだけではなく、他にも20人ばかり、同じ宿に泊まって木天馬捕獲に執念を燃やしている。 村の中はライバルであふれていた。 もちろん、彼らも捕獲のためにあの手この手を考えては、挑んでいる。例えば、トラップ。しかし、木天馬相手に餌を使った罠を仕掛けても意味がないし、突っ込む足がないベア・トラップも同じである。どちらも、ちょっと考えれば分かることだ。 木天馬に通用する罠を考案できず、敗北。 眠っているところを捕獲しようとした者もいるが、相手は玩具。睡眠は必要ない。というわけで、こちらも失敗。たかが玩具ながら、中々手ごわい相手なのである。 ストレッチも終わり、いざ、最終戦と身構えたその時、 「よう! ぼーいず あんど がーるず! 迎えに来てやったぜ!」 「おっはよー!」 上空に日陰が差したかと思うと、見覚えのある蝉型メカが3機、上空から下りて来た。 「ラムとピンガ!」 蝉のような形をした小型飛行艇、スカルヘッドと呼んでいるそれを操縦していたのは、拳火たちが世話になっている空賊の子供たちである。 2人の名を呼んだユーキは「何でここに?」と目を丸くした。 「言ったろ? 迎えに来てやったってな」 スカルヘッドを地上に下ろし、ラムはひょいと肩をすくめる。この少年は、こういう仕草が絵になった。軽やかな身のこなしで地上に立ったラムと違い、もう1人の子供、ピンガは「よいしょ」とやや体が重たそうである。 「それで? 風の木天馬はどこ?」 背中のリュックサックを背負い直し、ピンガはにこにこと拳火たちを見上げた。 「あーっと……」 「ええっと──すみません。あそこです」 申し訳なさそうにラティアが指さすその先に、早朝のひとっ走りを決め込んで来たらしい風の木天馬の姿が見えた。 木目の肌の上で、水滴がキラキラ光っているのが何とも憎たらしい。 「玩具が汗をかくなんて……ね」 「朝露だと思うよ、ボク」 「そうね。でも、汗みたいに見えるわ」 ピンガの意見を聞き入れつつも、水衣は自分の主観を告げる。 朝の澄んだ空気とキラキラ光る水滴。まさに、早朝練習に励む運動部員そのものである。 「あ〜っ、クソ! 憎ったらしいったらねえぜ!!」 「おぅ……朝っぱらから はっするしてんな」 「うるせえよ! おい、ユーキ!」 「分かってるって! 絶対、捕まえる!! 捕まえたら、馬刺し──は無理だから、燻製用のチップにしてやる!!」 朝日の眩しさにも負けぬほどの闘志をきらめかせ、少年2人は木天馬を捕まえるべく、走りだす。 「あはははは。若い人は元気だねぇ……」 「──あなたがそれを言うの?」 発言の主は、どう見ても小学生。水衣たちよりも年下である。しかし、彼は人間の子供ではない。ホムンクルスなのだ。人間と同じように成長するとは限らない。 「……ピンガさん、お幾つなんですか?」 「あはははははは」 ピンガは笑ってごまかした! 「おぅけぃ……なら、先に用事を済ませてくるか。ピンガ、おめぇはどうする?」 「ボク、ここに残ってる」 「あい しー」 ぴょんとスカルヘッドに飛び乗ったラムは、3機の連結を解き、「昼までには戻る」 再び空の上の人になったのであった。 「お姉ちゃんたちも見学?」 酒場の前に積んである酒樽の上に登り、ピンガはリュックサックを下ろす。中から出て来たのは、モバイルパソコンのような物だった。それを膝の上に乗せて、少年は打ち込みを始める。何をしているのか少し気になるが、ピンガはブリザール一家が所有しているメカの整備や新しい道具の開発などに携わっているので、その関係の何かなのだろう。 うわぁぁぁぁ! 悲鳴に顔を向ければ、木天馬の首に投げ縄をかけた男が振り回されている。手を離せとか、放すなとか、好き勝手なことを叫んでいた。 「風の木天馬にしては、力が強いねえ」 ピンガの独り言を右から左へ聞き流し、水衣は捕獲隊の群れへ加わるべく向かって行く。ラティアも彼女に習った。 そして、昼前。 「おっかえりー」 酒樽の上に陣取っていたピンガは、戻って来たラムに声をかけた。 「あいむ ほーむ……っつか、まだやってたのかよ」 兄弟と目が合う位置でスカルヘッドをホバリングさせ、ラムは軽く目を見張る。少年たちの視線の先には、もはや遊んでいるとしか見えない、大人たちの姿があった。 依頼主である村人たちは、そろそろ諦めの境地に達しているようである。 「ねえ、ラム。これ見てよ」 「はん?」 ピンガが示したパソコンもどきの画面を、ラムは横から覗きこんだ。どうやら、風の木天馬の移動パターンのようであった。 「はーはん……暴走してても、オモチャはオモチャってことか」 「まあね〜。これを見て、ラムはどうする?」 「どうするだって? 分かってんだろ?」 「あははははは」 挑むような視線をラムに向けたピンガは、悪戯っぽい笑みを浮かべた兄弟に満足した。 「おめぇも乗りな。さっさと片付けて帰ろうぜ」 ひょいと顎をしゃくり、ラムはスカルヘッドに乗れとピンガを促す。少年は頷くと、パソコンもどきをリュックサックにしまい、それを背負って、兄弟の乗る小型飛行艇に乗りこんだ。 ピンガが乗ったのを確認したラムは、スカルヘッドを操作して空へ昇る。 「ラム!?」 木天馬に近付くスカルヘッドに気づいた拳火は、驚き声をあげた。 「何をするつもりなんですかぁー!?」 ひゃあと悲鳴のような声を上げ、ラティアが頭に手を乗せる。 「何って、捕まえるんだよ。さっさとな」 事もなげに答えたラムは、風の木天馬の真上にスカルヘッドを寄せた。 「ここを曲がれば、直線こーす……っ!」 ジャガイモ畑のコーナリングを綺麗に抜ける。ラムは、きらりと不敵に目を輝かせ、 「後は頼むぜ、ピンガ!」 スカルヘッドから飛び降りた! 「うわ!?」 「危ない!」 ユーキと水衣の声は、直後の歓声にかき消される。 「はっはー!」 ラムは風の木天馬にまたがり、風に揺られるままだったその手綱を取ったのだった。 手綱を握られては、もはやこれまでと諦めたのか、風の木天馬の駆けるスピードはみるみるうちに落ちていく。 「ていく いっと いーじぃー!」 簡単だったぜと、木天馬の上でラムが笑っていた。 ***************************** 「やれやれ。何とか黒字にしたかい……」 風の木天馬捕獲の収支報告を見て、マリーはふんと1つ鼻を鳴らす。 「ま、こんなもんだろうね」 「悪ぃ……その……あんまり稼げなくて──」 船長室へ、チームを代表して報告に来ていた拳火が決まり悪そうに頬をかく。マリーは片目を眇めると「アンタが謝るような事は何もないじゃないか」 テーブルに置いた酒のグラスを手に取り、それを一息に煽る。 「けが人なし、依頼遂行、収支は黒字。あたしゃ、文句を言うつもりはないね」 「けど……!」 「いい勉強になったろ。どんなに簡単そうに見える依頼でも、実際に現地に行って状況を確かめなきゃ分からないってね。ついでに言えば、依頼をしくじらない人間なんているわけがないんだ。落ち込むようなことでもないね」 分かったら部屋に戻ってゆっくり休みな。 「……分かった。この次はもうちょっと稼いでみせる」 「ああ。頼りにしてるよ」 部屋に戻って行く少年の背を見送り、マリーは酒瓶を手にとって、琥珀色の液体を空になったグラスに注いだ。そこへ「いやあ……懐かしいモンを見たわい」 ほくほく顔の夫は部屋に入って来た。嫌な予感がする。 「あの木天馬、フォルトーの魔法使い組合の研究室におった頃にワシが作ったもんだったんじゃ。いやあ……まだ残って現役で動くとは思いもよらんかったわい」 某貴族へ研究費をねだるつもりで作った物だったのだが──完成した直後に、贈るつもりだった貴族が横領罪で逮捕されてしまったという、曰く付きの品である。 「ま、おかげで人造妖精の作り方に道筋はつけられたわけじゃが──はて……その後はどうしたんじゃったかな?」 妻がコレクションしているお酒をおさめたキャビネットの前で、バノブルーが首を傾げた。勝手に戸を開き、その中からお気に入りの一本を取り出す。 「──ふざけんじゃないよ! 全く!!」 「うぉっ!?」 マリーの怒声と同時に、バノブルーの足元がぱかっと口を開いた。年よりの反射神経は鈍い。というわけで、彼はそのまま足元に出来た大穴に吸い込まれて行ってしまった。 「なんじゃー!? 何でこんなもんがあるんじゃー?!」 「酒泥棒捕獲のための罠だよ」 妻は鼻を鳴らして一言。酒泥棒は、アレで間違いないと確信しているのだが今のところ証拠がないので、ユマの協力を得てこのような物を仕掛けた次第。 琥珀の液体が揺れるグラスを片手に、マリーは落とし穴の縁へ近付いて中を覗きこみ、 「人造妖精なんて作れるのかい?」 中でトリモチまみれになっている夫へ話しかけた。 「作れるようにはなったがのー……コストがバカ高くってしょうがないんじゃ」 「……それじゃ、意味がないね」 「ないのう」 バノブルーは、トリモチゾーンからの脱出を早々に諦めたようである。腕だけ自由を取り戻すと、酒瓶のコルクを捻って、直接ラッパ飲みし始めた。 「妖精は上手く使えば便利じゃが──その半面、恐ろしい存在でもあるからの」 意味ありげにひょいと肩をすくめる夫。 しかし、トリモチまみれでは、威厳も減ったくれもありはしない。 「夕飯までにはそこから脱出するんだね」 酒を煽り、マリーは操舵室へ行ってくると、バノブルーに告げた。 「は!? マ、マリー? すまんが、脱出を手伝ってもらえるとありがたいんじゃがって……マリー!? マリーや〜い! ってうぉぅ、トリモチがぁっ!? マリー! マリーィィィ!!」 じじいの声は、船長室に虚しく響き渡るのみであった。 |